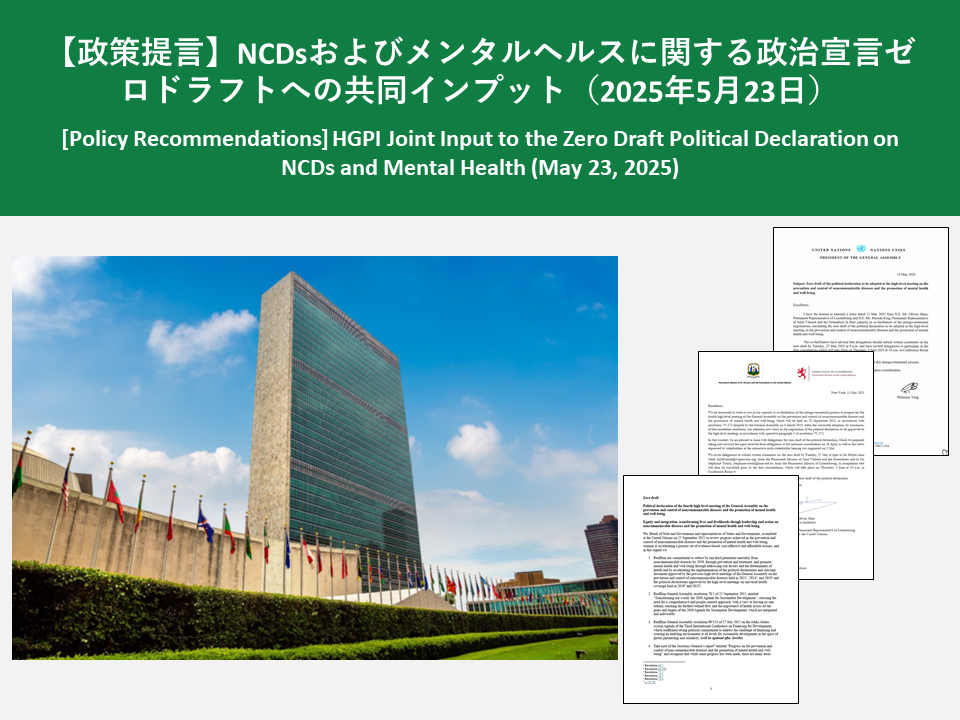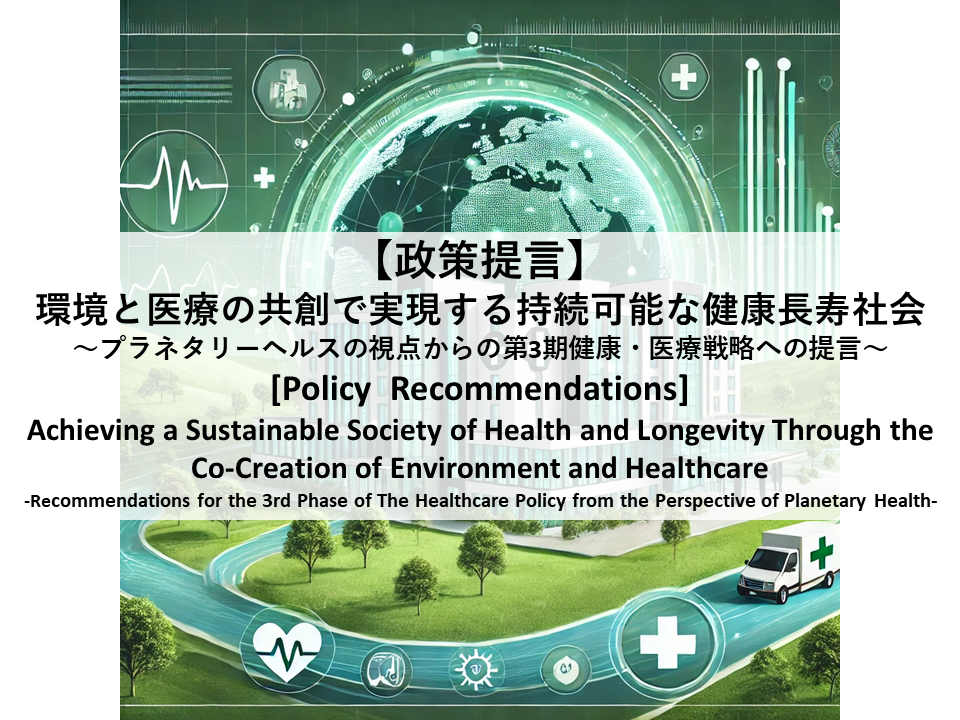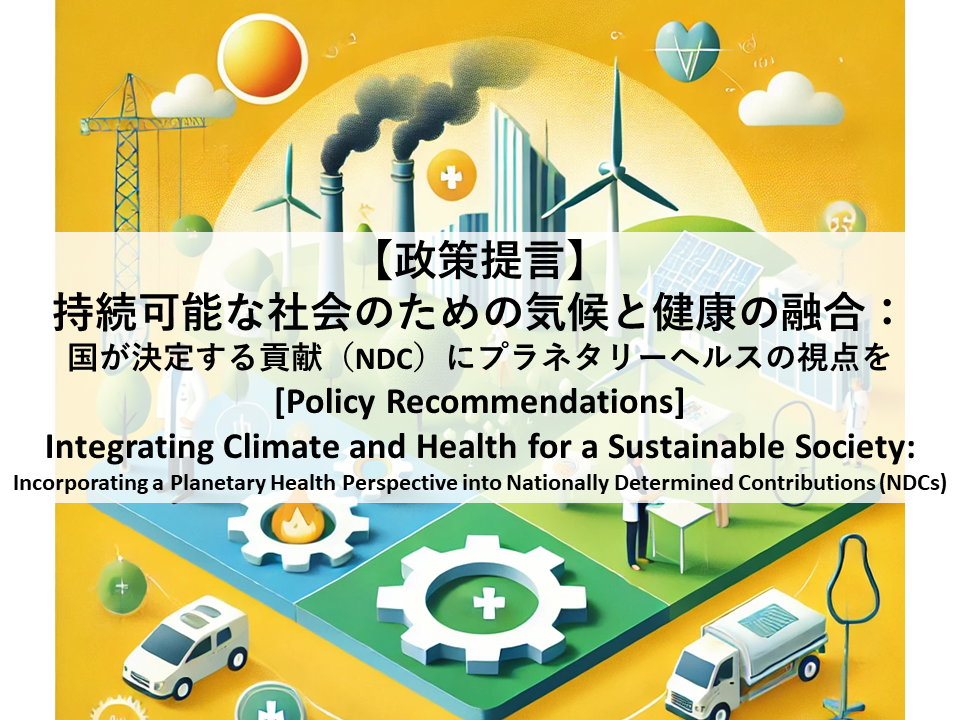【HGPI政策コラム】(No.60)―プラネタリーヘルスプロジェクトより―「第14回:『生物多様性と健康』に関する国際的・国内的な政策動向」

- 「生物多様性と健康」に関する政策的議論は、COVID-19を契機に国際的に加速し、「ワンヘルス」などの視点が各国の生物多様性政策に統合されつつある
- 国際的には「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」の採択に加え、健康との統合を促す「グローバル・アクションプラン」の策定が進み、生物多様性条約第16回締約国会議(CBD-COP16)ではその推進が確認された
- 日本国内でも「生物多様性国家戦略2023-2030」を通じて、生態系サービスと人間の健康の関連が明示され、里山・里海の保全や自然共生サイト等を活用した統合的な取組が推進されている
はじめに
近年、「生物多様性と健康」の関係性を重視する国際的な政策議論が急速に進展しています。とりわけ、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミック以降、生物多様性の喪失が感染症の発生と拡大を促進するリスクがあるという認識が国際社会全体に共有され、健康と環境の統合的なアプローチの必要性が繰り返し強調されてきました。今回のコラムでは、近年における国際的および日本国内の生物多様性と健康に関する政策動向について整理し、今後の展望を明らかにします。
「生物多様性と健康」をめぐる国際的な動向
- IPBES報告書と健康危機への警鐘
2019年に発表された、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム(IPBES: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)の「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」(以下、IPBES報告書)は、生物多様性や生態系サービスといった自然環境と人間の繋がりについて、科学的根拠に基づいて広範に分析した文書であり、以降の国際的な政策形成の基礎となりました。報告書は、森林伐採や農地の拡張、気候変動などによって生態系が著しく損なわれ、100万種以上の生物が絶滅の危機に直面していると指摘しています。これにより、人類が享受する自然の恵みである生態系サービスが失われつつあること、そしてこれが人間の身体的・精神的健康に直接的な影響を及ぼすことが明らかになりました。
特に注目すべきは、自然の寄与(NCP: Nature’s Contributions to People)の多くは人間の健康に不可欠であり、NCPの悪化は良質な生活を脅かすとの指摘です。NCPには、多様で栄養豊富な食品・薬品やきれいな水の供給、疫病や免疫系の調節、特定の大気汚染物質量の削減、自然とのふれあいを通じた心身の健康の改善など多種多様な恩恵が含まれます。そのため、自然の劣化は人々の便益を損ない、直接あるいは間接的に公衆衛生に影響を与え、医療アクセスや健康な食などに関して、現在ある不平等をさらに拡大しかねないとしています。IPBES報告書はこれらのリスクを警鐘とし、健康と環境の相互依存性を踏まえた統合的な政策形成の必要性を強調しました。
- COVID-19と環境保全の政策転換
2020年に発生したCOVID-19のパンデミックは、IPBES報告書で示された警告の現実性を裏付ける事例となりました。なお、2020年にIPBESは、パンデミックと生物多様性の関係性について論じ、パンデミックの制御・予防に向けて社会変革を促す政策オプションが必要であることを示したワークショップ報告書を発表しています。2022年には、国連食糧農業機関(FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations)、国連環境計画(UNEP: United Nations Environment Programme)、世界保健機関(WHO: World Health Origination)、国際獣疫事務局(WOAH: World Organization for Animal Health)の国際機関が連携し、「ワンヘルス共同行動計画」を立ち上げました。同年10月の世界保健サミットにおいて発表されたこの計画は、FAO、WHO、WOAHのワンヘルスに関する協力体制にUNEPを加えたことが非常に重要で、気候変動、土地利用の変化、環境の悪化等を含む健康リスクの要因について調査・分析しています。その結果、ワンヘルスのアプローチは、環境・動物・人間の健康を統合的に扱うグローバルな枠組みとして、国際合意の中心に据えられるようになりました。この議論は、2022年12月にモントリオールで開催されたCBD-COP15において、およそ190カ国が、2030年までに地球の陸と海の30%を保護し、生物多様性の損失に対して数々の対策を講じるという大筋の合意の形成に寄与しました。
この流れを受けて、国連生物多様性条約(CBD: Convention on Biological Diversity)における政策議論でも、生物多様性の保全が感染症予防、公衆衛生の向上、さらには健康格差の是正といった多面的な課題と結びつけて扱われるようになりました。こうした環境政策と保健政策の統合は、持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)にも整合するアプローチとして、今後さらに加速させることが期待されます。
- 昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)の採択と健康政策の補完
COVID-19の影響を受けて、国際社会では生物多様性保全の新たな指針として、「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF: Global Biodiversity Framework)」の策定が進められました。GBFは、CBD-COP15にて正式に採択され、2030年までに陸域・海域の30%を保全する「30by30」目標を柱としながら、2050年には「自然と共生する世界」の実現を目指す内容となっています。GBFには、人間の健康に関する具体的な言及が含まれているものの、その実施を支える政策や実行手段においては依然として課題が残されていました。
- 「生物多様性と健康」に関するグローバル・アクションプランの策定
そこで登場したのが、「健康と生物多様性に関するグローバル・アクションプラン(Global Action Plan on Biodiversity and Health)」です。このアクションプランは、GBFにおける健康分野の補完的文書として位置づけられ、感染症リスクの低減、都市緑地の整備、野生動物取引の管理、医薬品開発に必要な遺伝資源の保護といった具体的な行動を各国が講じるためのガイドラインとなっています。
アクションプランは、2023年に草案が策定され、2024年10月からコロンビア・カリで開催されたCBD-COP16おいて正式採択に向けた交渉が行われました。その位置づけは法的拘束力をもたない「自主的枠組み」ではあるものの、GBFの23のターゲットの実効性を高める役割を担うとされ、UNEPやWHOなどの専門機関が全面的に支持を表明しています。
このアクションプランには、四つの柱が含まれています。第一に、土地利用計画における健康影響評価の導入、第二に、生息地の急速な喪失が起きている地域での疾病監視の強化、第三に、野生動物取引の厳格な規制、第四に、医薬品の開発に資する遺伝資源やデジタル配列情報の保全と公平な利益分配です。さらに、抗生物質の不適切な使用と廃棄に関する規定や、化学物質や農薬による健康被害への対応策も盛り込まれており、包括的かつ現実的なロードマップとして評価されています。
しかし、CBD-COP16では、これらの措置を「義務化」するか「任意とするか」をめぐって、先進国と途上国、製薬産業と公衆衛生分野の間で意見の対立が続きました。最終的に、アクションプランは多数国の支持を受けて推進の方向性が確認されましたが、その採択は2025年以降に持ち越される見通しとなっています。
「生物多様性と健康」をめぐる日本国内の動向
国際的な議論の深化と並行して、日本国内でも「生物多様性と健康」の統合に向けた政策形成が加速しています。とりわけ、COVID-19のパンデミックを契機として、自然環境と人間の健康の相互依存性に対する理解が広まり、環境政策の中に健康を位置づける取り組みが国・自治体・企業・市民の多層的なレベルで推進されています。また、GBFの採択などの国際的な潮流を契機に、日本でも政策や施策や導入され、生物多様性の保全と健康増進に対して統合的にアプローチする政策として発展を続けています。
- 「生物多様性国家戦略」の改定と新たな健康視点の導入
このような中、2023年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」は、日本における生物多様性政策の根幹を成す文書として、国際的な枠組みである「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」との整合性を図りながら、「ネイチャーポジティブ」(2020年を基準として、2030年までに自然の損失を食い止め、反転させ、2050年までに完全な回復を達成する」という世界的な社会目標)の実現を掲げています。この戦略においては、健康に関する記述が明示的に盛り込まれており、生物多様性が人間の生命・健康・安全保障の基盤であることが改めて強調されています。
具体的には、戦略において「生態系サービスの持続的な享受」が掲げられており、その一環として、森林、湿地、海洋、農地など多様な生態系が提供するサービスの中に、健康への貢献が位置づけられています。例えば、都市部での緑地や公園は、ヒートアイランド現象の緩和や空気質の改善、精神的な回復機能などを通じて住民の健康増進に寄与することが科学的に示されています。また、農薬の使用削減や化学物質への曝露低減などの施策を通じて、公衆衛生への悪影響の回避も目指されています。
また、「生物多様性国家戦略」で注目されているのが、「里山・里海」の保全と活用です。かつて農村地域で行われてきた薪炭林の管理や棚田での耕作、海岸沿いの藻場・干潟の利用といった伝統的自然利用の形態は、生物多様性の豊かさを支えると同時に、住民の健康的な生活習慣を形成してきたという歴史があります。近年では、こうした里山的風景など「自然と触れ合うことが心身の健康に資する」というエビデンスが数多く示される中で、再評価が進んでいます。
実際に、森林セラピーやネイチャーツーリズム、地域住民による環境教育活動などを通じて、自然との関係性を回復し、健康増進と環境保全の「共便益(co-benefits)」を生み出す事例が全国で蓄積されています。とりわけ、過疎化の進む中山間地域では、地域コミュニティと連携しながら、医療福祉と連動した「地域包括的な自然共生戦略」のモデルづくりが進められつつあります。
- 30by30目標と自然共生サイトの登録促進
また、コロンビア・カリで開催されたCBD-COP16を受け、日本国内でも2030年までに陸・海の重要地域と生態系の保護面積を30%にする「30by30」目標の達成を目指す動きが始まっていています。ただ、法的に管轄する国立公園や自然公園だけでは要求される30%を賄えないため、民間にも呼びかけ、保有する緑地や森などの登録を推奨していています。国際的にはOECMs(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)、日本では「自然共生サイト」と位置づけられています。環境省は現在、企業だけでなく、大学や自治体などの公共・教育研究機関も含めた幅広い主体に対して、登録・協力を呼びかけています。2025年4月から、自然共生サイトを法制化した新法・「地域生物多様性増進法」が施行され、自然共生サイト登録の動きが加速しています。各国においてGBFの目標達成に向けた動きが強まる中で、日本国内においても自然関連の要求度が高まると考えられます。例として、汚染物の影響低減のため、製造現場での制約が厳しくなる可能性が挙げられます。また、啓発活動とともに、国家戦略としてのGBFへの対応は新たな規制となって表れてくるかもしれません。しかし、それらと同時に、環境技術の革新や新たなビジネスモデルの創出といった機会を提供するものでもあります。例えば、環境省が推進するネイチャーポジティブ経済移行戦略では、生物多様性の保全が企業価値の向上や新市場の開拓につながるとされています。また、自然共生サイトへの支援活動に対しては、環境省から支援証明書が発行され、企業の自然再興への貢献を示す手段として活用されています。これらの施策は、環境と経済の両立を目指すものであり、企業にとっては持続可能な成長を実現するための新たな道を開く可能性があります。
- 「グリーンインフラ」の導入と活用
生物多様性と人間の健康を同時に支える方策として、日本国内では「グリーンインフラストラクチャー」(以下、グリーンインフラ)の導入と活用が注目されています。グリーンインフラとは、自然の持つ多様な機能(例えば、雨水浸透、気温調整、景観形成、生息地の提供など)を社会資本として活用する考え方であり、生物多様性保全と気候変動適応、さらには住民の健康・福祉の向上といった多面的な便益を同時に実現するアプローチです。国土交通省は2015年以降、「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」の設置や、都市計画・インフラ整備の中での自然環境の活用を進めており、2020年には「グリーンインフラ推進戦略」を公表しました。この戦略では、都市の緑地や水辺空間を活用したヒートアイランド対策、防災・減災、地域の魅力向上、そして健康増進への効果が明示されています。また、国土交通省は厚生労働省、環境省などと連携し、グリーンインフラを地域包括ケアや高齢者の健康寿命延伸政策と結びつける動きも出てきています。具体的には、ウォーカブルなまちづくり、健康増進型公園整備、自然観察路の整備といった取り組みが、自治体レベルで進められています。
- 今後の展望と課題
日本における「生物多様性と健康」の統合政策は、国家戦略に基づきながらも、実行段階においては多くの課題も抱えています。例えば、農薬や化学物質による健康被害に関しては、農業や林業との調整、規制の強化、代替技術の普及など、科学と制度の両面での対応が求められています。また、都市部における緑地の確保といったグリーンインフラや30by30に関わる土地利用計画の課題も依然として残されており、これらに対する政策的・空間的対応をどう進めるかが問われています。
さらに、自然と健康との関係性を評価するための指標やモニタリング体制の整備も重要です。例えば、都市部における緑被率や空気質、あるいは自然環境が住民のストレスや不安をどのように軽減しているかといった評価指標は、エビデンスに基づく政策形成にとって不可欠となっています。現在、政府や自治体、研究機関が連携し、地域ごとの「自然と健康」に関する定量的・定性的データの収集が進められており、今後の政策の根拠として活用されることが期待されます。
まとめ
国際的には、グローバル・アクションプランの策定とCBD-COP16における議論を通じて、生物多様性と健康を結び付ける新たな政策枠組みが提示されました。国内においても、国家戦略や地方自治体の取り組み、里山・里海の保全や自然共生サイトの整備といった多様な施策を通じて、統合的なアプローチが着実に進められています。
今後は、これらの取組をいかに継続可能で効果的なものとし、地域住民の生活や経済活動と両立させていくかが重要となります。「生物多様性と健康」はもはや専門家だけの関心事項ではなく、全ての人々の暮らしと未来に関わる基本的なテーマです。今後の政策形成と市民参加の広がりが、自然と健康の共生社会の実現に向けた鍵を握っていると言えるでしょう。
【参考文献】
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services. https://ipbes.net/global-assessment (閲覧日2025年6月2日)
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2020). Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. https://ipbes.net/pandemics(閲覧日2025年6月2日)
- Food and Agriculture Organization, United Nations Environmental Programme, World Health Organization, & World Organization for Animal Health. (2022). One Health Joint Plan of Action (2022–2026). Working together for the health of humans, animals, plants and the environment. https://doi.org/10.4060/cc2289en(閲覧日2025年6月2日)
- United Nations. (2024). Biodiversity COP16: Important agreement reached towards goal of making peace with nature. https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/11/biodiversity-cop-16-important-agreement-reached-towards-goal-of-making-peace-with-nature-2/ (閲覧日2025年6月2日)
- Convention on Biological Diversity. (n.d.). Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. https://www.cbd.int/gbf/ (閲覧日2025年6月2日)
- Health Policy Watch. (2024年10月26日). Nations Deadlocked Over Health-Biodiversity Framework at COP16. https://healthpolicy-watch.news/nations-deadlocked-over-health-biodiversity-framework-at-cop16/(閲覧日2025年6月2日)
- 外務省. (2024年11月5日). 生物多様性条約第16回締約国会議等(結果概要). https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ge/pagew_000001_01063.html (閲覧日2025年6月2日)
- 環境省. (n.d.). 自然共生サイトに係る支援証明書について. https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/certificate/ (閲覧日2025年6月2日)
- 環境省. (2023年3月31日). 生物多様性国家戦略2023-2030. https://www.env.go.jp/content/000124381.pdf (閲覧日2025年6月2日)
- 環境省. (n.d.). 生物多様性と健康. https://www.biodic.go.jp/biodiversity/private_participation/health/index.html (閲覧日2025年6月2日)
- 環境省. (n.d.). ネイチャーポジティブ経済移行戦略について. https://www.env.go.jp/page_01353.html (閲覧日2025年6月2日)
- 環境省. 30by30ロードマップ. (2022年3月30日). https://www.env.go.jp/content/900518835.pdf(閲覧日2025年6月2日)
【執筆者のご紹介】
若田部 健太(日本医療政策機構 インターン)
山野 博哉(東京大学大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻 教授/国立環境研究所 生物多様性領域 上級主席研究員)
曽我 昌史(東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授)
菅原 丈二(日本医療政策機構 副事務局長)
ケイヒル エリ(日本医療政策機構 アソシエイト)
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)
- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)