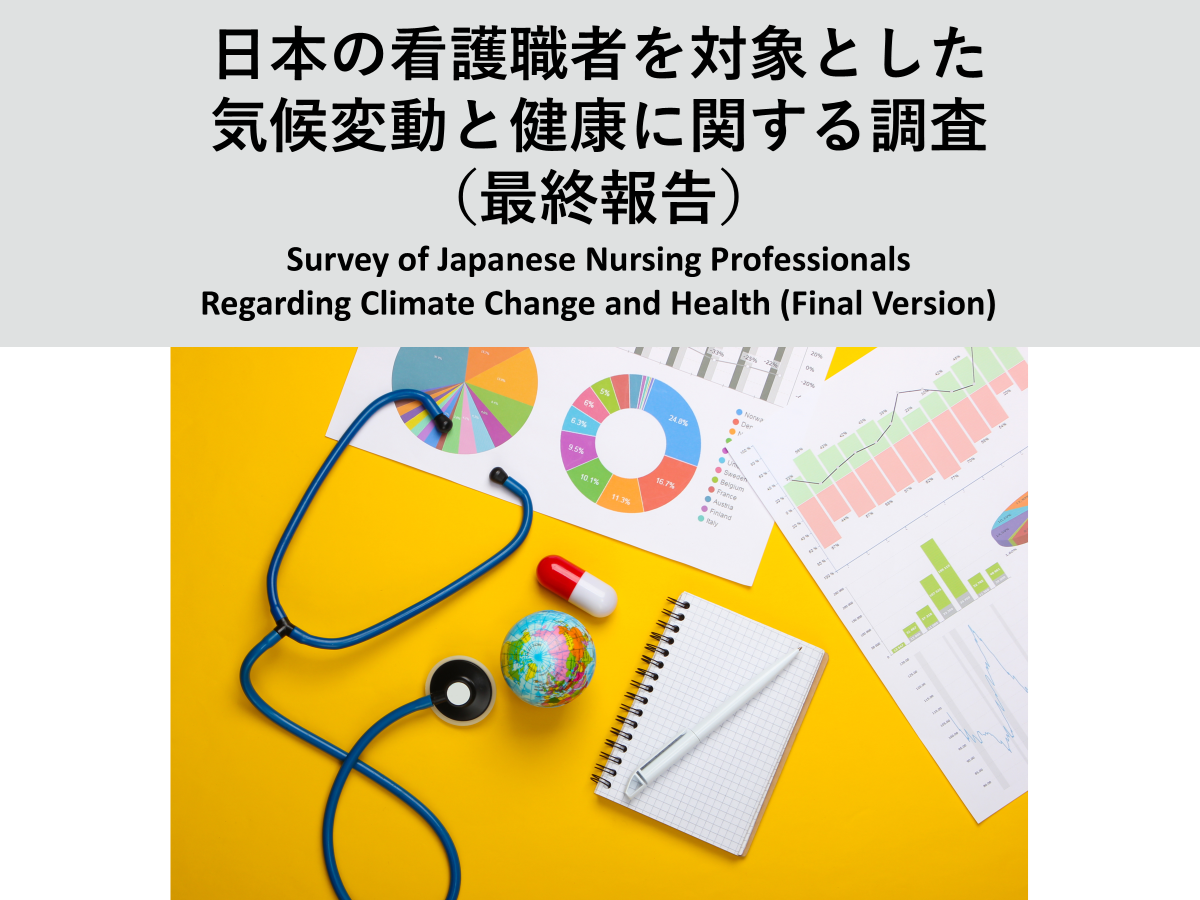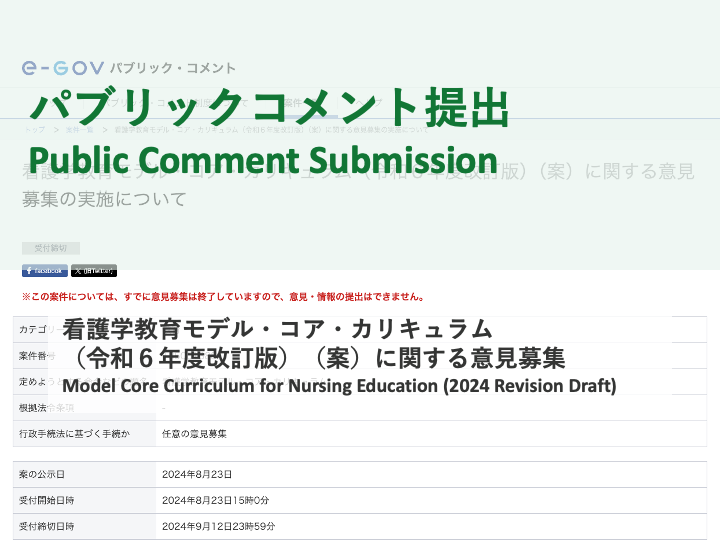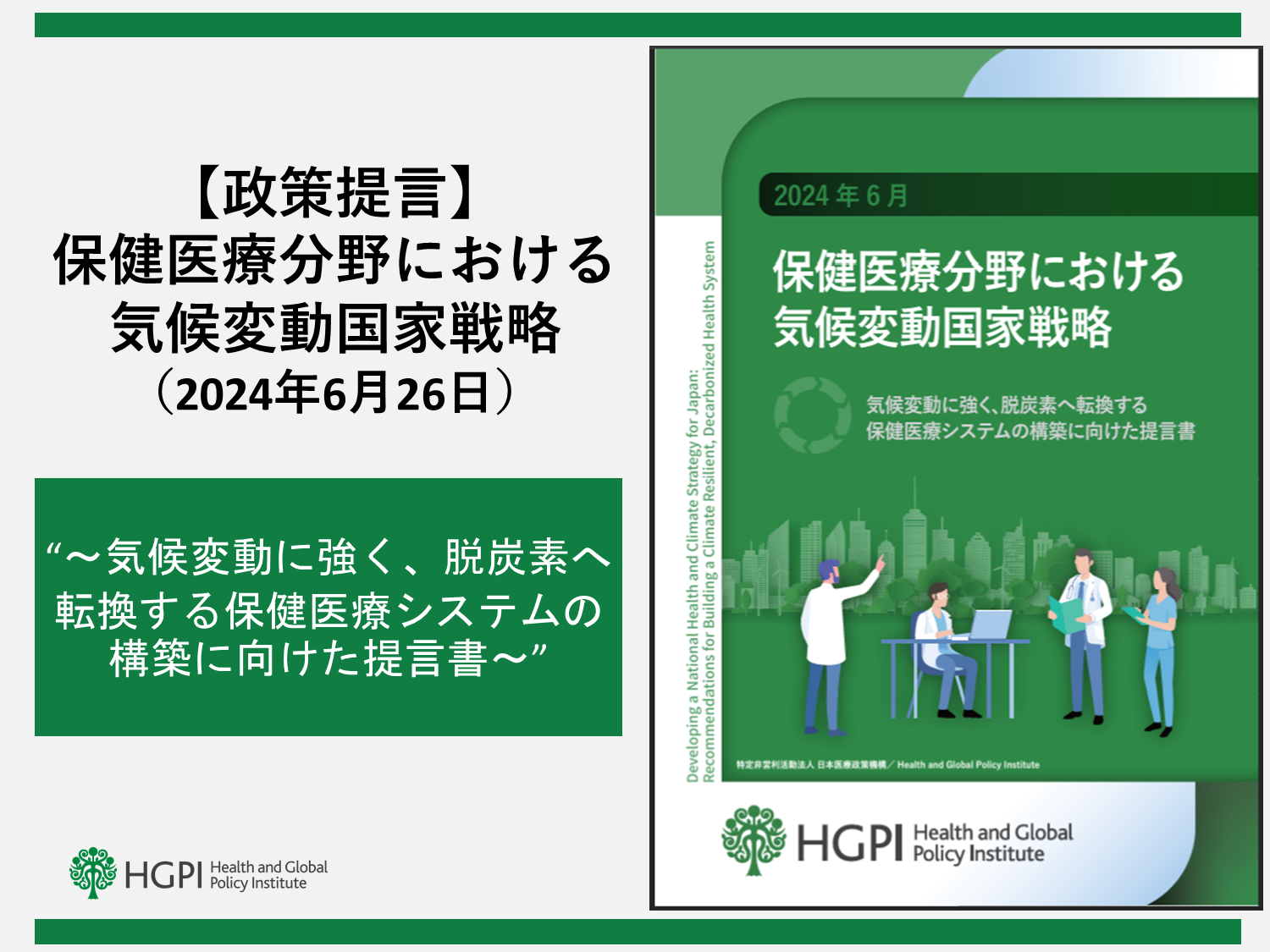【HGPI政策コラム】(No.59)―プラネタリーヘルスプロジェクトより―「第13回:人と地球の健康な未来を拓く看護: プラネタリーヘルスの視点がもたらす変革」

- 気候変動・感染症・災害の頻発など、複合的な社会課題が医療に影響を及ぼす中、看護職には地球環境を含む広い視野が求められている
- 看護学教育モデル・コア・カリキュラムに、「プラネタリーヘルス」の視点が初めて正式に位置づけられた
- 環境と健康の統合的視点の導入は、学部教育にとどまらず、現任看護職の学び直しや地域ケアの強化にもつながる重要な契機となる
はじめに
近年の社会環境は、少子高齢化・人口減少による医療供給体制の変容、そして新興・再興感染症の流行や頻発・激甚化する災害などの困難に直面しています。世界保健機関(WHO: World Health Organization)は全世界における健康と福祉への既存の脅威が観測されていると指摘しています。特に高温の影響は年々深刻化しており、日本国内でも高齢者を中心に熱中症による健康被害が急増しています。このような状況に対応するため「医療を取り巻く時代の変化に対応して自ら課題を設定し、論理的思考力、グローバルなコミュニケーション等によって、新たな価値やビジョンを創造し、積極的に社会を改善していく資質・能力を有する」看護人材の育成は喫緊の課題です。このような背景の下、文部科学省は2023年7月より「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」の改訂を開始し、新課程は2026年度(入学生)からの運用開始を予定しています。今回の改訂では、学んだ内容や時間などプロセスを重視するコンテンツ基盤型教育から、学生が卒業時点までに獲得すべき知識、スキル、態度・価値観などを4段階に構造化し、そのアウトカムを重視するコンピテンシー基盤型教育への転換が重要視されています。
プラネタリーヘルスとは:人と地球の不可分な関係
今回初めて「プラネタリーヘルス」という言葉が看護学教育モデル・コア・カリキュラムに追加されました。プラネタリーヘルスとは、人の健康と地球の自然システムの健全性が密接に関連しているという認識に基づく、学際的な研究分野であり、社会運動でもあります。気候変動や環境破壊は、単なる環境問題に留まらず、熱中症の増加、感染症の拡大、食料不安、精神的ストレスなど、多様な健康問題を引き起こす要因となります。私たちは、地球環境の危機が、私たちの健康の危機であることを認識する必要があります。
看護師は、個々の患者のケアに加え、家族や地域社会全体の健康増進にも深く関与する専門職です。未来の看護師には、目の前の患者の健康課題が、より広範な地球環境の変化と深く関連しているという視点が不可欠です。環境の持続可能性にも配慮した看護実践を通じて、個人とコミュニティの健康を守ることが求められます。
HGPIの提言:既存の教育への統合と再整理
日本医療政策機構(HGPI)は、2024年に実施した「日本の看護職者を対象とした気候変動と健康に関する調査 」の結果に基づく形で、今回の看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に対する提言を行いました。今回の提言においては、プラネタリーヘルスに関する新しい項目を単純に追加するのではなく、既存の項目に含まれる文言や考え方を修正することによって、未来にわたる環境や健康に関する視点を教育内容に組み込むことを重視しました。すでに、看護学教育の中にはプラネタリーヘルスと関連する様々な視点が含まれており、それを再整理するだけでも、十分にプラネタリーヘルスについて学びを深めることが可能です。
新カリキュラムでは、医療環境や社会環境と健康の関連性を理解する能力の記載が強化され、特に「地球環境・社会環境と人間の健康の相互関係、すなわちプラネタリーヘルスの観点について理解している(SO-01-02-03)」という到達目標が明記されました。「医学教育モデル・コア・カリキュラム」においては2019年に「気候変動と医療」の項目(コード 2019年版 ME-5-16→2022年版 SO-04-03)が追加されましたが、「プラネタリーヘルス」に関する記載は、今回の看護学モデル・コア・カリキュラムが初めての事例となります。
また、今回のモデル・コア・カリキュラム改訂に際して、関連法規には地球温暖化対策推進法など、環境に関する法律も追加されました。看護職が社会や環境に関わる法令や制度への理解を深めることは、その役割の拡大に伴い一層重要となっています。
プラネタリーヘルスの視点は、看護師の「地球の健康と人の健康は不可分である」という価値観の育成、環境変化が健康に与える影響に関する専門知識の習得、そして環境に配慮したケアや、環境由来の健康課題への対応といったスキルの獲得に繋がるものです。例えば、感染予防、環境整備、大規模災害への対応、地域社会における健康支援、健康教育、生活環境の整備といった既存の教育内容に、プラネタリーヘルスの視点を織り交ぜることで、学生は地球環境と健康の繋がりをより深く理解し、変化する社会に対応できる包括的な看護実践能力を培うことが期待できます。また、症候別看護、基本的看護技術、フィジカルイグザミネーション、臨床判断といった多岐にわたる教育内容において、その基盤となる知識や判断能力を養う過程で、環境要因が健康に与える影響を常に意識することが重要です。
未来への展望:プラネタリーヘルスが導く看護の進化
看護学教育モデル・コア・カリキュラムにプラネタリーヘルスの視点が統合されることは、変化する社会のニーズに応え、地球規模の健康課題に対応できる看護人材を育成する上で、重要な意義を持ちます。今後、実際の看護学教育の現場において、この視点がどのように具体化され、実践に繋がる教育が展開されていくか、その進捗が注視されるべきです。
今後の課題と展望
新カリキュラムへのプラネタリーヘルス視点の明記は大きな前進ですが、教育現場での実効化には課題も残ります。各看護教育機関では教員への研修や教材の整備、具体的な授業科目の工夫が求められます。医学教育においては、日本医学教育学会を中心に国内の大学関係者が協働してオンライン教材の開発を進めるなどの取組も行われており、相互連携をおこないながら看護学教育においても準備を進めることが期待されます。
国際看護師協会は2018年に「看護師は気候変動に適応・緩和しつつ回復力のある保健医療システムを構築する行動をリードすべき」と提言し、2024年にはCOP29のヘルスデーに合わせて、より重要度が高まっていると提言を更新しています。HGPIによるすでに臨床現場で働いている看護職者に対する調査でも、約72%の看護職者が「気候変動は看護職にとって重要課題」と回答し、80%が「気候変動と健康について学ぶ必要がある」と答えており、その必要性は看護現場で広く認識されています。しかしながら、実際に学ぶ機会があったと回答とした看護師は1割程度であり、看護職の生涯学習として継続的に育む仕組み作りも必要です。
現在、厚生労働省においては、「2040年を見据えた保健師活動のあり方検討会」が実施され、訪問看護推進連携会議(日本看護協会・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会)は、「2040年に向けた訪問看護ビジョン」策定の議論が進められています。このような現任教育に関連する活動のビジョン等にプラネタリーヘルスの視点が反映され、すでに現場で活動している看護師・保健師への教育の機会や実践の機会が生まれることを期待します。気候変動の影響が世界的に拡大する中で、看護職がその最前線で果たす役割はより重要性を増しています。国際的にも国内的にも、適応と緩和の双方に貢献できる看護人材の育成が急務とされています。
【参考文献】
- 文部科学省. 看護学教育モデル・コア・カリキュラム(令和6年度改訂版). https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/mext_00021.html (閲覧日:2025年5月20日)
- 文部科学省. 医学教育モデル・コア・カリキュラム(令和4年度改訂版). https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/mext_00005.html (閲覧日:2025年5月20日)
- 日本医療政策機構. 日本の看護職者を対象とした気候変動と健康に関する調査(最終報告). https://hgpi.org/research/ph-20241114.html (閲覧日:2025年5月20日)
- 日本医療政策機構. 日本の看護職者を対象とした気候変動と健康に関する調査(速報版)(2024年9月11日). https://hgpi.org/research/ph-20240911.html (閲覧日:2025年5月20日)
- 日本医療政策機構. 「看護学教育モデル・コア・カリキュラム(令和6年度改訂版)(案)に関する意見募集」(2024年9月11日).https://hgpi.org/research/ph-20240911-a.html (閲覧日:2025年5月20日)
- 日本医療政策機構. ポストSDGsの未来を見据えた看護学教育モデル・コア・カリキュラム:気候変動と健康を含むプラネタリーヘルスの視点の必要性(2024年5月30日). https://hgpi.org/research/ph-20240530.html (閲覧日:2025年5月20日)
- 国際看護師協会(ICN). International Council of Nurses calls for increased nursing leadership to combat effects of climate change on health. https://www.icn.ch/news/international-council-nurses-calls-increased-nursing-leadership-combat-effects-climate-change (閲覧日:2025年5月20日)
- 国際看護師協会(ICN). ICN marks COP29 Health Day with strengthened Position Statement calling for urgent climate action. https://www.icn.ch/news/icn-marks-cop29-health-day-strengthened-position-statement-calling-urgent-climate-action (閲覧日:2025年5月20日)
- 環境省. 地球温暖化対策の推進に関する法律. https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000117 (閲覧日:2025年5月20日)
- 厚生労働省. 2040年を見据えた保健師活動のあり方検討会報告書. https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou_128580_00015.html (閲覧日:2025年5月20日)
- プラネタリーヘルス・アライアンス・ジャパン・ハブ(PHA Japan Hub) 概要. https://phajapan.jp/concept/ (閲覧日:2025年5月20日)
- 日本医学教育学会モデル・コア・カリキュラム運用委員会. モデル・コア・カリキュラム紹介動画. https://core-curriculum.jp/movies (閲覧日:2025年5月20日)
- 日本看護協会・日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会. 訪問看護推進連携会議「2040年に向けた訪問看護のビジョン」(案)に対するご意見募集 https://www.nurse.or.jp/news/z_iken_202504.html(※現在募集・ページの公表は終了しています)(閲覧日:2025年5月1日)
【執筆者のご紹介】
鈴木 秀(日本医療政策機構 シニアアソシエイト)
菅原 丈二(日本医療政策機構 副事務局長)
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)
- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)