【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
日付:2018年3月22日
タグ: 女性の健康
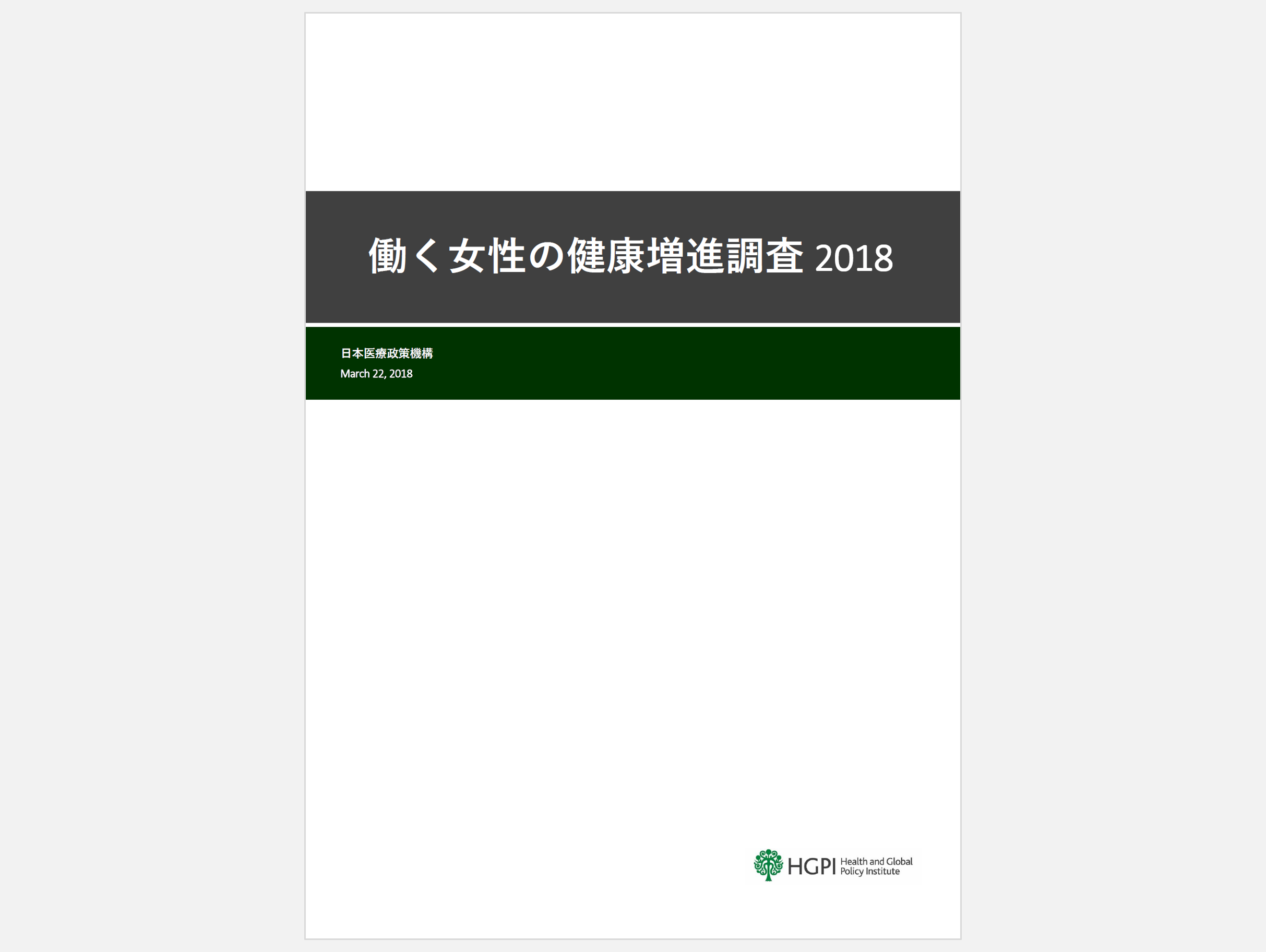
女性の健康週間がスタートした3月1日に日本医療政策機構が発表した、「働く女性の健康増進に関する調査2018(速報版)」の最終報告書を公表いたしました。
女性が、妊娠や出産・子育て、就労の継続等、ライフプランを主体的に選択するだけでなく、社会への貢献を実現するためにも、健康は重要な要素のひとつです。しかし、女性自身の健康知識や、健康増進に対する社会の支援は、まだ十分とは言えません。
そこで日本医療政策機構では、就労女性2,000名を対象に、女性に関するヘルスリテラシーと女性の健康行動や労働生産性、必要な医療へのアクセスとの関連性を調査しました。
本調査では、女性に関するヘルスリテラシーを「女性が健康を促進し維持するため、必要な情報にアクセスし、理解し、活用していくための能力」としています。つまり、体のしくみや女性特有の疾病知識だけでは充分ではなく、情報の取捨選択、医療関係者等への相談、女性特有の症状への対処といった行動が伴う必要があります。
調査結果より、女性に関するヘルスリテラシーの高さが、仕事や妊娠、健康行動と関連のあることが明らかになったことから、ヘルスリテラシー向上に繋がる対策促進の重要性が示唆されました。
■調査結果のポイント
- 女性に関するヘルスリテラシーの高さが、仕事のパフォーマンスの高さに関連
- 女性に関するヘルスリテラシーの高さが、望んだ時期に妊娠することや不妊治療の機会を失することがなかったことに関連
- 女性に関するヘルスリテラシーの高い人は、女性特有の症状があった時に対処できる割合が高い
- 女性に多い病気のしくみや予防・検診・治療方法、医療機関へ行くべき症状を学ぶニーズが高い
- 企業の健康診断が、定期的な婦人科・産婦人科受診に貢献
■調査結果を受けての見解:今後推進すべき対策
女性特有の健康リスクへの対応を促進するために必要な知識の提供
- 国:女性自身が特に必要とする項目の授業を促進すべくリーダーシップをとるべき
- 教育機関:生涯を通じて女性に必要な健康管理の項目も重点的に扱うべき
- 企業:従業員のライフステージごとに必要な知識を提供する研修等を実施すべき
ヘルスリテラシーを意識した企業の健康対策の促進
- 国:健康経営銘柄選定において女性のヘルスリテラシー向上の取り組みを重視すべき
- 国・研究機関:企業が実施した女性の健康対策の評価手法を開発すべき
- 企業:女性のヘルスリテラシー向上に繋がる相談体制を整備すべき
婦人科・産婦人科へのアクセス向上
- 企業:企業の定期健康診断に婦人科特有の項目を含めるべき
- 医療提供者:患者に対し定期的な受診の必要性を伝えるべき
- 医療機関:患者のニーズを踏まえた医療提供体制を整備すべき
望んだ人が妊娠や不妊治療に取り組める環境づくり
- 企業:短時間でも利用ができる柔軟な有給休暇制度を整備すべき
- 企業:整備した制度を利用できる職場の雰囲気づくりに努めるべき
■調査概要
【調査主体】特定非営利活動法人 日本医療政策機構
【調査手法】インターネット調査
【調査エリア】全国
【調査時期】2018年2月
【調査対象者】全国18歳~49歳のフルタイムの正規/契約/派遣社員・職員女性2,000名
■調査体制
【調査チーム】 *敬称略、順不同
- 大須賀 穣(東京大学 大学院医学系研究科 産婦人科学講座 教授)
- 森崎 菜穂(国立成育医療研究センター社会医学研究部 ライフコース疫学研究室 室長)
- 窪田 和巳(横浜市立大学医学部 臨床統計学 助教)
- 鈴木 秀(東京大学大学院 医学系研究科 健康科学看護学専攻地域看護学分野 修士課程)
- 今村 優子(日本医療政策機構 シニアアソシエイト)
- 小山田 万里子(日本医療政策機構 副事務局長)
- 吉田 友希子(日本医療政策機構 プログラムスペシャリスト)
【アドバイザー】
- 武谷 雄二先生(アルテミス ウイメンズ ホスピタル 理事長、日本医療研究開発機構女性の健康の包括的支援実用化研究事業プログラムスーパーバイザー)
- 吉田 穂波先生(神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 准教授)
【協賛】
- ドコモ・ヘルスケア株式会社
- バイエル薬品株式会社
実施にあたって同社との意見交換を行いましたが、それらの意見の反映については、調査チームが主体的に判断しました。
■尺度を使用される際のお願い
本調査報告書9ページの図4、図5で使用しております尺度は当機構が独自に作成したものとなります。尺度を使用される際には、論文「日本の女性労働者におけるヘルスリテラシーと労働生産性の関連(Association of Women’s Health Literacy and Work Productivity among Japanese Workers: A Web-based, Nationwide Survey)」から引用した旨を公表の際にご記載ください。なお、使用方法等に関するお問い合わせは下記にお願いいたします。
■本調査に関するお問い合わせ先
特定非営利活動法人 日本医療政策機構(担当:今村)
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)








