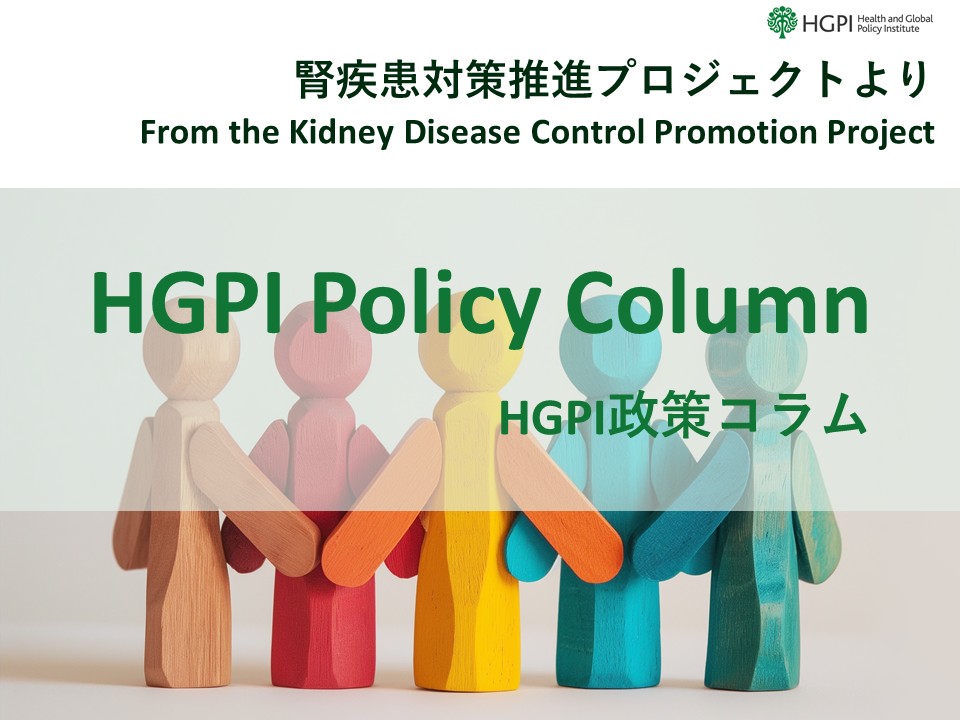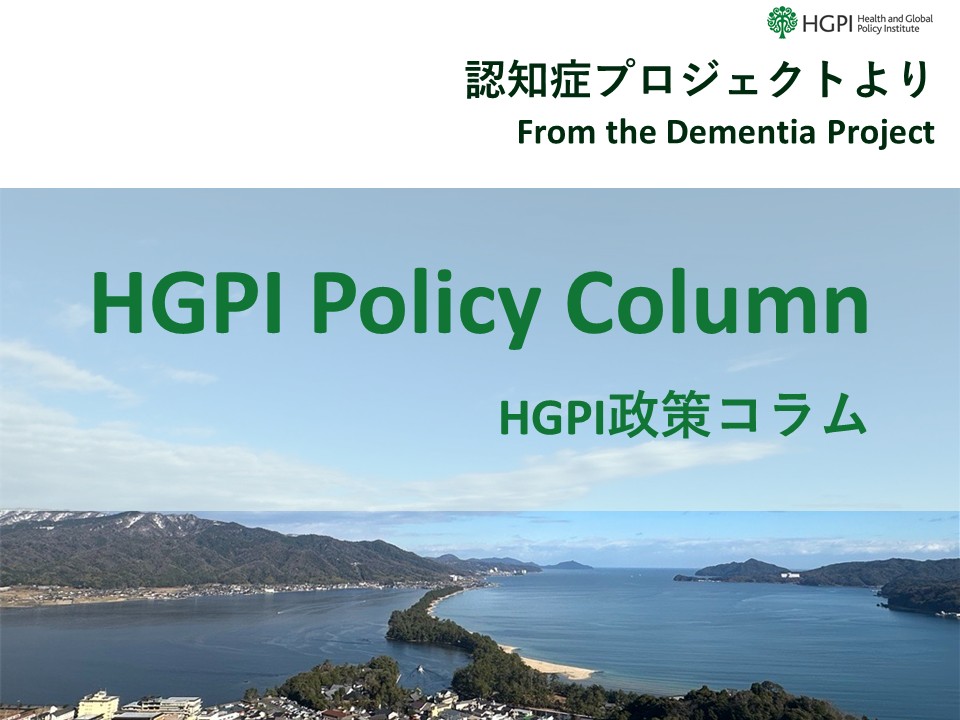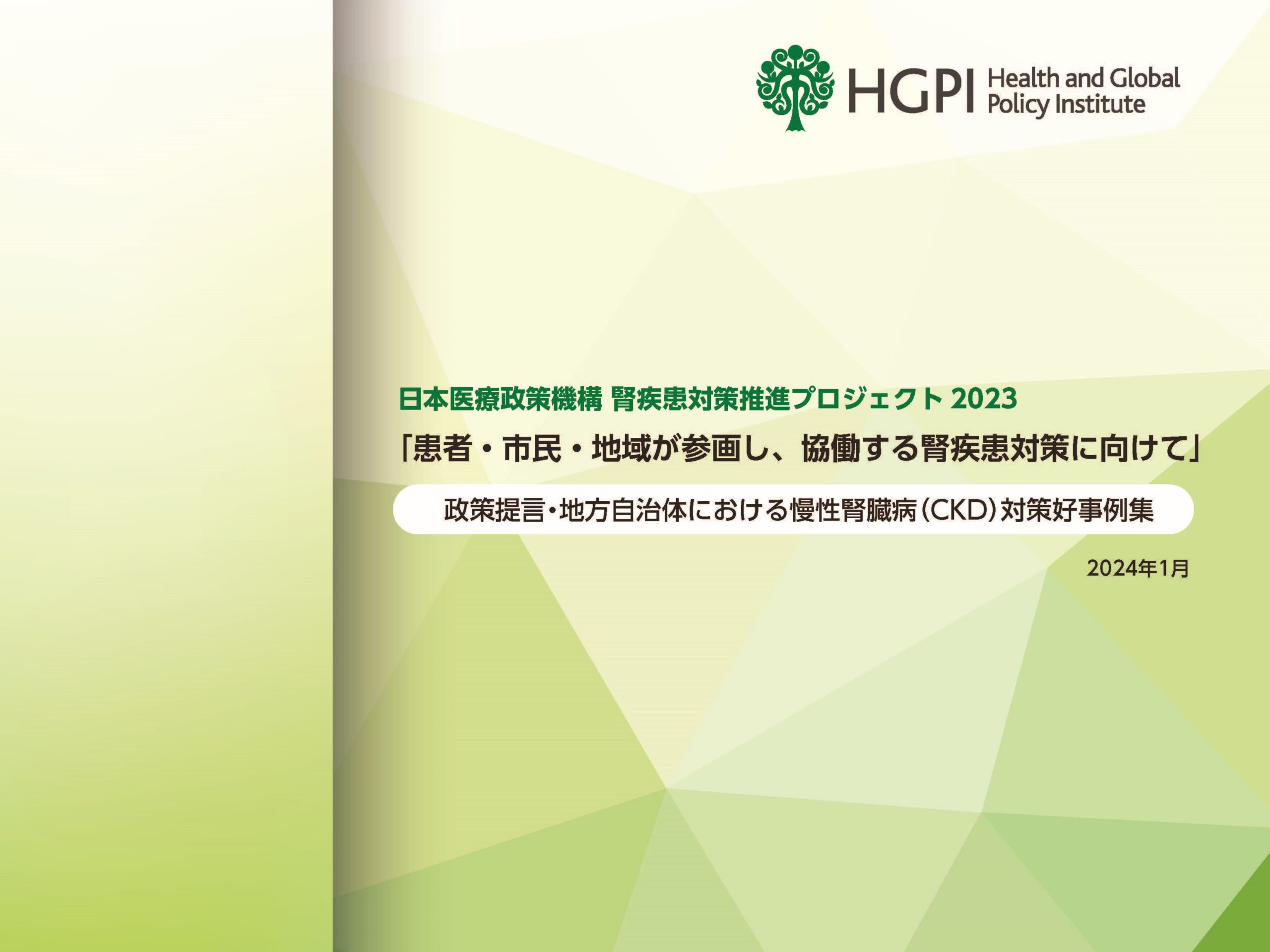【HGPI政策コラム】(No.55)―腎疾患対策推進プロジェクトより―「慢性腎臓病(CKD)の治療の継続において患者視点で求められていること(食事療法編)」
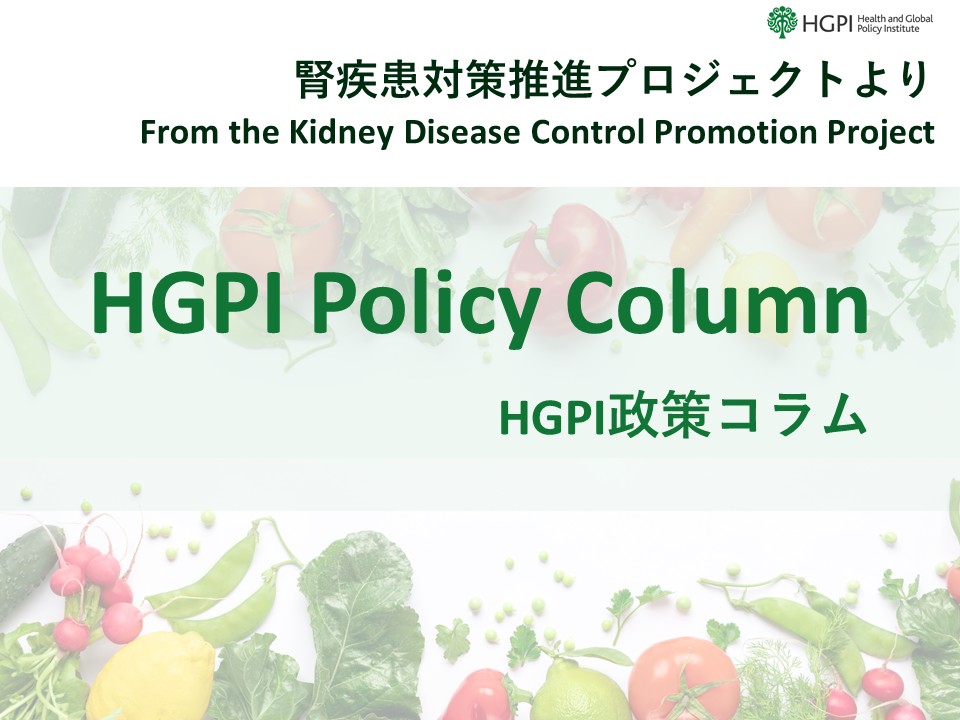
<POINTS>
- CKDの食事療法においては、適正なエネルギー摂取と食塩制限を基本とし、個々の病態に応じてたんぱく質・カリウム制限などが加わるが、これらは治療の一環であると同時に患者の生活の質に影響を与える重要な要素である。
- 2020年以降の診療報酬改定により外来における栄養食事指導の制度が整備され、アクセシビリティが向上している。
- しかし、患者視点では外来で栄養食事指導にたどり着くにはハードルがあり、今後はよりアクセスしやすく患者の視点に寄り添った支援体制の構築や対応が必要である。
はじめに
慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)の治療では、薬物療法に加えて日々の生活に影響する食事療法を必要とする場合があります。これまで日本医療政策機構 腎疾患対策推進プロジェクトでは複数のCKDと共に生きる方へヒアリングを行ってきた中で、食事療法は医師に食事療法の必要性を説明されたその日から始まり、自身で取り組む必要があることから、しばしば大きな困りごとの一つとしてあげられました。今回のコラムでは、栄養食事指導の制度や患者視点で求められることを中心に紹介します。
CKDにおける食事療法について
CKDの治療では、CKDの重症度分類、年齢や検査結果、身体状態等から医師が必要と判断した場合、食事療法が必要となることがあります。ここでは透析療法に移行する前のCKDステージ1から5までの食事療法について記述します。食事療法の内容としては、適正なエネルギーを摂取すること(25-35 kcal /kgBW /日)、食塩を控えること(3g /日以上6g /日未満)が基本となります。ただし個人の症状等によっては、これらに加えてたんぱく質制限、カリウム制限などが必要となることがあります。このように食事療法の内容は、個人差があることに注意が必要です。
また、食事療法を開始する以前の食事にたんぱく質や食塩の過剰摂取がみられた場合は、大きな食事の見直しが必要になる可能性があるので、ストレスに感じる人もいます。CKDの食事療法は治療の一環であると同時に、食べることが楽しみや生きがいにつながる人もいることから、食事療法がその人の生活の一部であるという認識が必要と考えられます。
CKDの食事療法について詳しく知りたい場合は、「慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版」(日本腎臓学会編、東京医学社)や「日本人の食事摂取基準(2025年版)」(厚生労働省)が参考になるでしょう。
医療機関における栄養食事指導(外来)とは
保険医療機関における栄養食事指導では、管理栄養士が医師の指示に基づいて具体的な献立等によって指導を行います。当該保険医療機関の管理栄養士が栄養食事指導を実施する場合は外来食事栄養指導料1(以下、指導料1)、他の医療機関等に所属する管理栄養士が実施する場合は外来栄養食事指導料2(以下、指導料2)を算定します。指導料1では初回の指導において対面では260点、情報通信機器等を用いた場合では235点、2回目以降において対面では200点、情報通信機器等を用いた場合では180点、指導料2では初回の指導において対面では250点、情報通信機器等を用いた場合では225点、2回目以降において対面では190点、情報通信機器等を用いた場合では170点となっています。
また、初回の栄養食事指導を行った月は月2回、その他の月は月1回算定が可能です。外来の栄養食事指導は医師の診察がない日でも算定が可能となっています。
2020年の診療報酬の改定で、指導料2が追加されました。指導料2は管理栄養士が栄養ケアステーションや他の保険医療機関に所属していることが条件ではあるものの、オンラインでの栄養食事指導のサービスの活用などによって、診療所においても栄養食事指導が実施しやすくなっています。また、同年に2回目以降において情報通信機器を用いた栄養食事指導料を算定することが可能に、2024年の診療報酬の改定では初回から情報通信機器を用いた栄養食事指導が可能となり、さらに外来で栄養食事指導を実施しやすい体制となっています。
CKDの栄養食事指導(外来)について
CKDに関連した栄養食事指導料が外来においても算定可能な疾患は多数あります。外来の栄養食事指導料は基本的には入院栄養食事指導料を算定している範囲となり、例えば、医師により病名を診断されているCKD、ネフローゼ症候群などが含まれ、たんぱく質のコントロール、食塩の制限等が留意事項となります。外来の場合には、高血圧症に対する減塩の指導も対象となります。
CKDの患者視点で食事療法に求められること
CKDと共に生きる方へのヒアリングを通じて、「CKDの食事療法が難しくて医師の説明だけでは分からない」、「食事について聞きたいと思っているが聞く先が分からない」、「自分で栄養指導を受けられる場所を見つけられない」などの声が聞かれました。管理栄養士が常駐している診療所は多くなく、患者視点で考えると外来の栄養食事指導にたどり着くまでにハードルがあることに気づきます。今後は、CKDの治療を行っている診療所であればどこでも栄養食事指導にアクセス可能な体制が整備されることが期待されます。
また、栄養食事指導が必要なく自身の管理で十分と医師が判断した場合でも、患者や家族は食事について困りごとを人知れず抱えている可能性があることについても留意が必要と言えるでしょう。CKDと共に生きる人にとって食事療法は治療だけではなく、生活の一部です。医療者は食事について「ちょっとした困りごと」を相談したいと思っている可能性を念頭に置いて対応することが求められます。
【参考文献】
- 編集 日本腎臓学会、エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023、東京医学社、2023年
- 日本腎臓学会 編、慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版、東京医学社、2014年
- 厚生労働省、日本人の食事摂取基準(2025年版)策定検討会報告書 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html(閲覧日:2025年3月4日)
- 厚生労働省、別表第一医科診療報酬点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf(閲覧日:2025年3月4日)
【執筆者のご紹介】
大河 明咲子(日本医療政策機構 アソシエイト)
吉村 英里(日本医療政策機構 シニアマネージャー)
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)