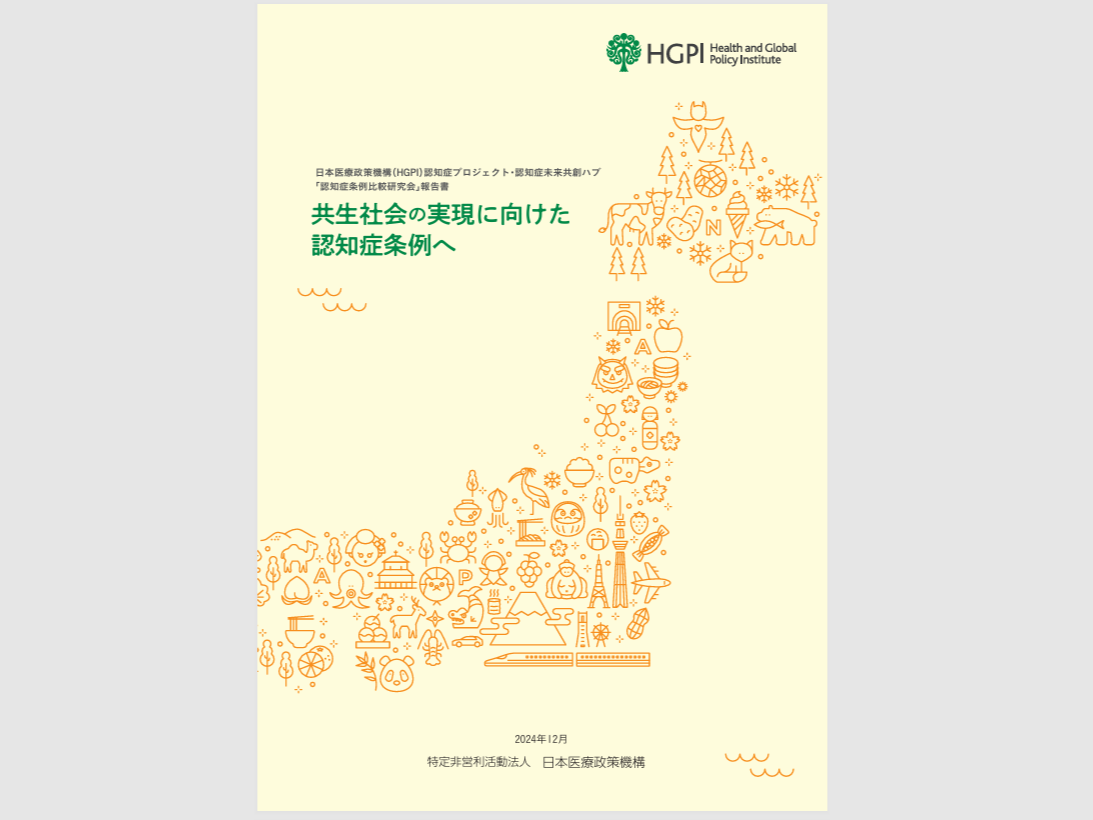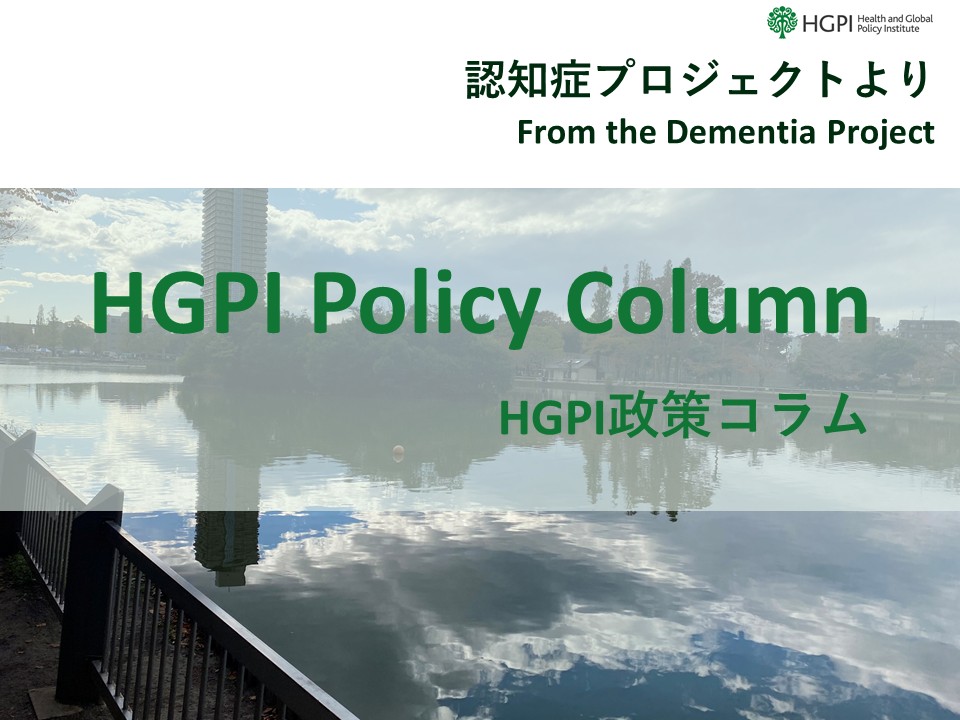【開催報告】認知症研究における当事者参画の推進に向けて「車座対話」~研究について話そう~(2025年3月17日)
日付:2025年3月27日
タグ: 認知症

日本医療政策機構では、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下、認知症基本法)にて明記されている、認知症の人と家族等の研究への参画促進に向けた取り組みの一つとして、認知症の本人や家族等と研究者が対話する場として「車座対話~研究について話そう~」を開催しました。
認知症プロジェクトでは、近年急速に関心が高まっている研究への「患者・市民参画(PPI: Patient and Public Involvement)」について、被験者として研究に参加をする「参加(Participation)」、研究の一部へ関与する「エンゲージメント(Engagement)」、患者・市民が研究チームの一人として研究者とリーダーシップを共有しながら積極的に関与する「参画(Involvement)」の三段階に大きく分類できると考えています。研究者は、「研究は当事者(本人、家族等)や市民その結果を享受する人達のためにあるものである」ということを理解し、研究の種類や内容に応じて適切に患者・市民参画を推進することが求められます。

現状日本の認知症研究においては、「参加(Participation)」も決して円滑とは言えず、特に医学研究などでは研究者や大学・研究機関が、それぞれ地道に被験者をリクルートするなど研究遂行の観点からも課題が多い状況です。認知症基本法が掲げる共生社会の実現に向けては、各研究分野において特に「参画(Involvement)」への底上げが期待されています。認知症の医学的な研究においても当事者参画の推進によって、これまでになかった新しい気づき・視点・アプローチが生まれ、それらは市民社会のみならずアカデミアにも新たな価値をもたらすことが期待されています。
車座対話を開催するにあたり、アルツハイマー病領域の研究者である新美芳樹氏(東京大学医学部附属病院 特任准教授)および、当事者団体である「おれんじドア三鷹」の皆様にご協力をいただきました。
当日は、新美氏より、「研究とはなにか」「医学研究とはどのようなものか」をご自身の経験や研究をふまえて、当事者が分かりやすい簡単な言葉を用いながら概説いただきました。ご講演後、参加者からは日常生活での疑問や研究に対する質問などが挙げられ、活発な対話が繰り広げられました。
 |
 |
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)
- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)