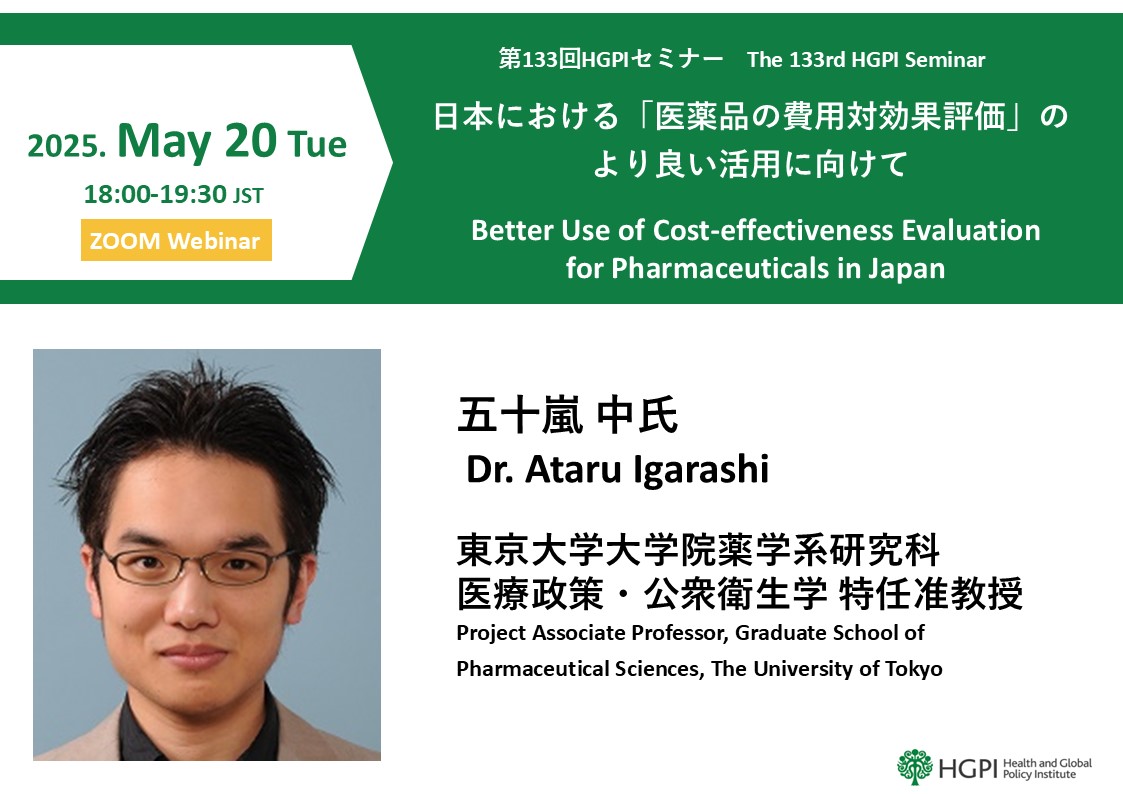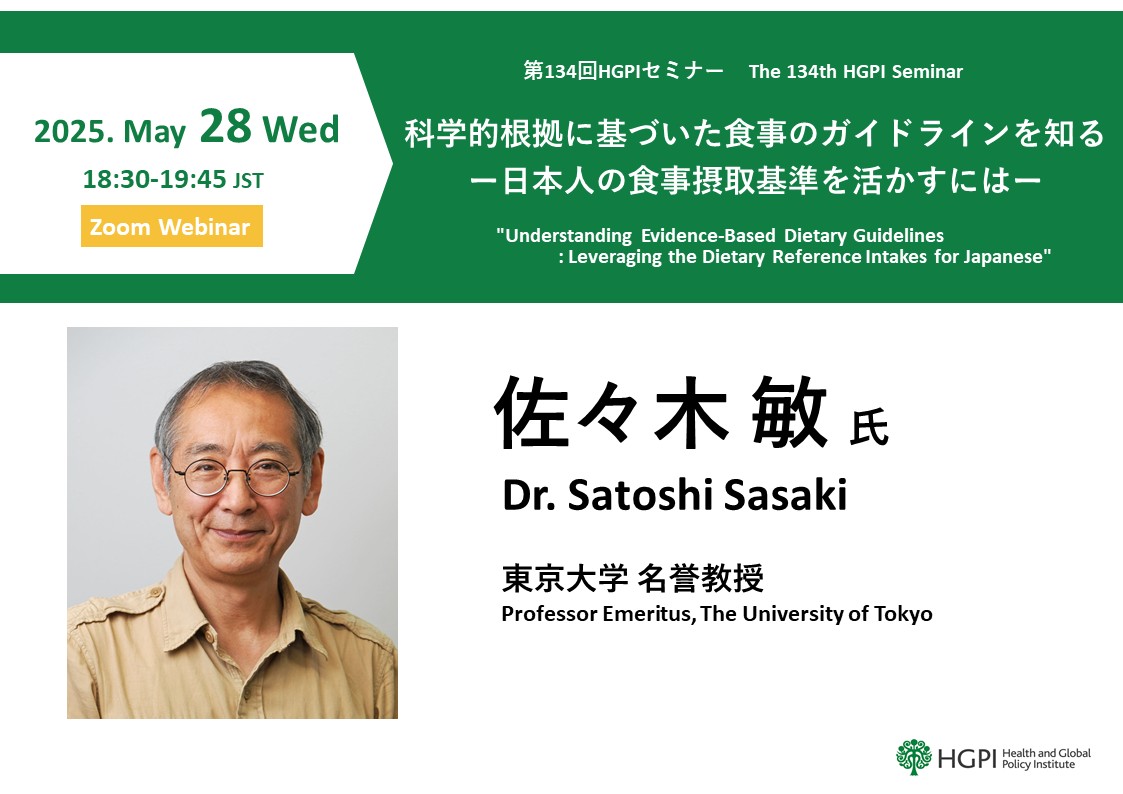【開催報告】第127回HGPIセミナー「政策を通じて人々の健康を守り、保健医療の仕組みを築く上での課題と展望」(2024年7月18日)
日付:2025年5月14日
タグ: HGPIセミナー, Innovation and Sustainability, 医療DX, 医療システムの未来

今回のHGPIセミナーでは、矢野好輝氏(厚生労働省 医政局総務課 保健医療技術調整官)をお招きし、かかりつけ医機能の制度整備の経緯やオンライン診療による医療アクセス向上のための諸政策、今後の課題について最新の動向を踏まえながらお話をいただきました。
<POINTS>
- かかりつけ医機能は2013年の社会保障制度改革国民会議で大病院への患者集中の緩和のため「穏やかなゲートキーパー機能」の導入の必要性を背景として提唱されたもの
- 制度整備の骨格は医師のキャリアパス整備、かかりつけ医機能報告制度の創設、医療機能情報提供制度の刷新から成る
- 高齢者の複合ニーズに対応した「治し、支える医療」実現のため、地域での生活に着目した医療制度が必要である
- オンライン診療は医療アクセス拡充とかかりつけ医機能との相乗効果が期待される一方、エビデンス構築と適正利用促進が課題となっている
■かかりつけ医機能は、大病院への患者集中を緩和する「穏やかなゲートキーパー機能」として社会保障制度改革の提案過程で提唱され、社会保障費の抑制と高齢者の複合ニーズに対応した質重視の医療体制構築を目指した制度整備が進められている
かかりつけ医機能は、大病院への患者集中の課題に対し、限りある医療資源を効率的に活用する必要性から、患者が最初にかかりつけ医を受診し、必要に応じてかかりつけ医が大病院に紹介するという「穏やかなゲートキーパー機能」を果たす目的で社会保障制度改革の提案過程で提唱された。外来医療の医療提供体制改革について言及した2013年の社会保障制度改革国民会議の報告書では、大病院で行われている外来医療の専門分化を進め、診療所でなるべく外来医療を受けられるようにするため、かかりつけ医機能の強化が提案され、2020年の全世代型社会保障改革の中でも、患者の定額負担の範囲の拡大が実施され、かかりつけ医の普及が更に図られた。
この様な対策により、直近の約30年で、紹介無しで受診した患者の割合は全体的に減少傾向であることが患者調査からも明らかになっており、かかりつけ医機能の普及に一定の成果が出ていると言える。一方で、政府全体の課題として、社会保障費が経済成長率を超えて膨張し、国家財政を圧迫している現状を鑑みると、これらの改革では不十分であるとの指摘もある。そのため、かかりつけ医機能の明確化や、かかりつけ医機能の発揮のための制度整備が更に必要との提案がなされている。2022年の財政制度等審議会では、従来の国民への啓発、好事例の横展開などの政策では外来医療の制度改革は成し得ず、これまでの「いつでも好きな所へ」という量重視のフリーアクセスから、「必要な時に必要な医療に行ける」という質重視のフリーアクセスへの転換を強化する必要があるという意見が出された。患者の定額負担を外来診療にも拡大し、諸外国のように、かかりつけ医の認定制度、患者によるかかりつけ医事前登録制を設け、かかりつけとして登録した医療機関以外を受診する場合は定額負担を求める仕組みを導入すべきという提案もなされている。
かかりつけ医機能の政策決定には複数の課題が存在した。例えば、かかりつけ医の事前登録性の導入による混乱、医療者側・患者側共に「かかりつけ医」に対する認識が一様でない中での方針決定をすることの困難さ、医療費削減効果についてはエビデンス不足などが挙げられた。そのため、政府として制度整備の方向性について2022年12月の全世代型社会保障構築会議のとりまとめでも再度議論がなされた。そこで、高齢者医療への対応の必要性という制度整備の趣旨の明確化と、医療費削減のためではなく、医療サービスの質の向上につながるためのものであるという目的の整理がなされている。
かかりつけ医機能が発揮される制度整備の骨格については、医師のキャリアパスの整備に加え、かかりつけ医機能報告制度の創設と医療機能情報提供制度を刷新することが大きな柱となっている。身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行うことなどを、地域で必要なかかりつけ医機能として定め、医療提供者側の体制改革のために報告制度を作り、国民への情報提供の強化を行う予定である。この背景には85歳以上の要介護高齢者が増加していることが存在する。複数の慢性疾患や医療介護の複合ニーズを持っている高齢者の増加を念頭に置き、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現し、いかに生活の質を維持するのか、地域での高齢者の生活に着目した医療制度が必要とされている。
かかりつけ医機能報告制度の検討において、かかりつけ医機能に関する知識(座学)と経験(実地)に必要な研修内容の検討、研修修了に関する公表や、医療情報プラットフォームでのかかりつけ医機能に関する検索機能追加により、研修を修了した医療者であることが分かりやすい形にするという提案などが打ち出されている。医師の育成に関しては、幅広い視野で患者や家族を見守り、地域を支える機能を持つ総合診療の専門医を増やし、かかりつけ医として対応していくという考え方もある一方、臓器別の専門医へかかりつけ医に関するリカレント教育を行うことでこれからの医療に対応できるようにしていくという考え方も検討されている。高齢者医療に対応した医療を提供できる医師を育てていくため、行政による支援や地域の医療機関での実地研修により、地域で必要となるかかりつけ医機能の確保が必要である。
■オンライン診療は情報通信技術の進化により医療アクセスを拡充し、かかりつけ医機能との相乗効果が期待される一方、今後の更なる普及に向けてはエビデンス構築と適正利用の促進が課題となっている
情報通信機器を活用したオンライン診療は、情報通信技術の発展や、地域の医療提供体制及び医療ニーズの変化に伴い、患者の医療アクセス改善のために近年需要が高まっている。オンライン診療は特に、医師が患者から必要な情報の提供を求めたり、患者が医師の治療方針へ合意したりする際に相互の信頼が必要となるため、かかりつけ医機能と親和性が高いと言える。新型コロナウイルス感染症流行と共にオンライン診療は大きく広がりをみせたが、発熱、上気道炎など、感染症に関する疾患がほとんどで、必ずしも幅広く普及が進んでいるとは言えない状況であることや、不適切な利用実態もあることが指摘されており、医療者・患者共に理解を進めていく必要がある。
オンライン診療拡大の経緯は、主に医師法20条(無診察治療等の禁止)の条文解釈と連動して進んできた。1997年に離島やへき地でのオンライン診療は医師法20条において問題にならないとされ、その後2015年には離島・へき地はあくまで例示であり、対面診療に代替し得る程度の患者情報が取得できる場合のオンライン診療は問題とならないとの解釈が示された。2018年にオンライン診療の適切な実施に関する指針が策定され、オンライン診療料の創設など診療報酬の評価にも繋がった。さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、再診のみで認められていたオンライン診療が初診にも認められるようになった。
オンライン診療実施により、患者にとって、医療の質向上や医療アクセス改善が見込まれ、医師側にとっても、オンライン診療への診療報酬上の再評価や、へき地等において医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設が認められるなど、医療法上の緩和も行われている。しかし、オンライン診療が標準医療として確立する前に規制緩和が先行して進んでしまっている状況もあり、特に美容医療などでトラブルが増加している。オンライン診療の適正な推進に向け、自治体主導の好事例集の作成や医療機関主導の研究・ガイドライン作成など、エビデンスの収集、構築が重要である。
【開催概要】
- 登壇者:
矢野 好輝 氏(厚生労働省医政局総務課 保健医療技術調整官) - 日時:2024年7月18日(木)18:30-19:45
- 形式:オンライン(ZOOMウェビナー)
- 言語:日本語
- 参加費:無料
- 定員:500名
■登壇者プロフィール
矢野 好輝氏(厚生労働省医政局総務課 保健医療技術調整官)
京都大学医学部医学科卒。厚生労働省に入省後、保険局医療課(診療報酬改定)、医政局研究開発振興課(臨床研究推進)、障害保健福祉部企画課(障害者福祉)等を歴任。環境省、宮崎県庁、米国保健福祉省への出向も経験。2022年7月より現職。現在、医療政策の技術案件の総合調整、かかりつけ医機能の推進、オンライン診療の推進、医療広告等を担当。東京医科歯科大学大学院博士課程修了。医師、医学博士(医療政策情報学)。
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)