【開催報告】HGPIセミナー特別編 認知症共生社会の構築に向けた普及啓発施策のあり方を考える(2021年4月20日)
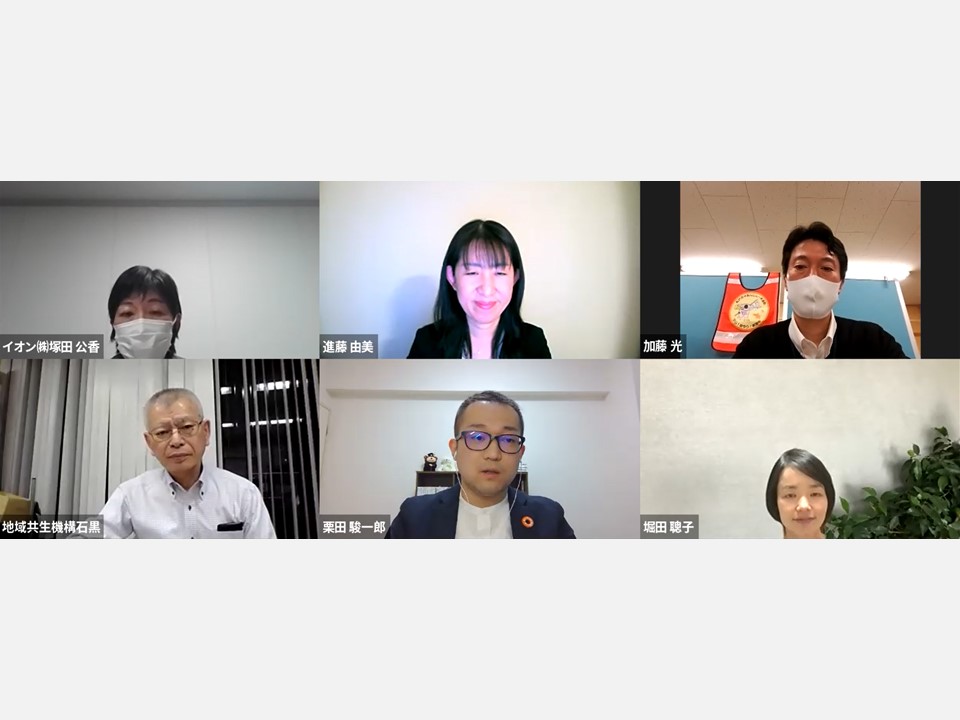
*****最終報告書を作成し、発表しました。(2021年6月21日)
詳しくは、当ページ下部のPDFファイルをご覧ください。
———-
日本医療政策機構(HGPI)では、非営利・独立の医療政策シンクタンクとして、認知症をグローバルレベルの医療政策課題と捉え、世界的な政策推進に向けて取り組みを重ねてまいりました。認知症政策の推進に向けたマルチステークホルダーの連携促進を基盤とし、「グローバルプラットフォームの構築」「当事者視点の重視」「政策課題の整理・発信」を柱として、多様なステークホルダーとの関係を深めながら、活動を行っています。
日本では厚生労働省が2004年に呼称を「痴呆症」から「認知症」へと変更してから約15年が経過しました。多くの関係者の尽力により、認知症への理解は格段に向上し、最近では認知症の本人が自らの経験や想いを発信することも当たり前の社会に変わりつつあります。今や、認知症は誰しもなり得るものであり、それに向け備えるための取り組みが必然であることが共通の理解となっています。こうした社会の変化に大きく貢献しているのが、全国各地で行われている「認知症サポーター養成講座」によって誕生した「認知症サポーター」の存在です。認知症サポーター養成講座は、2005年にスタートし、現在では1200万人を超えるサポーターが養成されています。講師役となる「キャラバン・メイト」は、一定の専門性や役割を持つ人々が養成研修を受けて登録されます。キャラバン・メイトは養成講座を実施するとともに、地域における認知症理解促進のリーダーとして自治体と連携しながら活躍しています。また近年では、企業・職域型の認知症サポーター養成も活発化しており、2019年に公表された国の認知症施策推進大綱でも、企業・職域型の認知症サポーターを400万人養成することが目標値として盛り込まれています。またこうした取り組みは世界的にも注目されており、例えば英国では2012年から「Dementia Friends」と名付けた英国版の認知症サポーターを養成する取り組みも始まっています。
誕生から15年が経過した認知症サポーターを筆頭に、これまでの認知症普及啓発の施策・取り組みは大きな成果を挙げてきました。これまでの理解促進に関する施策の貢献を評価するとともに、国際的な動向も踏まえ、今後さらに認知症共生社会に向けた歩みを進めるためにはどういった施策が求められるのか、認知症のご本人やアカデミア、地方自治体や産業界などマルチステークホルダーでの議論を進めるべく、HGPIセミナー特別編を開催いたしました。
開会挨拶・趣旨説明
乗竹 亮治(日本医療政策機構 理事/事務局長・CEO)
日本医療政策機構は、非営利かつ独立のシンクタンクとして、医療政策の提言を数多く実施している。認知症を重要な政策課題と位置付け、グローバルに市民・当事者主体の議論を重ね、「認知症未来共創ハブ」などの活動を推進。慶應義塾大学、issue+design、認知症フレンドシップクラブといった団体との活動を通じ、日本の好事例を世界へ発信している。
2005年からスタートした「認知症サポーター養成講座」は、世界的にも重要な取り組みとして注目され、英国では、2012年から「Dementia Friends」という認知症サポーターを養成する活動が始まった。日本の好事例が世界に共有されている一例である。
認知症サポーターキャラバンをはじめとする皆さんが、長年にわたり活動されてきた礎を基に、最近では国内外を問わず、当事者が安心して声を上げ、認知症に関する多様な課題を一緒に解決していくための議論が活発になっている。産官学民のマルチステークホルダーの一員として、よりよい社会をつくろうと努力される当事者の方々も増えてきた。本日は、これまでの実績を振り返りつつ、今後のグローバルな展開を含め、ディスカッションしていきたい。
認知症の普及啓発・本人発信支援施策の現状と展望
菱谷 文彦 氏(厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課 認知症総合戦略企画官)
「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授)の速報値によると、2025(令和7)年には、認知症の人は約700万人に上ることが推計されている。
こうしたなか、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を車の両輪とした施策を推進するための認知症施策推進大綱(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定)を取りまとめた。
具体的な施策の5つの柱として、①普及啓発・本人発信支援、②予防、③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援、④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援、⑤研究開発・産業促進・国際展開、を掲げている。
大綱では、認知症の人本人からの発信支援について、「認知症の人が生き生きと活動している姿は、認知症に関する社会の見方を変えるきっかけともなり、また、多くの認知症の人に希望を与えるものでもあると考えられる。認知症の人が、できないことを様々な工夫で補いつつ、できることを活かして希望や生きがいを持って暮らしている姿は、認知症の診断を受けた後の生活への安心感を与え、早期に診断を受けることを促す効果もある」と記述している。
さらに「認知症とともに生きる希望宣言」について、「認知症本人大使(希望宣言大使(仮称)」を創設すること等により、本人等による普及活動を支援する」ことが掲げられたことを踏まえ、年代、性別のほか地域性も考慮し、令和2年1月20日に5名の「希望大使」(丹野智文さん、藤田和子さん、柿下秋男さん、春原治子さん、渡邊康平さん)を任命した。
また、令和2年度以降、都道府県知事が委嘱・任命等を行う地域版の希望大使の設置を推進していくこととしている。地域版の希望大使は、全国版の希望大使と協働・連携しながら、認知症の普及啓発活動やキャラバン・メイトへの協力など地域に根ざした活動を行っていく。
令和2年度には、厚生労働省において全国7人の認知症の人が自らの希望を語り、地域の中でそれを実際に叶えながら生き生きと過ごしている姿を伝える動画を作成した(詳細はこちら)。
認知症の人やその家族が地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場である認知症カフェを活用した取り組みの推進については、令和元(2019)年度実績調査によると、47都道府県1,516市町村にて7,988カフェが運営されている。
しかし現在、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策のために、全国各地で認知症カフェの中止を余儀なくされている。そこで「認知症カフェにおける新型コロナウイルスの影響と緊急事態宣言等の状況下における運営のあり方に関する調査研究事業」を実施している(令和2年度老人保健健康増進等事業。実施団体は社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター)。感染対策をしながら、お手紙・戸別訪問・オンライン等を活用した代替的な方法で認知症カフェを効果的に継続するための手引書を運営者向けと参加者(本人・家族)向けの2種類作成し、自治体等へ発出しているので、適宜ご活用いただきたい。併せて、本人ミーティングやピアサポーターによる本人支援も推進することとしている。
認知症サポーターの養成は、2020(令和2)年度末の目標値1,200万人を上回り、2020(令和2)年12月末の実績値は1,301万人となっている。2025(令和7)年末には、企業・職域型の認知症サポーター養成数400万人(令和2年度実績は64万人)を目標に掲げている。
先進的に認知症サポーターの活動促進に取り組んでいる自治体も出てきており、認知症サポーターがチームを組んで行う見守り活動や認知症カフェへの参加、傾聴、外出支援など地域のニーズに応じた多様な活動を展開されている。先進事例として、三重県松阪市の高齢者安心見守り隊、神奈川県のオレンジパートナーなどの取組がある。
こうした取組を更に進めていく観点から、「チームオレンジ」の取組を進めていくこととしている。具体的には、市町村がコーディネーター(認知症地域支援推進員を活用しても可)を配置し、地域において把握した認知症の方の悩みや家族の身近な生活支援ニーズ等と認知症サポーター(基本となる認知症サポーター養成講座に加え、ステップアップ講座を受講した者)を中心とした支援者をつなぐ仕組みであり、認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業(地域支援事業交付金)により、全市町村で、本人・家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組み(チームオレンジなど)を整備するという目標の実現に向け、取り組んでいく。令和元年度実績調査(認知症施策・地域介護推進課実施状況調べ)によると、33都道府県87市町村にて153チームが設置され、3,118名のチーム員が活動している。
2019(平成31)年には、認知症に係る諸問題への対応が社会全体で求められているという共通認識の下、行政のみならず民間組織の経済団体、医療・福祉団体、自治体、学会等が連携し、取組みを推進することを目指すために日本認知症官民協議会を設立。その下に認知症イノベーションアライアンスワーキンググループ(経済産業省)、認知症バリアフリーワーキンググループ(厚生労働省)を設置している。令和2年度認知症バリアフリーワーキンググループでは、業態等に応じた認知症の人への接遇方法等に関する『認知症バリアフリー社会実現のための手引き』を作成し、ホームページ等で公開している。
認知症サポーターキャラバン15年の歩み
石黒 秀喜 氏(地域共生政策自治体連携機構 事務局長代理)
2004年12月に「痴呆」という用語を「認知症」と改めたことなどを契機に、厚生労働省は「認知症を知り地域をつくる10カ年」の構想に基づき、2005年から普及啓発のためのキャンペーンを開始した。2009年度(中間年)到達目標の1つに「認知症について学んだ住民等が100万人程度に達し、地域のサポーターになっている」とあったが、2009年度よりも前にサポーターの数は100万人を超えた。2014年度(最終年)到達目標は「認知症を理解し、支援する人(サポーター)が地域に数多く存在し、すべての町が認知症になっても安心して暮らせる地域になっている」であった。こうした取り組みに協力する形で、国と当法人とのコラボが始まった。
認知症サポーターキャラバンでは、厚生労働省の認知症サポーター等養成事業実施要綱に基づき、キャラバン・メイト(認知症サポーターを養成・育成する講師)養成研修事業、認知症サポーター(認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る「応援者」)養成事業を行っている。認知症の基礎知識や認知症の人に接するときの基本姿勢、家族の支援等を学ぶ90分程度の講座を受講した認知症サポーターの人数は2021年3月末現在1,318万人に上り、厚生労働省の目標1,200万人を1年前倒しで達成した。
認知症サポーター養成事業を通し、多くの人々が、認知症は高齢になるほど誰もがなり得る「脳の疾患」に起因する症状であることを理解し、認知症の本人の気持ちを汲むことなくプライドを傷つけることが認知症の行動・心理症状(BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)の引き金になるなど、「認知症を知る」ことによって、早期対応や重度化予防が可能となる。さらに、地域ぐるみで共通の理解の下に安心できる環境を整えることが「共生」と「予防」につながる。
全国的な展開が活発化した背景には、高齢者の増加に伴って認知症の家族を持つ人が増え、関心を持たざるを得なくなったことや、認知症サポーター養成講座をボランティア養成ではなく、自分ごととして認知症を学び、できる範囲で手助けをするという性格にしたことなどが挙げられる。
2011年6月14日付の産経新聞には、東日本大震災が発生した際、南三陸町では認知症の人々の避難や避難所での対応に混乱が少なかったという記事が掲載された。同町では数年前から「認知症サポーター養成講座」を積極的に行い、町長を含めて町の人口の1割が認知症サポーターとなって「認知症でも笑顔で暮らせる町づくり」を進めてきたことが、その背景にあると指摘。認知症の人への対応を理解している人が多ければ、認知症の人は穏やかに生活できることが示された。
また、認知症サポーターキャラバンの啓発活動の効果として、65歳以上高齢者1人に対し2.5人(全国平均は高齢者3.2人に対しサポーター1人)の認知症サポーターがいる福井県若狭町では、初診患者における認知症重症者の割合が8.1%(2位の敦賀市は14.5%)と、同県嶺南4市町のなかで最も低いことが明らかになっている(平成24年)。
認知症サポーターキャラバンは、米国、カナダ、ドイツ、スイス、タイといった国々でも、現地の日系人会などを通じて広がっており、2012年の世界保健機関(WHO: World Health Organization)報告書、国際アルツハイマー病協会(ADI: Alzheimer’s Disease International)2021年版報告書においても高く評価されている。英国では、2012年から日本を手本とした「Dementia Friends」という認知症サポーター制度が始まり、台湾、タイ、韓国でも類似の取り組みが展開されている。
さらに今後は、厚生労働省が推奨している「認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業」に位置付けられているチームオレンジに参画し、本人や家族の孤立化を防止するなど、当事者の社会性の維持を支援する具体的な活動を発展させていくことが期待されている。
認知症のご本人からのビデオメッセージ「当事者とともにつくる地域・社会 -forからwithへ-」
山田 真由美 氏(認知症当事者キャラバン・メイト/borderless -with dementia-メンバー)
山下 祐佳里 氏(borderless -with dementia-メンバー)
山下氏:山田さんは、48歳のときに症状が出始め、51歳で若年性アルツハイマーと診断されました。診断を受けたときは、どう思いましたか?
山田氏:何かおかしいなとは思っていましたが、自分が認知症になるなんて。なぜ、私だけこんな嫌な目にあうのだろうと泣いていました。
山下氏:家にこもっていたのですね。でも、こうして外に出て来るようになったきっかけは?
山田氏:あゆみの会(名古屋市若年性認知症 本人・家族交流会)に参加したとき、自分と同じような女性に会ったのです。その人と話していたら、自分と同じ経験をしていることが分かって、「自分だけじゃない。他の人もがんばっているんだ」って。そのときから、元気になりました。
山下氏:平成28年9月、山田さんは、名古屋市で初の当事者キャラバン・メイトとして登録されました。同年8月には、息子さんの結婚式に向けて、結婚式場のスタッフに認知症サポーター養成講座を開催されましたね。
山田氏:自分ができないことや、やってもらいたいことなどを伝えて、スタッフの皆さんに助けてもらい、結婚式に参加することができました。料理を一口大に食べやすくしてくれたり、席まで誘導してくれたり、とても優しくしていただきました。
山下氏:新郎の母として、結婚式のお祝いの席に安心して参加できたのですね。記念写真も、とてもきれいに写っています。
山田氏:はい。嬉しかったです。
山下氏:では、当事者が自分のしたいことを伝えるツールとして、認知症サポーター養成講座を活用することをどう思いますか?
山田氏:必要ですね。
山下氏:認知症サポーター養成講座をもっと広めていきたいと思いますか?
山田氏:はい。
山下氏:当事者のキャラバン・メイトも、増えたほうがいいと思いますか?
山田氏:そうですね。どんどん外に出てほしいですね。
山下氏:当事者の思いを実現するために、認知症サポーター講座が重要なツールだということがよく分かります。
山下氏:3年前には、スコットランドへ一緒に行きましたね。例えば、空港での手続にしても認知症の人への対応が自然で、認知症の理解が人々の生活に根差していると感じました。日本でも、そのように地域の人たちが変わってくるといいですね。
山田氏:そうですね。
山下氏:そのためには、認知症サポーター養成講座をもっと開催したほうがいいでしょうか?
山田氏:はい。本当にもっと、色々なところでやってもらえたらいいと思います。
山下氏:山田さんも多くの開催場所を訪れて、話をしたいと思いますか?
山田氏:はい。
山下氏:全国の認知症当事者さんたちも、発信の場として認知症サポーター養成講座を活用することは、いいことだと思いますか?
山田氏:そう思います。
山下氏:実際に、生活のなかで困っていることを変えてもらうために、認知症サポーター養成講座を使ってほしいですよね。
山田氏:使ってほしいです。認知症の人はたくさんいるから、外に出てほしい。やりたいこともいっぱいあるだろうし、行きたい所もいっぱいあるだろうし。それが叶えられるので、恥ずかしがらずに、皆でやっていければいいと思います。
山下氏:当事者を含むキャラバン・メイトで新しいことをどんどん考えて、認知症サポーターの皆さんが地域で活躍してほしいですね。当事者の方たちのために、認知症サポーター養成講座をツールとして積極的に活用していただきたいと思います。最後に、山田さんから皆さんにお伝えしたいことをどうぞ。
山田氏:はい。私たちが困っていたら、助けてください。怒らないでください。
山下氏:それから、自分でできることは、自分でやっていきたいんですよね。
山田氏:そうです。
山下氏:私たちはキャラバン・メイトとして、これからも多くの方々に認知症サポーター養成講座を実施していきたいと思います。本日は、ありがとうございました。
山田氏:ありがとうございました。
パネルディスカッション「これまでの15年、これからの15年」
パネリスト:
石黒 秀喜 氏(地域共生政策自治体連携機構 事務局長代理)
加藤 光 氏(松戸市役所 地域包括ケア推進課 課長補佐)
進藤 由美 氏(国立長寿医療研究センター 老年社会科学研究部 研究員)
塚田 公香 氏(イオン株式会社 環境・社会貢献部)
モデレーター:
栗田 駿一郎(日本医療政策機構 マネージャー)
話題提供1:松戸市の認知症施策について
加藤 光 氏(松戸市役所 地域包括ケア推進課 課長補佐)
松戸市は、都⼼から20㎞圏、千葉県の東葛地域(北⻄部)の⼀翼に位置する。2021年3月末の人口は50万人弱、65歳以上の高齢化率は25.8%、75歳以上人口は13.5%となっており、市内15カ所に地域包括支援センターを設置している。
2020年4⽉時点における認知症(認知症⾼齢者⽇常⽣活⾃⽴度Ⅱ以上)の⼈は1万3,211⼈で、2025年4⽉には1万6,336⼈、2040年4⽉には2万1,386⼈に増加することが推計されている。
松戸市の認知症施策の理念として、「認知症を予防できる街 まつど」「認知症になっても安心して暮らせる街 まつど」を掲げ、認知症の人の意思決定支援、自立支援、できる限り在宅、地域包括ケアの実現に向けた施策を展開している。
2021年2月末(声かけ隊は同年3月末)現在、松戸市の認知症サポーターは2万8,957人、そのうち登録をした「オレンジ声かけ隊」は3,786人の個人および227の団体、さらに積極的に実践活動する「オレンジ協力員」は958人となっており、普段の生活の中で手助けが必要な高齢者を見かけたときに「何かお困りですか?」「お手伝いしましょうか?」と声をかけ、高齢者を地域全体で温かく見守っていく「あんしん一声運動」を推進している。
オレンジ協力員は専門職と連携し、買物のお手伝い、カフェ(課外活動)のお手伝い、認知症サポーター養成講座のお手伝い、オレンジパトウォークなどを行っている。オレンジパトウォークは、オレンジ協⼒員(認知症⽀援に特化したボランティア)などと⾼齢者いきいき安⼼センター(地域包括⽀援センター)が連携し、地域を⾒守るパトロールである。平成29年から始まったが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を受け、多くのオレンジ協⼒員の活動も⾃粛に追い込まれてしまった。⼈と⼈との関わりが薄れてきているなかで、特に⾼齢者の社会的孤⽴が問題視されていることから、松⼾市ではこのオレンジパトウォークを市内全15地域に拡⼤し、周知啓発(相談窓口・情報・イベント)、戸別訪問、認知症の人も一緒に歩く活動などを実施している。
令和2年度の新たな取り組みとして、認知症の本人の社会参加・活躍支援を目的としたプラチナ・ファーム(農園)、普及啓発のためのロバ隊長(認知症サポーターキャラバンのマスコットキャラクター)アクセサリーの作製・配布、認知症の人向け癒しの音楽会(音楽鑑賞と本人ミーティング)を実施している。
話題提供2:イオンの認知症への取り組み
塚田 公香 氏(イオン株式会社 環境・社会貢献部)
イオンは、総合スーパーなどの小売業を中心にアジア14カ国で約2万1,900店舗を展開。従業員数は約58万人の企業グループである。「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」を基本理念とし、お買い物という接点を通じ、コミュニティの拠点として、高齢者や認知症のお客さまにも安心してご利用いただける「場」の提供を目指している。
当社は、2007年より「認知症サポーターキャラバン」に参画している。従業員が認知症に関する勉強会を受講することで、接客時に「認知症」と思われるお客さまに気配り・心配りのある適切な対応ができるようになること、「認知症」のお客さまへの対応に困ったときに地域と連携して対応することを目的とし、この取り組みを開始した。従業員が「認知症」について正しく理解し、職場・地域・家庭で役立てることを目指している。
認知症サポーター養成講座では、地域の講師による認知症についての講義や、現場で実際に起きている事例をDVDで視聴し、対応についてグループディスカッションするなどして接客に必要な知識を習得するとともに、地元の認知症カフェや地域包括支援センターと連携し、啓発活動を推進している。
昨年度は、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策のため、対面での講座は難しい状況であった。そこで、オンラインでの認知症サポーター養成講座に取り組んだ。外部講師による講座(新店・改装オープン時、自治体との協働、本社ビル・各会議体など)、社内講師(キャラバン・メイト899名)による講座を合わせると、これまでに8万607名(2021年3月末現在)の従業員が受講し、認知症サポーターとなっている。
また、店舗という場を活用し、自治体や製薬会社と協働で、全国各地のイオン店舗において地域住民向け認知症啓発セミナーも展開している。現在は、コロナ禍において従来のような対面での開催は難しい状況であるが、創意工夫によって、地域住民に向けた認知症の啓発活動を今度も継続していきたいと考えている。
イオンの認知症対応の目指す姿として、ステップ1に、認知症サポーターを全店舗へ配置し、正しい知識を持って適切な接客を行える体制づくりに取り組んでいく。ステップ2では、認知症のお客様に対し、各店舗が地域の様々なステークホルダーと連携して対応できる体制を構築し、認知症対応の社会資源として機能することを目指していく。そしてステップ3として、認知症のお客様・ご家族のご意見を生かした店舗づくり(商品・施設・サービス)に取り組んでいきたいと考えている。
話題提供3:認知症施策の流れとこれまでの普及啓発施策について
進藤 由美 氏(国立長寿医療研究センター 老年社会科学研究部 研究員)
国の認知症施策の流れとして、2005(平成17)年に「認知症を知る1年」キャンペーンが実施され、認知症サポーター養成講座がスタートした。その後の15年間で、認知症に関する様々な研修や取り組みが推進されてきた。
平成28年度老人保健健康増進等事業「認知症サポーターを国際的に展開するための調査研究事業」にて、大分オレンジカンパニー(認知症にやさしい企業・団体)の従業員を対象に実施した質問紙調査(回答数516通、回答率56.9%)の結果によると、認知症サポーター養成講座を受講することで、認知症に関する「察知力」が高まり、従業員が職場のみならず、個人として認知症について考えるようになることが明らかになった。
WHOアクションプラン(2017-2025)では、7つの柱の2番目に「認知症の理解促進と認知症フレンドリーを促進する」が挙げられている。このアクションプランを踏まえ、国際アルツハイマー病協会(ADI)は2020年6月25日、各国の政策評価に関するレポート「From Plan to Impact III – Maintaining dementia as a priority in unprecedented times-」を発表した。
日本の認知症政策に対する評価は「5A」と上位ではあるものの、最高位の「5B」を得るためには、財政措置や進捗の評価が求められている。単に目標数値を達成するのではなく、当事者の意見をしっかりと踏まえたうえで、当事者が暮らしやすい社会を共に目指していくことが重要である。
◆認知症啓発施策の変化「これまでの15年」
- 認知症への理解は進み、社会は変わってきた。施策・取り組みの評価が課題
- 感覚として、本人が認知症であることを隠さず、オープンにしやすくなっている。ただし明確なデータを示すには、調査が必要な状況である。
- 単年だけでなく数年おきの世論調査を実施できれば、経年の変化が明らかになると思う。
- 市役所として地域を見ていると、以前は、市役所主導で啓発活動を推進していたが、近年は、オレンジ協力員などの市民ボランティアが独自に工夫を凝らし、活動している状況である。行政だけでは限界があるため、地域の人々が活躍することで、普及啓発の効果が高まっている。
- この15年ほどで、市役所の職員でも福祉部門以外の部署にいると、認知症サポーターが身につける「オレンジリング」を知らず、話についていけないといった変化が起こっている。松戸市では、職員全員が認知症サポーターになる目標を掲げ、数年後に達成。最新の情報が行き渡るようになった。組織全員が知っているのは強みであり、その点も大きな変化だと感じている。
- 企業として、2007年から認知症サポーターの養成に取り組んできたが、当時は「なぜ、こんなことをやるの?」という意見が社内でも多かった。そこで、当社として取り組むべき意味合いについて、時間をかけて丁寧に説明した後、認知症サポーター養成講座を実施した。現在では、認知症が大きな社会課題として認識されており、「なぜ?」という意見は、年月の経過とともに減っている。一方で、受講した従業員から寄せられる「普段の接客を見直すきっかけになった」という声は、15年前も今も変わらない。その意味で、認知症サポーター養成講座は、認知症のお客様への対応だけでなく、一般のお客様の接客にも通じる内容として、今後も続けていきたい。
- 15年前のまったく知らなかった状況から、知識を得るようになり、次のステージがこれからの15年になると思う。大きな成果を上げた一方で、評価の在り方という課題も残っている。認知症に限らず、「社会課題は行政が解決するもの」と市民社会が認識しているのは、大きな課題といえる。「自分たちが課題を解決する主体である」と一人ひとりが自覚できるように変えていく必要がある。
◆認知症啓発施策の未来「これからの15年」
- 認知症の本人の発信と当事者の語りの蓄積・一般化の必要性
- 全ての人は加齢によって認知機能が低下することを認識したうえで、認知症状が生ずるメカニズムといった全体像を知り、「脳疾患に起因しているのだから、自分が腹を立てても仕方がない。認知症の人の顔を立てよう」といった基本的な認識を多くの人々に持ってもらうことが大切である。90分の認知症サポーター養成講座では、こうした基本的なことをしっかり学び、その上で支援する対象者像を明確にして、より実践的な内容を学ぶステップアップ研修などで個別に学習を継続していくべきと考えている。
- 認知症の本人による普及啓発には大きなインパクトがあるが、若年性認知症と生理的な老化も伴う高齢期の認知症では状況が多少異なるため、留意する必要がある。ステップアップ研修と組み合わせながら、幅を広げていってほしいと思う。
- 今後は、多様な当事者の語りを蓄積し一般化していくことが求められる。
- 認知症の本人の想い・経験を起点とした社会づくりを官民連携して進める必要性
- 近年、店舗での啓発イベントなど、認知症の本人に発信していただく場を提供しているが、自治体との連携が不可欠と考えている。今後も地域と連携しながら、様々な活動を推進していきたい。
- 認知症に限らず、あらゆる社会課題の解決のためには「官民連携」が重要である。
- 前述のADIによるレポートにおいて、日本が分類された「5A」は、「政策は承認されているが、社会に対して伝えきれていない」という評価である。そのため、次の15年では、従来のように取り組みの重要性を発信していくだけでなく、認知症の人の意見を聞くことが大切である。「伝える」「聞く」という双方向のコミュニケーションによって認知症政策を作り上げていくことが必要である。
- 「特別なもの」から「当たり前」にしていく必要性
- ⼦どもから大人まで、皆が認知症に対して十分な理解があり、⽇頃から⾝近に感じ、認知症の⼈が思いを発信できる場があり、活躍できる社会になることを目標に、今後も普及啓発の取り組みを進めていきたい。認知症の⼈がいることが⾃然になり、「特別なもの」でも「こわいもの」でもなく「なっても安⼼、⼤丈夫」と誰もが思い、究極的には、認知症という⾔葉すら意識しない世の中になっていることが、普及啓発の目指すところだと考えている。
- やはり、日常の中に溶け込んでいくことが重要だと思う。英国を訪れた際、スーパーマーケットには、認知症の人がゆっくり会計できるスロー・レーンが設置されていた。このように、認知症の人を含めた共生社会が当たり前になっていく必要がある。しかし日本では、毎年9月の認知症月間のみ、イベントが催されるような状況に留まっている。
- 企業の役割として、認知症に限らずさまざまな不自由を抱えているお客様への対応を考えることは重要である。スロー・レーンの設置についてもその1つであり、今後検討が必要と認識している。
閉会の辞
堀田 聰子 氏(慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 教授/日本医療政策機構 理事/認知症未来共創ハブ 代表)
認知症共生社会の構築に向けた認知症サポーターキャラバンという「土台」の意義をあらためて感じている。その上で、3点申し上げたい。
1つ目に、普及啓発すべき「価値」は何か、ということである。認知症である前に人として、あなたも私も、どのような状況であっても、ここで生きていていいということ。そして認知機能が低下し、認知症と診断されたとしてもそれは何ら変わらず、人権に影響を与える決定事項に参加し、権利を主張できるということ。そういった哲学や権利ベースのアプローチが伝わっていくことが重要ではないか。認知症にかかわる普及啓発施策についても、その目指す方向や共有したい価値に基づいて、一人ひとりの体験が変わったのか、当事者と対話しながら振り返り、深化させていくことが求められていると思う。
2つ目に、当事者との出会い方の多様なデザインが必要である。当事者を含むキャラバン・メイトや認知症本人大使といった取り組みも起点にしながら、なにかともにする、共につくる機会を持つことは、私たちひとりひとりの「認知症観」を変えることにつながり、次の世代への希望のリレーにもなる。「経験専門家」からのリアルな学びのチャンスにもなるだろう。
これに関連する3つ目は、見守り、支援する対象から、あるいは「認知症」を超えて、「人としてともに生きる」という考え方へのシフトである。認知症のある方の困りごとを解決してあげるという観点から、パートナーとしてやりたいことを一緒に実現する体験を積み重ね、見えるようにしていくことで、ともによく生きる社会のつくり手になっていこうというフェーズに進むことができる。この15年で芽生えてきた、苦しいことも楽しいことも、まず一緒にやってみようという機運を着実に広げていくことが、共生を確かなものにしていくと期待する。
<今後への提言>
- 認知症を社会課題として捉えるのではなく、当事者と対話をしながら「すべての人が共に生きるための環境づくり」を進めるという考え方へシフトすべき
人は誰でも自分らしく尊厳ある人生を生きることができる。認知症であってもなくても、すべての人が等しく尊厳ある人生をともに生きるための環境づくりを進めるという考え方の下、認知症の普及啓発を進める必要がある。その上で、認知症共生社会に向けて、認知症本人大使やキャラバン・メイトといった既存の取り組みをはじめ、認知症の本人との出会いを多様な形で創出すべきである。また当事者組織、市民社会、アカデミアが主体となり、多様な当事者の語りを蓄積し、共通項を整理し一般化することも求められる。
- 普及啓発施策・取り組みの評価の在り方を他疾患領域の知見も合わせて再考すべき
誕生から15年が経過した認知症サポーターを筆頭に、これまでの認知症普及啓発の施策・取り組みは大きな成果を挙げてきた。今後さらに効果的な普及啓発を進めるためには、世論調査や認知症サポーター養成講座受講者への意識調査等を継続的に実施し、認知症の普及啓発施策・取り組みの効果を中・長期的に調査・分析する必要がある。
またそうした調査・分析に加え、がんや循環器病等にもスコープを広げ、疾患横断的に普及啓発施策を共有し、評価する機会を設けるほか、諸外国の好事例も積極的に参照しながら今後の普及啓発施策・取り組みの立案につなげていくことが求められる。
- 産官学民の各ステークホルダーが主体的に参画し、連携を進めるべき
認知症普及啓発施策・取り組みにおいて、国や地方自治体といった行政での取り組みに関心が集まりがちだが、地域社会で「認知症とともによりよく生きる未来」を作り上げていくためには産官学民のマルチステークホルダーの主体的な参画と連携が不可欠である。引き続き、当事者の思い・体験と知恵を中心に認知症の本人を中心として、認知症のある方、家族や支援者、地域住民、医療介護福祉関係者、企業、地方自治体、関係省庁及び関係機関、アカデミアなど国内外のステークホルダーが知見を共有・議論する場を設けることが求められる。
・・・
■開催概要
日時: 2021年4月20日(火)18:00-20:00
形式:Zoomウェビナーを使用したオンライン形式
■プログラム:(順不同・敬称略)
| 18:00-18:05 | 開会挨拶・趣旨説明 |
| 乗竹 亮治(日本医療政策機構 理事/事務局長・CEO) | |
| 18:05-18:20 | 認知症の普及啓発・本人発信支援施策の現状と展望 |
| 菱谷 文彦(厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課 認知症総合戦略企画官) | |
| 18:20-18:45 | 認知症サポーターキャラバン15年の歩み |
| 石黒 秀喜(地域共生政策自治体連携機構 事務局長代理) | |
| 18:45-19:00 | 認知症のご本人からのビデオメッセージ |
| 山田 真由美(認知症当事者キャラバン・メイト/borderless -with dementia-メンバー) | |
| 山下 祐佳里(borderless -with dementia-メンバー) | |
| 19:00-19:50 | パネルディスカッション「これまでの15年、これからの15年」 |
| パネリスト: | |
| 石黒 秀喜 | |
| 加藤 光(松戸市役所 地域包括ケア推進課 課長補佐) | |
| 進藤 由美(国立長寿医療研究センター 老年社会科学研究部 研究員) | |
| 塚田 公香(イオン株式会社 環境・社会貢献部) | |
| モデレーター: | |
| 栗田 駿一郎(日本医療政策機構 マネージャー) | |
| 19:50-20:00 | 閉会の辞 |
| 堀田 聰子(慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科 教授/日本医療政策機構 理事/認知症未来共創ハブ 代表) |
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【提言】「医療システムの持続可能性とイノベーションの両立に向けて~薬価制度改革に求められる視点を中心として~」(2025年12月26日)
注目の投稿
-
2026-01-09
【申込受付中】(ハイブリッド開催)認知症プロジェクト2025年度企画「認知症の人をケアする家族等を取り巻く認知症施策のこれから」総括シンポジウム(2026年3月9日)

-
2026-01-26
【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)

-
2026-02-05
【申込受付中】(オンライン開催)第141回HGPIセミナー「韓国の肥満症政策の現状と展望―政策推進における当事者の声―」(2026年3月3日)

-
2026-02-06
【調査報告】AMR Policy Update #5:がん医療と感染症(後編)





