【緊急提言】「成育基本法・成育基本計画の実施と運用に向けた課題と展望」(2023年2月17日)
日付:2023年3月10日
タグ: こどもの健康
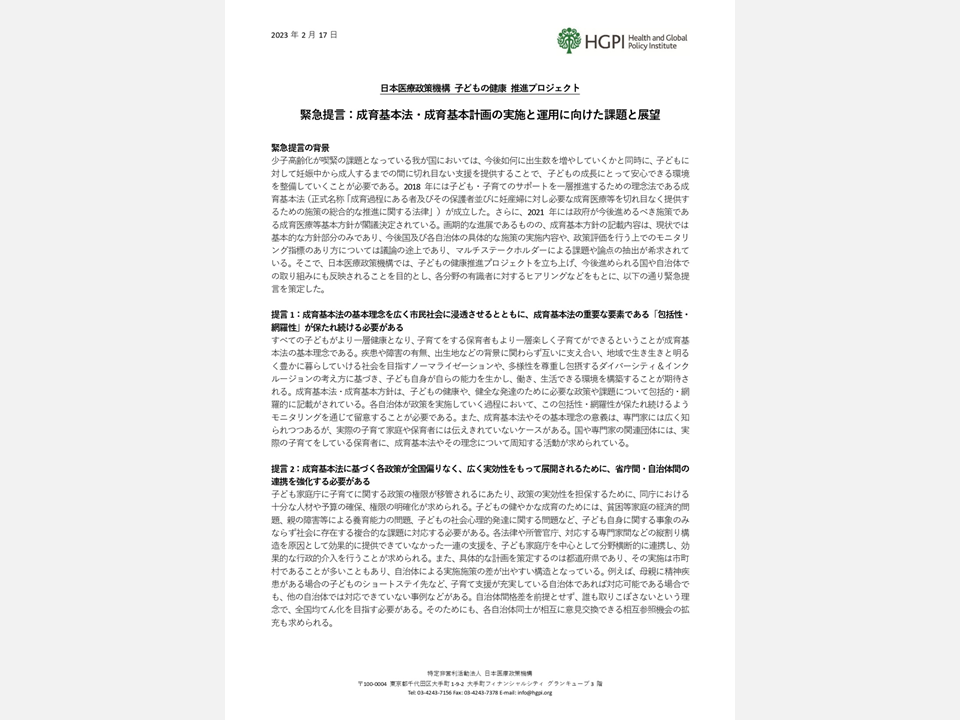
日本医療政策機構は、緊急提言「成育基本法・成育基本計画の実施と運用に向けた課題と展望」を公表しました。
少子高齢化が喫緊の課題となっている我が国においては、今後如何に出生数を増やしていくかと同時に、子どもに対して妊娠中から成人するまでの間に切れ目ない支援を提供することで、子どもの成長にとって安心できる環境を整備していくことが必要です。2018年には子ども・子育てのサポートを一層推進するための理念法である成育基本法が成立しました。さらに、2021年には政府が今後進めるべき施策である成育医療等基本方針が閣議決定されています。
これらは、画期的な進展であるものの、今後国及び各自治体の具体的な施策の実施内容や、政策評価を行う上でのモニタリング指標のあり方については議論の途上であり、マルチステークホルダーによる課題や論点の抽出が希求されています。
日本医療政策機構では、子どもの健康推進プロジェクトを立ち上げ、今後進められる国や自治体での取り組みにも反映されることを目的とし、各分野の有識者に対するヒアリングなどをもとに、以下の通り緊急提⾔を策定しました。
提言は、以下7つの要素から構成されています。
提言1:成育基本法の基本理念を広く市民社会に浸透させるとともに、成育基本法の重要な要素である「包括性・網羅性」が保たれ続ける必要がある
提言2:成育基本法に基づく各政策が全国偏りなく、広く実効性をもって展開されるために、省庁間・自治体間の連携を強化する必要がある
提言3:子どもの健康に関連するバイオサイコソーシャルな視点での政策評価・モニタリングを官民連携で行うべきであり、その指標の標準化を行い、全国での比較評価を可能とするべき
提言4:子どもの健康に関連する研究結果の速やかな社会的実装を行うべく、研究体制の構築、財政的な支援の拡充、官学間連携の継続的な推進が求められる
提言5:デジタルヘルス等を活用し医療提供体制を集約化するとともに、医療と福祉や行政の連携を推進する必要がある
提言6:家族全員を支援対象としてとらえ、子育て支援を切れ目なく実施するための、官民を含めた複合的な体制を構築する必要がある
提言7:周産期から学童期にかけて、支援・対策が不足している課題については、重点的に支援を充実させる必要がある
無痛分娩、産後ケア、母乳育児、新生児マススクリーニング、0歳児虐待、心理・社会的健康に関する診療・健康診査、学童期スクリーニングによる家族性疾患の早期発見・早期治療、包括的性教育や健康医療に関連する倫理教育
詳細については下記PDFをご覧ください。
「子どもの健康 推進プロジェクト」アドバイザリーボード(敬称略・五十音順)
阿真 京子(「子どもと医療」プロジェクト 代表/日本医療政策機構 フェロー)
五十嵐 隆(国立成育医療センター 理事長)
遠藤 文夫(熊本大学 名誉教授/くまもと江津湖療育医療センター 総院長)
千先 園子(国立成育医療研究センター こどもシンクタンク企画調整室 副室長)
中村 公俊(熊本大学大学院 生命科学研究部 小児科学講座 教授)
羽田 明 (ちば県民保健予防財団 調査研究センター長/千葉大学 予防医学センター 特任教授)
平原 史樹(横浜市病院経営本部長/横浜市立大学 名誉教授)
堀内 清華(山梨大学大学院 総合研究部医学域 社会医学講座 特任助教)
山縣 然太朗(山梨大学大学院 総合研究部医学域 社会医学講座 教授)
協賛
武田薬品工業株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
※本提言は、ヒアリングをもとに、独立した医療政策シンクタンクとして日本医療政策機構が取りまとめたものであり、アドバイザリーボード・メンバー参加者などの関係者、および関係者が所属する団体の見解を示すものでは一切ありません。また、当機構の「寄附・助成の受領に関する指針」に基づき、協賛社の有無や意向に関わらず、事業の方向性や内容を独自に決定しております。
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)











