【開催報告・専門家会合まとめ】第3回AMRグローバル専門家会合「Tokyo AMR One-Health Conference サイドイベント~アクションプラン推進に向けて国内外で取るべき施策~」(2017年11月14日)
日付:2018年4月12日
タグ: AMR
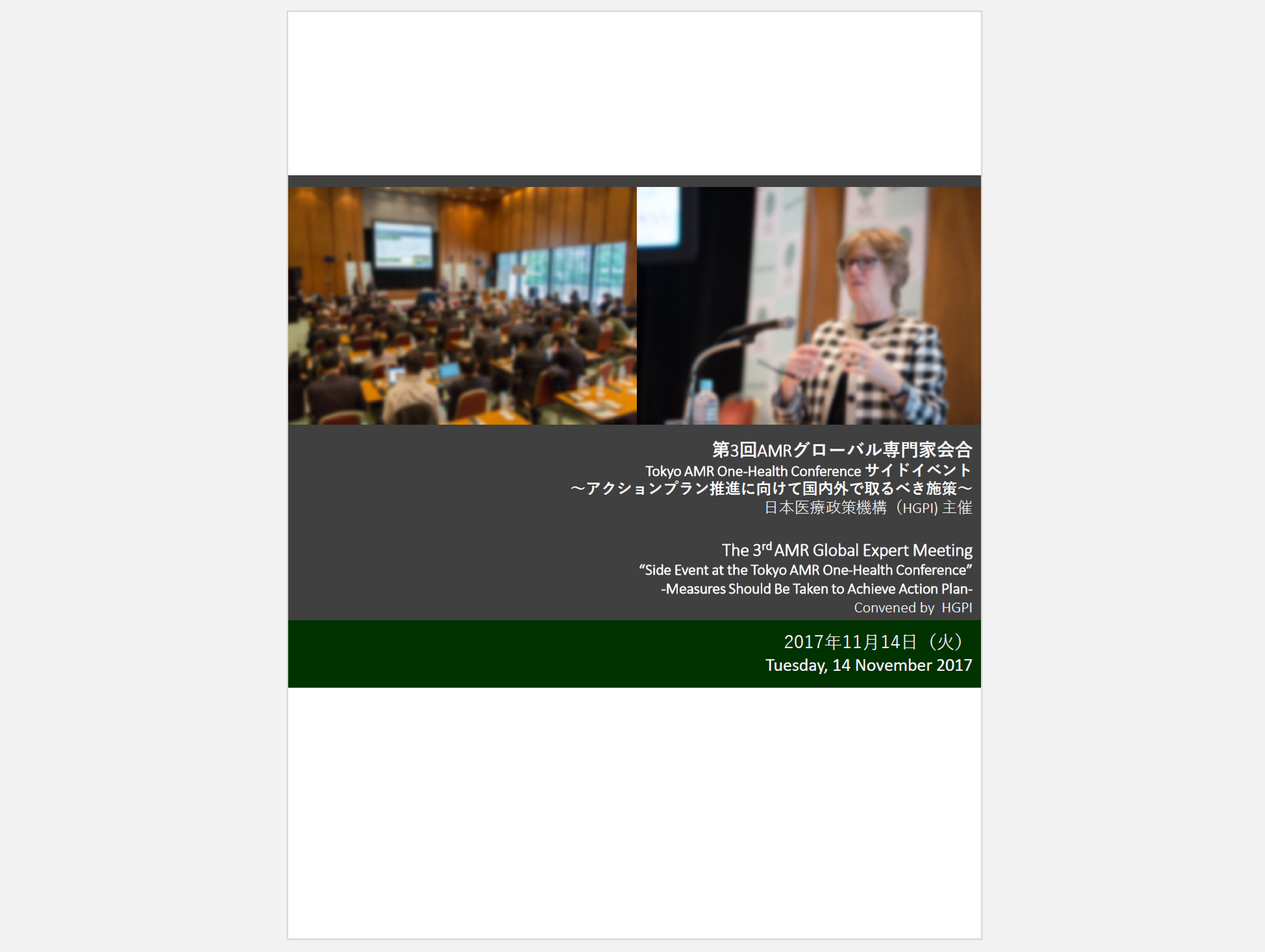
2017年11月14日(火)、日本医療政策機構は、第3回AMRグローバル専門家会合「Tokyo AMR One-Health Conference サイドイベント~アクションプラン推進に向けて国内外で取るべき施策~」を開催しました。
既存の抗菌薬が効かない細菌が世界規模で増加し、この薬剤耐性(AMR)に関する様々な課題を解決するために、各国や国際機関、企業などにおいて、対策や連携、新たな研究開発が求められています。
2017年7月21日(金)に開催された「第2回AMRグローバル専門家会合 AMRアクションプラン策定から一年 ~国内外におけるAMR政策の進展と、新たな課題~」では、マルチステークホルダーが結集し、「AMR政策の進展に向けた7つの提言(専門家会合まとめ)」を出すことができました。一層具体的な政策の形成を促進すべく、2017年11月13・14両日に厚生労働省主催の国際会議「Tokyo AMR One-Health Conference」のサイドイベントとして開催された本会合では、その7つの提言うち、迅速かつ正確な診断の推進、抗菌薬開発促進のインセンティブそして日本からの世界への貢献にフォーカスを当て議論が行われました。

本会合でなされた議論は、「AMR政策の進展に向けた7つの提言(専門家会合まとめ)」を補足する形として、下記のようにまとめられました。
今後の課題と求められる取り組み(専門家会合まとめ):
1. 適正診断を進めるべく、迅速検査の重要性を再認識すべき
- 科学的根拠(エビデンス)をもとに、遺伝子検査による迅速検査の機器の早期導入や、保険適用の観点も含めた臨床現場での遺伝子検査の活用促進につながる方法を検討すべき。
- 医療施設における監視培養の公的支援や集団発生を防ぐための検査手法の徹底など、早期の封じ込めを可能にするための環境を整備すべき。
- 遺伝子診断が難しい医療施設や高齢者施設での感染症対策として、感染症学・微生物学の専門医や公衆衛生学的な視点をもった人材を育成するための教育環境を整備すべき。
2. R&Dに関わるインセンティブを構造的に設計すべき
- 大学や製薬企業に対する研究開発(R&D: Research and Development)支援等のプッシュ型インセンティブを提供していくとともに、抗菌薬が適正使用される理想的な環境下において、収益性の低い抗菌薬開発に関して収益の予見性をもたらし、価値を反映するためのプル型インセンティブの構築を検討すべき。
3. 検査データの分野横断的かつ国際的な統合を促進すべき
- 恒常的な監視を可能にするために、信頼性が高く、かつ分野横断的なデータの収集・活用方法、および短期的なサイクルでのデータ分析方法を検討すべき。
- 高齢者施設で発生する傾向のある耐性菌の情報を包括的に収集・活用していくために、地域ネットワークを利用したデータの収集・活用が促進される環境整備を検討すべき。
- 行政や医療機関、国民が感染症について正しく理解し、安全な対策を国全体で検討することができるよう、抗菌薬の使用状況などのデータを広く共有する文化を作っていくべき。
- 世界的に信頼性の高いエビデンスの構築を支援し、臨床現場や国民に還元する仕組みを検討すべき。
4. 産官学連携の具体的進展を図るべき
- 薬剤耐性菌の制御に関して、学術分野(アカデミア)と製薬企業との連携が促進される環境構築、および産官学におけるデータの共有を支援すべき。
- 国内外に基礎研究促進と医療システムの維持向上に向けた資金を投資することにより、薬剤耐性(AMR: Antimicrobial Resistance) 対策における国際的なリーダーシップを日本が担うべき。
- ワンヘルス・アプローチによる取り組みを拡大するためには、農業や環境分野も含めた産官学の協働を推進する革新的なメカニズムの創設を検討すべき。
5. 過剰抑制に留意しつつ、アクションプランのさらなる実施を進めるべき
- 各地域の医療体制の実情を踏まえた抗菌薬へのアクセスを担保するとともに、耐性菌の拡大を防ぐためにより一層の適正使用(AMS: Antimicrobial Stewardship)の推進徹底をすべき。
- AMR対策が世界的な課題であることを再確認し、ワンヘルス・アプローチの視点も含めたアクションプランのさらなる実施を促進していくべき。
6. 国際的なリーダーシップを引き続き日本が担うべき
- アクションプランで定められた成果目標の達成につながった具体的な対策をアクションパッケージとしてグローバルに発信することを検討すべき。
- 感染症対策における優れた技術の国際展開を促進するとともに、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC: Universal Health Coverage)の世界的な達成に向けて、二国間協力、国連機関や国際機関と連携した専門家による技術協力、および研究開発促進のメカニズムへの参画を検討すべき。
- 日本が独自にアクションプランに盛り込んだ「国際協力」をより一層推進すべき。
7. 啓発活動を一層推進すべき
- ワンヘルス・アプローチの視点から、環境問題や食糧供給といった幅広い分野と関連づけたAMR対策について行政、学術研究機関(アカデミア)、企業の取り組みを横断的に共有する環境を整備すべき。
- 産官学のみならず、メディアもステークホルダーとして正しい情報を国民に丁寧に伝える啓発活動に積極的に取り組むべき。
■概要:
開催趣旨
- 黒川 清(日本医療政策機構 代表理事)

開催趣旨では、当機構代表理事黒川清より、世界的に薬剤耐性菌が増加し、新たな抗菌薬のR&Dが減少する中、人間・動物・環境が互いに影響し合うことを前提としたワンヘルス・アプローチの必要性について言及がありました。
開会の辞
- 池田 千絵子(厚生労働省 総括審議官(国際保健担当))

開会の辞では、厚生労働省 総括審議官(国際保健担当)である池田千絵子氏り2015年に世界保健総会(WHA: World Health Assembly)で採択された「薬剤耐性(AMR)に関するグローバル・アクション・プラン」を各国で厳格に履行していく必要とともに、新規抗菌薬のR&Dに向けた国際的な枠組みと産官学の連携についてご講演いただきました。
パネルディスカッション「アクションプラン推進に向けて国内外で取るべき施策」
パネリスト(五十音順・敬称略):
- 梅田 千史(MSD株式会社 執行役員 肝炎・感染症・麻酔 ビジネスユニット統括 兼 ワクチンビジネスユニット統括)
- 賀来 満夫(東北大学大学院 内科病態学講座 総合感染症学分野/ 感染制御・検査診断学分野 教授)
- 牧野 友彦(WHO西太平洋地域事務局 医官)
- Michael Bell(米国疾病予防管理センター 医療品質促進課 副課長)
モデレーター:
- 髙松 真菜美(日本医療政策機構 マネージャー)

本パネルセッションでは、「AMR政策の進展に向けた7つの提言(専門家会合まとめ)」における迅速かつ正確な診断の推進、抗菌薬開発促進のインセンティブそして日本からの世界への貢献について深い議論がなされたとともに、地域ネットワークを利用したデータの収集・活用や各地域の医療体制の実情を踏まえた適正使用の推進・徹底の重要性等についてもより具体的な議論が展開されました。またAMR対策を行ううえでの各国の現場レベルでの課題についても、会場から多くの質問やコメントがあり、活発な議論が交わされました。
基調講演:欧州の取り組みおよび英国の事例
- Dame Sally Davies (英国政府 主席医務官/AMRに関する国連機関間調整グループ共同議長)

基調講演で、Dame Sally Davies英国政府主席医務官より、英国がAMR対策を最優先課題として、国内外において積極的にワンヘルス・アプローチによる取り組みを拡大していること、国内外に基礎研究促進と医療システムの維持向上に向けた資金を投資することにより、国際的なリーダーシップをはかっていること等についてお話しをいただきました。
閉会の辞
- 塩崎 恭久 (衆議院議員/前厚生労働大臣)

閉会の辞では、衆議院議員の塩崎恭久氏より、欧米諸国における積極的なAMR対策を受けて、日本でもアクションプランが策定されたことを皮切りに国際的なリーダーシップを発揮されている実情や、我が国のAMR対策を推進するためには、農業や環境分野も含めた産官学の協働に向けた意識啓発の必要性等についてもお話しいただきました。
(順不同・敬称略)
(写真: 井澤 一憲)
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)








