【調査報告】現代日本における子どもをもつことに関する世論調査(最終報告)(2022年3月4日)
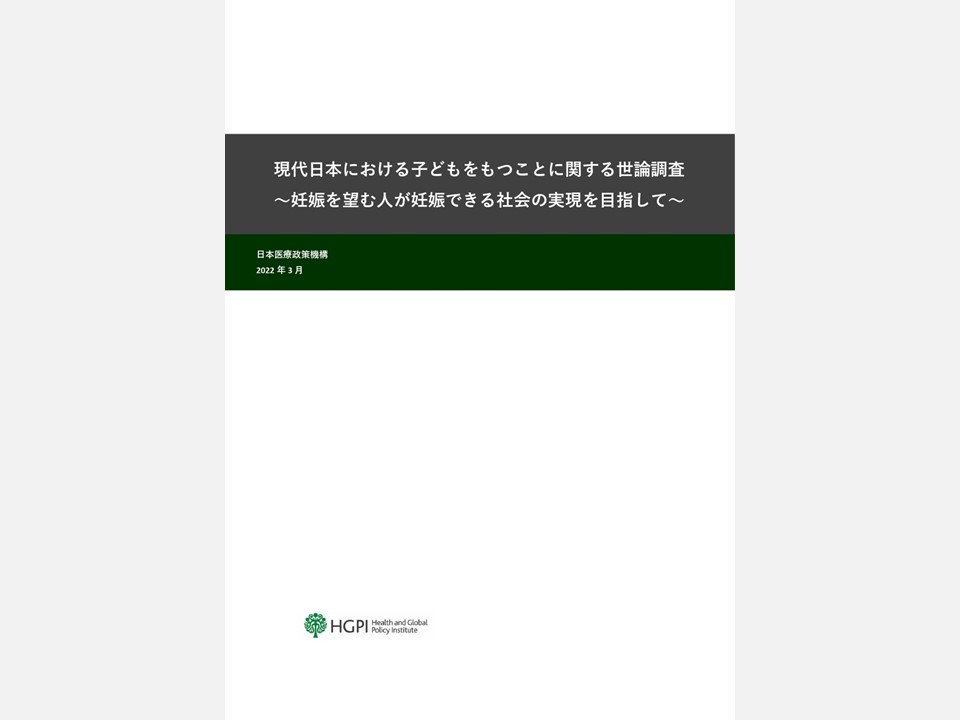
日本医療政策機構 女性の健康プロジェクトでは、女性の健康週間(3月1日~8日)に合わせて「現代日本における子どもをもつことに関する世論調査」の最終報告書を公表いたしました。
1990年に記録した過去最低の合計特殊出生率「1.57ショック」以降、日本政府は少子化対策として様々な法整備や施策を実施してきました。希望出生率1.8の実現に向け、2020年5月閣議決定された少子化社会対策大綱では、「児童手当の見直しや待機児童の解消」、「若者の雇用環境の改善」、「男性の育児休暇の取得」等が盛り込まれ、具体的な数値目標が設定されています 。しかしながら、同年6月に発表された2020年の合計特殊出生率は、1.34と前年を0.02ポイント下回り、5年連続で低下しています 。そこで新たな少子化対策として、不妊治療の助成拡大が実施され、保険適用の対象拡大に向けた議論が進められているが、妊娠を希望する世代のニーズをまだ十分には反映しきれていないとする声も少なくありません。
そこで日本医療政策機構 女性の健康プロジェクトでは、妊娠を望む人が妊娠できる社会の実現に向けて、必要かつ効果的な対策を具体的に示し、提言することを目的として、全国25歳から49歳までの男⼥10,000名を対象にインターネットでアンケート調査しました。
本調査結果から、男女における妊孕性や不妊症、さらには女性特有の健康リスク等に関して、社会全体のヘルスリテラシーに向上の余地があることが明らかになりました。また、子どもを望む人が子どもをもつことに関連する要因として、子宮内膜症や子宮筋腫、多嚢胞性卵巣症候群の診断や治療の有無、婦人科の初診時期、年収や就業形態、幼少期における近所づきあいやその後の周囲の子どもとの関わりとの関連性が示唆されました。
■ 主な調査結果
(ヘルスリテラシー)
- 女性の約半数、男性の6割以上が、月経時の症状や月経前の症状は治療が可能であることについて、「知らない」と回答
- 女性の約半数、男性の6割以上が、子宮内膜症や子宮筋腫等の器質性疾患や無月経を放置することは不妊につながるリスクがあることについて、「知らない」と回答
(婦人科系疾患)
- 子どもがいる群と比較して、現在第一子妊活中の群は、子宮内膜症、子宮筋腫、多嚢胞性卵巣症候群で治療を受けたり、診断された割合が高い傾向にあった
(社会経済活動)
- 個人年収について、「収入なし」もしくは「年収が500万円未満」と回答した人は、男性で「子どもがいる」群の37.4%、「子どもがいない」群の63.9%で有意な違いがみられた
- 現在の就業状況について、「正社員(フルタイムもしくは短時間勤務)」と回答した人は、男性で「子どもがいる」群の95.7%、「子どもがいない」群の76.8%で有意な違いがみられた
- 妊娠をしたいと思う人が妊娠できるために必要だと考える支援や制度について、子どもをもつ家庭の負担を軽減するような税制の導入、雇用対策、安定した雇用機会の提供との回答が多くみられた
(周囲との環境)
- 子どもがいない群は、子どもがいる群と比較して、子どもをもつ前の日常において子どもとの触れ合う機会があった人の割合が低い傾向があった
■ 本調査結果を受けた4つの視点
視点1: ヘルスリテラシー向上のための支援の強化
視点2: 婦人科へのアクセス向上のための体制整備
視点3: 子どもをもちたい人のための経済的支援、働き方改革の推進
視点4: 子どもと触れ合う機会の提供や地域で支えあう仕組みの促進
報告書全文は下部PDFをご覧ください。
■ 調査体制
【調査チーム】※敬称略、順不同
- 今村 優子(日本医療政策機構 マネージャー)
- 河田 友紀子(日本医療政策機構 シニアアソシエイト)
- 藤村 真耶(日本医療政策機構 プログラムスペシャリスト)
- 矢野 隆志(日本医療政策機構 アソシエイト)
- 三輪 のり子(日本医療政策機構 プログラムスペシャリスト)
- 玉腰 暁子(北海道大学大学院 医学研究院社会医学分野 公衆衛生学教室 教授)
- 木村 尚史(北海道大学大学院 医学研究院社会医学分野 公衆衛生学教室 助教)
【アドバイザリーボード】※敬称略、五十音順
<スペシャル・アドバイザー>
- 阿藤 誠(国立社会保障・人口問題研究所 名誉所長)
- 大須賀 穣(東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座 教授)
- 黄川田 仁志(衆議院議員/国際人口問題議員懇談会事務総長)
- 北村 邦夫(一般社団法人日本家族計画協会 会長)
- 木村 正(大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教室 教授)
- 黒川 清(特定非営利活動法人日本医療政策機構 代表理事)
- 野田 聖子(衆議院議員)
- 三原 じゅん子(参議院議員)
- 和田 義明(衆議院議員)
<メンバー>
- 安藏 伸治(明治大学政治経済学部 教授/明治大学付属明治高等学校・明治中学校 校長)
- 小西 美穂(日本テレビ キャスター/解説委員)
- 佐々木 かをり(株式会社イー・ウーマン 代表取締役社長)
- 治部 れんげ(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 准教授)
- 杉本 亜美奈(fermata株式会社 CEO)
- 宋 美玄(丸の内の森レディースクリニック 院長)
- 高橋 幸子(埼玉医科大学 助教)
- 福田 和子(なんでないのプロジェクト 代表)
- 吉野 正則(株式会社日立製作所 シニアプロジェクトマネージャー/北海道大学COI拠点長、客員教授)
【グローバルコーディネーション】※敬称略、五十音順
<メンバー>
- 池田 裕美枝(京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野博士課程)
- 佐藤 摩利子(国連人口基金駐日事務所 所長)
- 林 玲子(国立社会保障・人口問題研究所 副所長)
- 森 臨太郎(国連人口基金アジア太平洋地域事務所/人口高齢化と持続可能な開発に関する地域アドバイザー)
【協賛企業・組織】
- 朝日生命保険相互会社
- バイエル薬品株式会社
- 富士製薬工業株式会社
- 北海道大学
※実施にあたって同企業・組織との意見交換を行ったが、それらの意見の反映については、調査チームが主体的に判断した。
■ 本調査に関するお問い合わせ先
特定非営利活動法人 日本医療政策機構(担当:今村、河田)
■ その他
北海道大学大学院医学研究院公衆衛生学教室が、 「現代日本における子どもをもつことに関する世論調査」で得られたデータを用いて、研究課題名:生殖と関連する社会的要因の検討を2023年12月~2026年3月に実施予定です。詳細は添付ファイルをご覧ください。
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【調査報告】「2023年 日本の医療の満足度、および生成AIの医療応用に関する世論調査」(2024年1月11日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)








