【開催報告】第70回定例朝食会「グローバルヘルス・セキュリティーにおける新戦略 『グローバル・バイローム・プロジェクト』~感染症対策の最前線~」(2018年6月29日)

第70回の今回は、米国国際開発庁(USAID: United States Agency for International Development)で国際保健分野を担当されているデニス・キャロル氏をお招きしました。キャロル氏には「mapping the global virome, the transformative power of big data」と題して、グローバル・バイローム・プロジェクト(GVP: Global Virome Project)という感染症予防の国際プロジェクトについて、またそのプロジェクトに携わってこられたご自身の経験についてお話いただきました。GPVは、将来起こり得る感染症の流行リスクを減らすために、地球上の未知のウイルスのほぼすべて検出することを目的とした、10年にわたる国際的なパートナーシップです。
講演の概要
■背景と課題:なぜ今、新しい課題解決の手法が必要なのか
現在世界では、より多くの未知のウイルスが野生動物から人間に感染を拡大させており、解決しなければならない大きな課題の一つとなっている。人口の増加に伴い、人類は新たな住居の建築、野生動物の生息域への侵入、またそれらを促進する農業技術の確立によって、我々を取り巻く環境、特に野生動物との関わり方を大きく変化させてしまった。その結果人類は、より多くの感染症のリスクにさらされている。
このような状況下において、流行が起こってから対策を始める現在の手法の効果は、弱まっていく一方である。そのため、受け身ではない、積極的に課題を解決するための新しい手法が強く求められている。GVPは、その一つになり得るだろう。
■課題の解決策:GVPはどのように課題解決に貢献するのか
GPVは、科学者、生態学者、環境保全活動家、政治家、そして国際保健の専門家等が協力し、自然界に存在するすべてのウイルスのデータベースを作ることによって、従来の感染症への対策を一新するために立ち上がった、国際的なプラットフォームである。
幸運なことに、野生動物を媒介するウイルスは、推定で約150万種と、現在の技術で十分に扱える範囲である。加えて人類はすでに、ウイルスを採集し特徴を分析する、つまり未知のウイルスを既知のものに変える技術を確立している。ウイルスの主な宿主は哺乳類と水鳥類のため、それらの種の生息域にターゲットを絞ることで、費用対効果の高いサンプリングが実現可能だ。またサンプリングの過程で、ウイルスの生態についても、深い知識を得ることもできる。そして、サンプリングが完了次第、収集したすべてのウイルスの遺伝子プロファイルを作成する。このような戦略的なサンプリングと分析により、GVPはすべてのウイルスの生態および遺伝子配列のデータベース化を可能とする。
■インパクト:GVPは何をもたらすのか
GVPの包括的なデータベースは、ウイルスに対する新たなアプローチを可能とし、大きな影響を及ぼすと考えられる。なぜなら、個々のウイルスの遺伝子情報だけでなく、各ウイルス科の遺伝子情報は、将来の新型ウイルスにも効果をもたらす、より広範に有効なワクチンの開発をも可能とするからである。
さらに、そのウイルスがどこに蔓延しているのか、そしてどの地域が一番危険にさらされているのか等を含むウイルスの生態データの活用により、人々はウイルスの流行が始まった直後に、その対策を講じることができるようになる。つまり、この手法は、単に直近の危機への対処だけではなく、未来のリスクに対する投資ともいえるだろう。
受け身の感染症対策から積極的な感染症対策への変化、そして感染症に対する備えにより、パンデミックの時代に終止符が打たれると期待している。
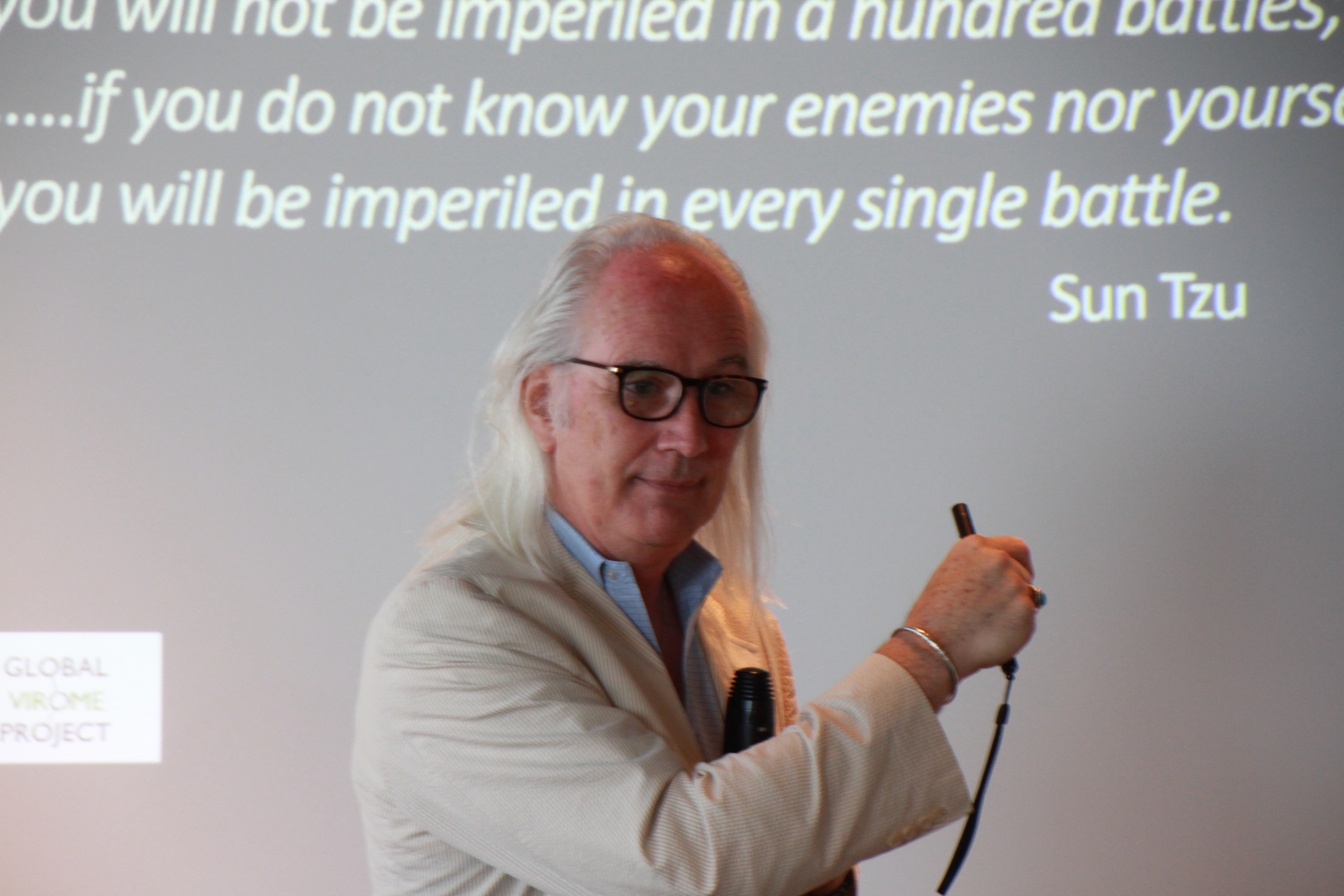

デニス・キャロル 氏
米国政府の海外援助機関であるUSAIDのグローバル保健局で新興感染症室長。新興感染症の脅威に対応する戦略作りや実務を指揮している。また、USAID代表としてグローバルヘルス・セキュリティーに携わっている。
1991年に米国疾病予防管理センター(CDC: Centers for Disease Control and Prevention)からUSAIDに出向、1995年にUSAIDで感染症を担当する上級アドバイザーとなり、マラリア、結核、薬剤耐性菌問題(AMR: Antimicrobial Resistance)、感染症サーベイランス、顧みられない熱帯感染症、新興感染症などのプログラムの責任者となった。そこで、地域レベルでの糸状虫症(オンコセルカ症)の治療、マラリアの急速診断、薬剤耐性マラリアの新しい治療法、妊婦のマラリア間欠治療、マラリアの長期残効型蚊帳などさまざまな疾病の予防や管理に携わった。また、2005年に発足したマラリア制圧プログラムであるプレジデント・マラリア・イニシアチブ(PMI)の計画、推進に発案当初から関わった。2005年からはUSAIDの職員となり、鳥インフルエンザの対応にあたった。
キャロル氏はマサチューセッツ大学アムハースト校で、熱帯病にフォーカスした生物医学の博士号を取得した。 その後、コールドスプリングハーバー研究所でウイルス感染の分子力学について研究。彼のマラリアやパンデミック・インフルエンザの業績をたたえて、CDCやUSAIDから2006年、2008年などに表彰されている。
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【調査報告】AMR Policy Update #5:がん医療と感染症(後編)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【調査報告】AMR Policy Update #4:がん医療と感染症(前編)
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【パブリックコメント提出】「気候変動影響評価報告書(総説)(案)」(2025年12月24日)







