【開催報告】第54回定例朝食会:20年後の医療ビジョン ―「保健医療2035」
日付:2015年8月27日
タグ: HGPIセミナー

20年後の医療ビジョン ―「保健医療2035」
今回の朝食会では、20年後の保健医療のあり方を検討する、厚労省の「保健医療2035」策定懇談会で座長を務めた東京大学渋谷健司教授をお招きし、「20年後の医療ビジョン」と題して開催しました。
6月9日に公表された同懇談会が示したビジョンについて議論し、20年後を見据えた「医療の持続可能性」について考える会となりました。
(懇談会による提言書はこちらからダウンロードが可能です。)
■スピーカー:
・渋谷 健司
(東京大学大学院国際保健政策学教授、「保健医療2035」策定懇談会座長)
・小野崎 耕平(当機構 理事)
■日時:
2015年7月24日(金)8:00‐9:15
■場所:
神戸屋シルフィー グランアージュ丸の内店
~講演内容要旨~(敬称略)
1、保健医療2035の概要(小野崎)
■なぜ2035年なのか?
今後20年間、さらなる高齢化の進展と人口減少という人口構造の変化に伴い、保健医療のニーズは増加・多様化し、必要なリソースも劇的に増大することが予想される。保健医療システムへの投入資源が限られる中で、地域差や医療の必要性を精査し、適切な保健医療システムを構築していかなければならない。また、2035年の保健医療に関する技術は大きな進歩を遂げていることが予測される。
一方、医療制度の改革には時間がかかる。ドイツの例やオバマケアの例にあるように、大きな制度改正を行うためには、少なくとも5~10年を超える時間が、場合によっては50年といった長い時間が必要だ。しかしこれまでは、現在、2020年、2025年を見据えた施策はあっても、その先を見据えたビジョンがなかった。これらを踏まえて、20年後という長めの時間軸が設定された。

■保健医療2035の特徴:ダイバーシティに富むメンバー
座長の渋谷先生を筆頭に、構成員は有識者と厚生労働省の官僚、アドバイザー。メンバーはこの手の会にしては若く(平均42.7歳)、官民が連携した多様性にあふれるチームであった。またメンバーを支えるアドバイザーとして、医療界の重鎮の方々にもサポートいただいたた。
■保健医療2035の特徴:検討プロセスの工夫
議論は非公開で、国際会議のルールの「チャタムハウス・ルール」(*)のもとで実施した。そのため、本質的で自由闊達な議論ができた。
また、短期間ではあったが、懇談会での議論に加え、オフサイトでの議論など100時間に渡る密度の濃い議論に加え、約20回にわたる関係者やアドバイザーとの個別の打ち合わせ、一般からの意見募集等も行った。
*議論の内容は公開できるが、発言者が特定されないようにする方式
■保健医療2035の特徴:アウトプットとスピード感
一般の方にも分かりやすいウェブサイトを構築し、さらに概要版は日英同時リリース(報告書全体版は英訳中)するなど、資料の打ち出しにも力を入れている。
また、発表の2週間後には日本経済新聞「経済教室」への記事の寄稿やランセット誌への投稿も行った。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2、保健医療2035の概要(渋谷)
■保健医療2035の背景
日本の医療が海外から注目されている事実や、日本の医療が転換期に来ているのを肌身で感じていたことから、懇談会の座長を引き受けた。既存の制度を維持することが本当に良い医療につながっているのかを考えることが、スターティングポイントであった。ウェブサイトをつくること、ポイントを3つ程度に絞ること、海外に発信することなど、ある程度は当初からイメージができていた。
■保健医療2035の特徴:若手を中心とした既存の枠組みにとらわれない議論
若手を中心に懇談会のメンバーを構成した。20年後も現役で働いている方であれば、この提言を自分たちのこととして考えることができるという趣旨からだ。また、保健医療には女性の視点も特に大切と考えているため、メンバーに女性は欠かせなかった。
既存の枠組みや制約にとらわれず、保健医療のあり方の転換や求められる変革の方向性を徹底的に議論した。省内幹部インタビューや一般からの意見も数多くいただき、そのうちのいくつかは提言に盛り込んだ。イノベーティブなアイデアが、特に官僚から出ていたのが興味深かった。3ヶ月間の策定プロセスでチームとして連帯感が強まり、アイデアや意見を出し合うことができた。
■保健医療2035の特徴:具体例の提示
我々は、「〜という方向性もあるものの、今後検討する」といった曖昧な表現をできる限り避け、具体的な例を挙げることに務めた。
一方で、報告書で挙げた例は、あくまで「こういうこともできるのではないか」と示しているにすぎない。今後、ステークホルダーと議論し、最適化していくことが重要だ。
■保健医療2035における期待
多くの人に報告書を読んでいただきたい。特に、医者・看護師や医療現場の人々には、ぜひ読んでいただきたい。そして報告書をベースに議論をし、その中からイノベーティブなアイデアを出してほしい。
保健医療2035はあくまでも厚生労働大臣の私的懇談会だが、実現に向けた実行推進本部を設置されると聞いている(*)。大臣が変わったとしても、持続性を失わずに推進していきたい。

*註:8月6日に推進本部初会合が開催された
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3、質疑応答
保健医療2035はかなり踏み込んだ提言内容となっているが、一番のポイントは?
渋谷: 以前から、住まいや地域づくり・働き方等の社会システムの変革や健康の社会的決定要因を踏まえた医療のパラダイムシフトが必要と考えていたので、その部分を提言として入れることができてよかった。すぐに変えられるものではないが、この提言書が端緒になると思う。
小野崎: 「より良い医療をより安く」を実現するためのアクションは重要であると考えている。これからは、極めて低いコストで2倍の結果を生むようなドラスティックなイノベーションが求められていると考えている。財政面でも医療のサステナビリティの観点でも必要だ。
江副(厚生労働省・2035懇談会構成員): 個人的に肝と思う点は、「医療・予防・グローバル」の3つだ。これまでは、個別に議論することはあったが、横串で議論することはなかった。特にグローバルヘルスの部分については、系統的な議論もなく、体制も弱かったため、非常に良かった。私自身は今、厚生労働省の国際課において、グローバルヘルスの取り組みを始めている。
この提言は、省内では非常に大きなインパクトをもって受け止められている。
山崎(同構成員):活発に意見を出し合いながら未来について考えることのできる、楽しい懇談会だった。医療システムとは社会システムそのものであり、個人の考え方、生き方など様々なものを含んでいる。医療に関わる民間企業の方や、医療や介護の現場にいる方々、そして医学生からも、非常に良い反応があった。提言書をたたき台とし、今後議論を広げていきたい。
【おわりに】保健医療2035での提言を実現するためには何が必要か?
小野崎: 今後、厚生労働省内に実行推進本部が立ち上り、約120の提言すべてに対して検討すると聞いている。議論の分かれるものや実現の難しいものなど、是もあれば否もあると思うので、これを機に医療界で議論を深めて頂きたい。
渋谷: 今回の提案を踏まえ、前に進もうという動きが出てくれば、それが一番良い。自身だけでなく懇談会メンバーにも様々な場に出向いていただき、積極的に意見交換をできる場を作っていきたい。
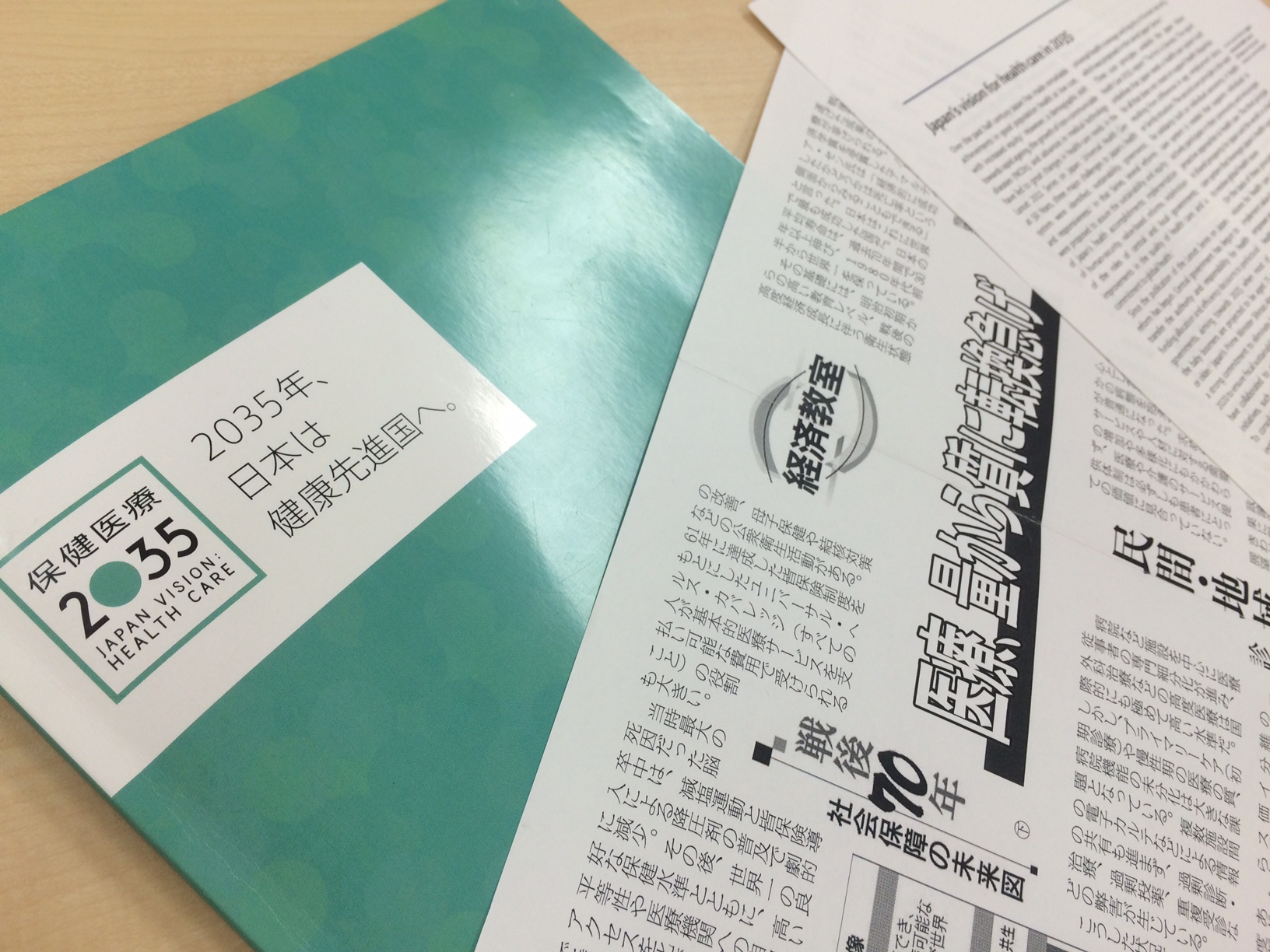
開催日:2015-08-27
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【調査報告】AMR Policy Update #5:がん医療と感染症(後編)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【調査報告】AMR Policy Update #4:がん医療と感染症(前編)







