(開催報告)第1回EOL(エンドオブライフ)ケア セミナー
日付:2013年7月5日
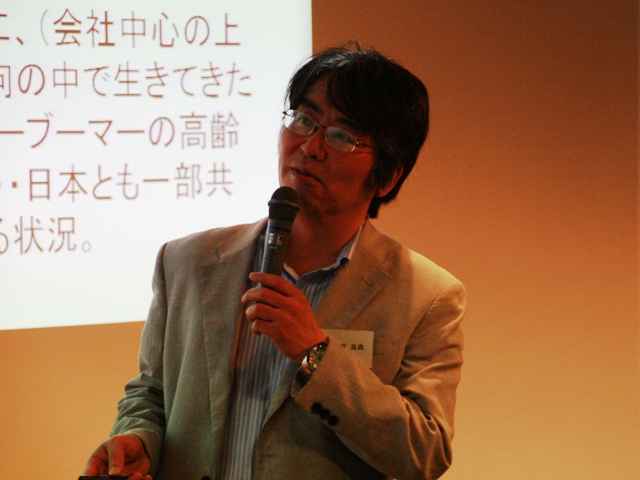
超高齢社会を迎える日本において「いかに老い、いかに死を迎えるか」—エンドオブライフ・ケア(EOL)を考えることは重要なことではないでしょうか。日本医療政策機構では日本社会で終末期について語り出し、前向きな議論を進めることが重要であると考え、全5回のシリーズでEOLケアのあり方と各自がとるべき最初のアクションを見出していきます。初回となった7月2日は千葉大学法経学部の広井良典教授から『死生観とコミュニティ』についてお話し頂き、またエンドオブライフ・ケアを語るにあたってどのような視点が必要かなど、参加者とパネリストの間で活発な議論が交わされました。
『死生観とコミュニティ』広井良典(千葉大学法経学部教授)
EOLの問題は死生観が根っこにあるテーマだと思う。いまは死亡急増時代であり病院で亡くなる人が増えているが、今後は病院に代わり老人ホームで亡くなる人が増えていく傾向が続くのではないかと思っている。単独世帯が増加していることも重要だ。性差があり男性では20代から30代、女性では70代から80代の単独世帯が増えている。また日本は世界的にみて社会的孤立の状況が高い。これらの状況を考える際に地域コミュニティという視点が重要なのだ。終末期を考えるにあたっては、死の直前期だけではなく“広さ”と“深さ”を持って捉えるべきだ。公共政策や社会システムに関する視点も重要である。いまの日本は“死生観の空洞化”であり、各個人が死生観を築き、それについて語り合う場や、伝統的な死生観の再発見が必要であろう。また、日本人の死生観を考える時、原神道的な層、仏教的な層、唯物論的な層の3つの層があるのではないか。最後に、“ケア”という言葉の意味を考える際、それは個人という存在をコミュニティや自然、スピリチュアリティの次元に繋いでいくことではないかと思っている。
参加者からの意見
「EOLケアを国民的議論にするには哲学的・内面的な話に終わってはいけない。もっと具体的な議論が出来るような環境づくりを」「死ぬ間際の問題と、どうやって死ぬのかという問題が混在してはいないか」「死生観とは3つの層に分けられるようなものでなく、実体験の積み重ねではないか」「ケアとはコンサルティングで、EOLケアの質を高める為には、患者の情報をどれだけ知っているかがキーではないか」「EOLのスタートは自己機能の低下かコミュニティからの離脱という大きな要素に分けられるのではないか」など、EOLケアの定義や論点について様々なバックグラウンドの方々から多様なご意見を頂きました。
—————————–
【第1回】EOL(エンドオブライフ)ケアの論点とは何か?-死生観を軸に考える
エンドオブライフケアを考える際に必要となる論点にはどのような広がりがあるのか、死生観を軸に大局的な視点から、明らかにしていきます。ディスカッションでは、多様な参加者の意見を出し合い、国民として今後議論を深めるべき論点を共有することを目的とします。
■日時: 7月2日(火)19:00-21:00
■会場: 東京21Cクラブ(〒100-6510 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10F)
■主催: 特定非営利活動法人 日本医療政策機構
■対象: 立法府、行政府、医療提供者、企業、アカデミア、市民、メディア等の若手・中堅 70名 (事前登録制)
(使用言語:日本語、同時通訳なし)
プログラム:
1. EOLケアを考えるための論点とは (武内 和久 (マッキンゼー・アンド・カンパニー))
2. 死生観とコミュニティ(スピーカー: 広井 良典(千葉大学法経学部教授)
スピーカーご略歴:
1961 年生まれ。東京大学教養学部、同大学院修士課程修了後、厚生省勤務をへて96年より千葉大学法経学部助教授、2003年より同教授。この間、2001年 ―02年マサチューセッツ工科大学客員研究員。専攻は公共政策及び科学哲学。著書に『死生観を問いなおす』(ちくま新書、2001年)、『定常型社会』 (岩波新書、2001年)ほか多数。『日本の社会保障』(岩波新書、1999年)でエコノミスト賞、『コミュニティを問いなおす』(ちくま新書、2009 年)で大仏次郎論壇賞受賞。
3. 会場とのインタラクティブ・ディスカッション (連続セミナー発起人が参加)
【連続セミナー発起人】 (五十音順、敬称略)
– 岩瀬 大輔 ライフネット生命保険株式会社 社長
– 小野崎 耕平 アストラゼネカ株式会社 執行役員コーポレートアフェアーズ本部長
– 渋澤 健 日本国際交流センター理事長 / コモンズ投信株式会社 取締役会長
– 武内 和久 マッキンゼー・アンド・カンパニー
– 宮田 俊男 厚生労働省課長補佐/外科医師
『死生観とコミュニティ』広井良典(千葉大学法経学部教授)
EOLの問題は死生観が根っこにあるテーマだと思う。いまは死亡急増時代であり病院で亡くなる人が増えているが、今後は病院に代わり老人ホームで亡くなる人が増えていく傾向が続くのではないかと思っている。単独世帯が増加していることも重要だ。性差があり男性では20代から30代、女性では70代から80代の単独世帯が増えている。また日本は世界的にみて社会的孤立の状況が高い。これらの状況を考える際に地域コミュニティという視点が重要なのだ。終末期を考えるにあたっては、死の直前期だけではなく“広さ”と“深さ”を持って捉えるべきだ。公共政策や社会システムに関する視点も重要である。いまの日本は“死生観の空洞化”であり、各個人が死生観を築き、それについて語り合う場や、伝統的な死生観の再発見が必要であろう。また、日本人の死生観を考える時、原神道的な層、仏教的な層、唯物論的な層の3つの層があるのではないか。最後に、“ケア”という言葉の意味を考える際、それは個人という存在をコミュニティや自然、スピリチュアリティの次元に繋いでいくことではないかと思っている。
参加者からの意見
「EOLケアを国民的議論にするには哲学的・内面的な話に終わってはいけない。もっと具体的な議論が出来るような環境づくりを」「死ぬ間際の問題と、どうやって死ぬのかという問題が混在してはいないか」「死生観とは3つの層に分けられるようなものでなく、実体験の積み重ねではないか」「ケアとはコンサルティングで、EOLケアの質を高める為には、患者の情報をどれだけ知っているかがキーではないか」「EOLのスタートは自己機能の低下かコミュニティからの離脱という大きな要素に分けられるのではないか」など、EOLケアの定義や論点について様々なバックグラウンドの方々から多様なご意見を頂きました。
—————————–
【第1回】EOL(エンドオブライフ)ケアの論点とは何か?-死生観を軸に考える
エンドオブライフケアを考える際に必要となる論点にはどのような広がりがあるのか、死生観を軸に大局的な視点から、明らかにしていきます。ディスカッションでは、多様な参加者の意見を出し合い、国民として今後議論を深めるべき論点を共有することを目的とします。
■日時: 7月2日(火)19:00-21:00
■会場: 東京21Cクラブ(〒100-6510 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10F)
■主催: 特定非営利活動法人 日本医療政策機構
■対象: 立法府、行政府、医療提供者、企業、アカデミア、市民、メディア等の若手・中堅 70名 (事前登録制)
(使用言語:日本語、同時通訳なし)
プログラム:
1. EOLケアを考えるための論点とは (武内 和久 (マッキンゼー・アンド・カンパニー))
2. 死生観とコミュニティ(スピーカー: 広井 良典(千葉大学法経学部教授)
スピーカーご略歴:
1961 年生まれ。東京大学教養学部、同大学院修士課程修了後、厚生省勤務をへて96年より千葉大学法経学部助教授、2003年より同教授。この間、2001年 ―02年マサチューセッツ工科大学客員研究員。専攻は公共政策及び科学哲学。著書に『死生観を問いなおす』(ちくま新書、2001年)、『定常型社会』 (岩波新書、2001年)ほか多数。『日本の社会保障』(岩波新書、1999年)でエコノミスト賞、『コミュニティを問いなおす』(ちくま新書、2009 年)で大仏次郎論壇賞受賞。
3. 会場とのインタラクティブ・ディスカッション (連続セミナー発起人が参加)
【連続セミナー発起人】 (五十音順、敬称略)
– 岩瀬 大輔 ライフネット生命保険株式会社 社長
– 小野崎 耕平 アストラゼネカ株式会社 執行役員コーポレートアフェアーズ本部長
– 渋澤 健 日本国際交流センター理事長 / コモンズ投信株式会社 取締役会長
– 武内 和久 マッキンゼー・アンド・カンパニー
– 宮田 俊男 厚生労働省課長補佐/外科医師
開催日:2013-07-02
調査・提言ランキング
- 【政策提言】持続可能な保健医療システムへの道筋-社会的合意が期待される三つの視点-(2026年1月22日)
- 【調査報告】「2026年 日本の医療に関する世論調査」(2026年2月13日)
- 【政策提言】我が国の予防接種・ワクチン政策の課題と展望-予防・健康づくり時代に求められるライフコースアプローチとワクチン・エクイティの視点から-(2025年4月25日)
- 【調査報告】「2025年 日本の医療に関する世論調査」(2025年3月17日)
- 【調査報告】日本の保健医療分野の団体における気候変動と健康に関する認識・知識・行動・見解:横断調査(2025年11月13日)
- 【調査報告】AMR Policy Update #5:がん医療と感染症(後編)
- 【調査報告】「働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)」
- 【政策提言】腎疾患対策推進プロジェクト「慢性腎臓病(CKD)対策の強化に向けて~CKDにおける患者・当事者視点の健診から受療に関する課題と対策~」(2025年7月9日)
- 【論点整理】社会課題としての肥満症対策~肥満症理解の推進と産官学民連携を通じた解決に向けて~(2025年8月21日)
- 【調査報告】メンタルヘルスに関する世論調査(2022年8月12日)












