
この度、中釜斉氏(国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED: Japan Agency for Medical Research and Development)理事長)をお招きし、第58回特別朝食会を開催いたしました。
2025年4月より、AMED理事長に就任した中釜氏に、AMEDの今までの成果と第3期の方針と取組についてご講演いただきました。
<講演のポイント>
- AMEDは設立から10年で医療研究の基礎から実用化まで一貫した支援体制を構築した。AMEDは年間約1,600億円を投じ、主に実用化フェーズに近い研究を重点支援しつつ、基礎から応用まで幅広い研究を推進してきた。先進的研究開発戦略センター(SCARDA)の設置や国際連携強化を通じて、感染症への備えやグローバル展開も視野に入れた体制整備を進めており、研究成果の実用化を重視した支援を実施している。
- 2025年4月から始動しているAMED第3期では、第2期の6つの統合プロジェクト体制を継続・発展させ、医薬品、医療機器、再生医療、感染症などを中心に、データ活用や臨床加速を通じた実用化を推進していく。運営面では、事業間連携、産学協創、基礎研究の充実、国際展開、医療DXを柱に、優れたシーズを効率的に実用化へと繋げる体制を強化していく。
- 国内外のベンチャーキャピタル(VC)との連携や国際的な頭脳循環の促進を通じて、日本の創薬エコシステムを国際的な創薬エコシステムに接続していくことを目指す。公的資金と民間資金の橋渡しを担う仕組みを構築し、国内外での日本の創薬エコシステムの強化を図っていく。
■AMEDの概要とこれまで(第1期、第2期)の成果について
AMEDは、医療分野における研究開発を基礎から実用化まで一貫して支援することで、研究開発の推進を後押しすること、医療分野の研究開発に活用できる環境を整備することを目的として活動している。現在、AMEDは設立10年を経て、2025年4月より第3期が始動している。
研究開発の推進における成果
AMEDは年間約1,600億円を投じて約2,600件の研究課題を支援しており、そのうち新規採択は約25〜30%を占めている。研究費の配分では、年間1,000万円から2,500万円の課題が最も多く、次いで2,500万円から5,000万円の課題が続いている。これは、実用化を目指す研究が開発後期に進むにつれて多額の資金を要するためであり、AMEDは他の公的機関による研究助成と比較しても金額が大きいことが特徴である。実際に、AMEDの研究費を獲得するには、平均して約2年11ヶ月の準備期間や他の研究資金での研究の蓄積が必要とされている。研究実績が蓄積され、実用化研究の段階でAMEDに申請・採択されている状況が構築されている。
一方で、育成しながら成果を創出していく仕組みも重要であると認識されており、開発フェーズ毎の課題採択数の割合は、基礎的・応用フェーズにある課題が大きくなっている。研究費の約6割は大学等の研究機関に支給され、次いで独立行政法人・国立試験研究機関、民間企業の順に配分されている。疾患領域別では、がん、次いで新興・再興感染症を含む感染症対策に重点が置かれている。その他、循環器系疾患や神経系疾患などにも多くの研究費が支給されている。
主な成果として、具体的には、基礎研究として6,000件以上の論文が発表され、応用研究では357件の非臨床概念実証(PoC: Proof of Concept)の獲得、434件の臨床試験が実施された。このうち40件が薬事承認を受け、実用化に至っている。研究の「出口」を明確にし、各モダリティ(創薬手法)を横断する形で研究支援することがAMEDに期待されている。
先進的研究開発戦略センター(SCARDA)の設置
先進的研究開発戦略センター(SCARDA: Strategic Center of Biomedical Advanced Vaccine Research and Development for Preparedness and Response)は、2021年6月1日に閣議決定された「ワクチン開発・生産体制強化戦略」を踏まえ、感染症の有事への備えが重要であるという認識の下、AMED内に設置された。
その主な3つの機能として、1. 広範な情報収集・分析、2. 戦略的な意思決定、そして3. 機動的なファンディングが挙げられる。ワクチン開発の推進に向けたワクチン戦略として、世界トップレベル研究開発拠点整備に515億円、新規モダリティ研究開発事業に1,500億円、そして創薬ベンチャーエコシステム強化事業関連予算に500億円が充てられ、有事の際に速やかに治療薬開発に繋げられるような体制準備を実施している。
日本の研究国際連携の取り組み
現在、日本の科学技術における国際的な位置付けの低下が懸念されている。これに対して、AMEDには、財政的支援にとどまらず、国際的な頭脳循環や国際連携、国際的な共同研究の実用化への展開に関する支援も期待されている。
例えば、米国国立衛生研究所(NIH: National Institutes of Health)との連携は、1965年の日米医学協力計画から始まり、60年以上継続している。欧州とは、感染症に関して欧州保健緊急事態準備・対応総局(HERA: Health Emergency Preparedness and Response)との協力を取り決めた。その他、共同研究や協力覚書(MOC: Memorandum of Cooperation)、e-ASIA共同研究プログラムに基づいて、様々な国と連携していく体制を構築している。
■AMED第3期における取組の方向性について
研究開発のさらなる推進に向けた統合プロジェクト体制景
AMED第2期において採用されたモダリティ等を軸とした統合プロジェクト体制については、これまでの成果や課題を踏まえつつ、基本的には第3期においても継続される。これにより、研究の一貫性を保ちつつ、さらなる発展と実用化を目指す体制を維持することができる。具体的には、「医薬品」、「医療機器・ヘルスケア」、「再生・細胞医療・遺伝子治療」、「ゲノム・データ基盤」、「疾患基礎研究」、「シーズ開発・研究基盤」の6つの統合プロジェクトに沿って、各疾患領域における研究開発が推進されてきた。そして、開発の目的がさらに明確化され、研究者の間に「出口」を意識した研究姿勢が醸成されることに寄与してきた。また、統合プロジェクトの枠組みは、事業間の連携強化にも寄与した。
AMED第3期でも、上記の統合プロジェクト体制の一部が踏襲され、主要プロジェクトとして「医薬品」、「医療機器・ヘルスケア」、「再生・細胞医療・遺伝子治療」、「感染症」が設定された(図)。さらに、これらを支えるデータ利活用およびライフコースプロジェクトが展開される。シーズ開発や基礎研究との連携を通じて、実用化への橋渡しおよび臨床開発の加速化を図る。最終的に、研究開発の「出口」として、イノベーションの創出や創薬エコシステムの強化に繋がることが期待されている。疾患領域としては、「がん」、「難病・希少疾患」、「ライフコース」(生活習慣病など、人生の各段階で蓄積されるリスクに関連する疾患を包括)の3分類に大別される。
2025年度の予算規模は、当初予算で1,232億円に加え、基金事業からの資金および理事長裁量経費(調整費)として措置される175億円を含め、総額で約2,000億円規模での運用が見込まれている。予算配分においては、医薬品プロジェクトへの配分が最大となっている。
AMEDの今後の運営方針
AMED第3期の運営方針として、以下の取り組みが掲げられている。
- 事業連携の取り組みの強化
各事業を個別に育成するのではなく、事業間の連携を強化することにより、研究開発の各フェーズ間に存在する課題の解消を図り、最終的な実用化への円滑な移行を目指す。そのために、AMED内でペアリング、マッチングの仕組みを構築・導入する取り組みが進められている。 - 研究開発の初期段階からの産学協創・企業導出
研究開発の初期段階より企業が関与することで、事業化の成功確率を高めることを目指す。 - 社会実装・貢献へつながる成果創出のための基礎研究の充実
社会実装を見据えた基礎研究の重要性を踏まえ、継続的かつ安定的な支援を通じて、成果創出に資する基礎研究の充実を目指す。 - 国際展開の推進
国際的な研究ネットワークを効果的に活用することで、シーズ開発と各事業との連携を深化させ、優れた研究成果を創出する基盤を整備する。また、世界のニーズを積極的に取り入れつつ国内での研究開発を進めることで、日本の医薬品市場が国際的にも注目されるような環境の構築に、AMEDが積極的に関与していくことが重要である。 - 医療分野の研究開発のDX
人工知能(AI: Artificial Intelligence)、量子技術等を活用し、パーソナル・ヘルス・レコードの利活用やビッグデータに基づく新たなエビデンス創出および実証を通じて、健康長寿社会実現に寄与することを目指す。
これらの方針のもと、国際的な知見も対象とした情報収集、事業間連携における課題の解消、ならびに企業への橋渡し支援を通じて、優れたシーズの実用化をより効率的に促進する体制の構築を目指す。
■最近の取組
既存の研究課題の強化と事業化を加速させる「調整費」による取り組み
AMEDの理事長裁量経費である「調整費」は、既存の研究課題の推進強化および事業化の加速を目的として活用される予算である。当該予算は、AMED内部での議論に加え、関係省庁との協議を経て、その有効な活用が図られている。2025年度における具体的な活用事例として、以下の3点が挙げられた。
- 小児先天性心疾患患者における手術設計を支援するシステムプログラムの開発に係る取り組み
小児の心臓血管構造には個人差が大きく、個別化された手術設計が求められる。開発されたプログラムの海外展開を見据え、調整費を活用し、海外の薬事規制に対応した臨床試験プロトコルの作成が支援された。これにより、日本における先進的な医療支援システムの国際展開が促進されることが期待される。 - 統合失調症の病態解明に係る研究開発
統合失調症の病態解明を目的として、記憶形成時におけるシナプスの挙動および関連分子の研究が進められている。調整費の活用により、新たな分子設計法を開発した別の研究グループとの連携が促進され、これを通じて、統合失調症に対する新たな治療標的の同定および治療薬の開発が進展することが見込まれる。 - 重症新生児に対する迅速なゲノム診断のための基盤構築および拡充
重症新生児を対象としたゲノム診断においては、既存の診断体制が東日本に1拠点のみであったため、データの保全性や対応体制に課題があった。調整費を活用し、西日本に新たな拠点を増設するとともに、データの安全性確保と遺伝カウンセリング体制の強化が図られている。この結果、ゲノム診断の迅速化・効率化が進み、診断率の向上が期待される。
創薬エコシステムの強化
研究の実用化・市場投入の際には、多額の資金が必要となる。しかし、その資金を賄うことは、AMEDの公的資金だけでは困難であり、ベンチャーキャピタル(VC: Venture Capital)や投資家、製薬企業の協力が必要である。研究段階早期における民間資金の獲得を支援するため、日本の創薬エコシステムを強化することが必要である。こうした状況を踏まえ、AMEDは以下の取り組みを新たに進めている。
人材育成と国際頭脳循環の促進
研究者とVCや投資家、製薬企業を繋ぐコーディネート機能および、それを担う人材プールの不足を課題と捉え、国際的な人材の積極的な受け入れを通じて、日本の創薬エコシステムの発展を推進している。
認定VCとの連携
AMEDでは、創薬分野への出資実績等を有する30のVCを「認定VC」として選定しており、創薬ベンチャーへの補助金交付と並行して、認定VCによる支援を組み合わせることで、医薬品開発の加速化を図っている。なお、認定VCの約半数は海外のVCであり、日本のシーズを国際的に発信する場の創出と、海外投資家からの支援獲得に資する取り組みとなっている。
国内外のエコシステムの連携
国内におけるシーズの育成を基盤としつつも、海外の創薬エコシステムとの連携を通じたグローバルな創薬の推進も重要である。海外の関係機関や投資家等に対し、日本のシーズを継続的かつ丁寧に紹介する活動を展開しており、これが日本の創薬エコシステムの発展に資するものと期待されている。あわせて、国内製薬企業の一層の参画も促進されることが望まれる。
講演後の会場との質疑応答では、事業化促進に向けた評価体制の強化の必要性、海外展開促進に向けた具体的な体制強化の内容、人材育成の方法、DXの活用促進を目指す医療研究分野等について、活発な議論が行われました。
(写真:井澤 一憲)
■プロフィール
中釜 斉(国立研究開発法人日本医療研究開発機構 理事長)
1982年東京大学医学部卒業。1990年同大学医学部第三内科助手。1991年から米国マサチューセッツ工科大学がん研究センター・リサーチフェロー。1992年医学博士号取得。1995年以降国立がんセンター研究所発がん研究部室長、生化学部長、副所長、所長を歴任。2016年4月より国立がん研究センター理事長・総長。2025年4月より国立研究開発法人日本医療研究開発機構理事長。ヒト発がんの環境要因、及び遺伝的要因の解析とその分子機構に関する研究に従事。分子腫瘍学、がんゲノム、環境発がんが専門。

このたび、特定非営利活動法人 日本医療政策機構は、2025年6月23日に開催された理事会において、武藤真祐(当機構 理事)を、副代表理事に任命することと決定いたしました。
また前・副代表理事の吉田裕明は、引き続き当機構理事として、活動に携わって参ります。
新体制のもと、さらに活動を強化して参ります。今後とも当機構をご支援頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。
■役員一覧(2025年6月23日時点)
- 終身名誉チェアマン 黒川 清
- 代表理事 乗竹 亮治(事務局長兼任)
- 副代表理事 武藤 真祐
- 理事 吉田 裕明
- 理事 小野崎 耕平
- 理事 津川 友介
- 理事 永井 良三
- 理事 堀田 聰子
- 監事 前川 健嗣
- 監事 松澤 香
※常勤の事務局長兼任である乗竹以外の役員は、非常勤・無報酬

この度、森光敬子氏(厚生労働省 医政局長(死因究明等推進本部事務局長併任))をお招きし、第57回特別朝食会を開催いたしました。
2024年7月より、女性として初めて厚生労働省医政局長に就任された森光氏に、国民が安心できる医療提供体制に向けた、地域医療の機能分化と連携についてご講演いただきました。
<講演のポイント>
- 現行の地域医療構想のもと、地域の医療機関や病床の機能分化と連携が進められており、2023年時点で病床数は119.3万床に達し、2025年度を見据えた病床数の目標をほぼ達成している。特に、医療ニーズの低い患者の在宅移行が順調に進んでいるが、病床配分には依然として課題が残る。
- 医療と介護の複合ニーズがピークになると予測される2040年に向け、厚生労働省は「新たな地域医療構想」について検討を進めてきた。検討すべき要点は高齢化に伴う救急搬送数増加と、在宅医療の需要・地域差の拡大の2つである。この課題に対応するため、高齢者特有の医療ニーズや救急搬送の実態、地域の特性を踏まえた医療体制の整備や、既存の病床機能区分の見直しなどが検討されている。
- 地域間における医師の偏在が課題として指摘されている。現在も医師の地域間での格差が拡大しており、特に人口規模の小さい地域での医師不足が懸念されている。これを是正するため、政府は医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージを策定し、経済的インセンティブや地域の医療機関の連携強化など、多角的なアプローチによる医師偏在対策の取り組みを進めている。
■地域医療構想とは何か
地域医療構想は、中長期的な人口構造の変化や地域ごとの医療ニーズの質や量の変化を踏まえ、医療機関の機能分化と連携を推進することで、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の構築を目的とする取り組みである。本構想は、2014年に成立した「医療介護総合確保推進法」に基づき制度化され、翌年から医療計画の一部として位置づけられた。
現行の地域医療構想は、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据えた高齢化の進行や、地域間の医療格差への対応を図るものである。具体的には、2025年に必要とされる病床数を、高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4つの医療機能に分類して推計し、地域の医療関係者による協議を通じて、医療機関や病床の機能分化・連携を進めることにより、地域の実情に応じた質の高い医療提供体制の構築を目指す取り組みである。
現行の地域医療構想は、社会保障制度改革国民会議報告書(2013年8月6日)に基づき進められてきた。「社会保障制度改革国民会議」は、日本の社会保障制度の将来像を検討するために設置された政府の有識者会議で、2012年8月に成立した「社会保障制度改革推進法」に基づき、同年11月に発足し、2013年8月まで活動した。その活動の中はで、少子高齢化や財政赤字の拡大といった課題に対応し、年金、医療、介護、少子化対策などの持続可能な制度改革を議論し、最終報告書では、「社会保障と税の一体改革」の基盤を築いた。この報告書では、団塊の世代が75歳を迎える2025年を見据え、医療需要と病床の推計を行い、地域毎に機能分化した病床機能に適した設備・人員体制を確保していくことが重要であると提言されている。また、必要とされる医療体制は地域によって異なるため、それぞれの地域で医療・介護の在り方を考えていく「ご当地医療」の必要性が示された。
政府は、地域の実情に応じた医療構想の推進を支援するため、自治体に対し、財政的・制度的な支援策を講じてきた。例えば、2014年度から、消費税の増収分を活用して「地域医療介護総合確保基金」という仕組みが各都道府県に設けられ、国による財政支援が行われている。各都道府県は、自らの地域の実情に応じた「都道府県計画」を策定し、その計画に基づいて医療や介護に関する事業を実施できる。
■現行の地域医療構想の評価
現行の地域医療構想は、病床の機能分化・連携を進めない場合、高齢化の進行により2025年時点で約152万床の病床が必要となると推計していた。この推計に対し、同構想は、一般病床のC3基準未満の患者(医療資源投入が比較的少なくて済む患者)を在宅医療などの医療需要に振り分けること、療養病床の医療区分1の患者(医療の必要度が最も低いと判断される患者)のうち70%を在宅医療等の医療需要に振り分けること、さらに療養病床の入院受療率の地域差を解消する取り組みを進めることで、必要病床数を約119万床に抑えることを目標としている。
2023年の病床機能報告によると、2023年時点の病床数は119.3万床であり、地域医療構想の全体の目標はほぼ達成されていることが明らかになった。その内訳をみると、一般病床のC3基準未満の患者に係る病床数は11.8万床から4.3万床に減少(64%減)、療養病床の医療区分1の患者に係る病床数は12.5万床から3.0万床に減少(76%減)、医療区分1以外の慢性期病床の減少は目標の11.9万床に近い11.3万床の減床の減少が見られた。このように、医療ニーズの低い患者の在宅移行が順調に進んでいる一方で、2023年時点の高度急性期・急性期・回復期・慢性期の病床配分には依然として課題が残っている。特に、急性期病床の分布が大きく、当初の推計と異なる状況が見られる。
■2040年に向けた「新たな地域医療構想」
背景
現行の地域医療構想は2025年までの取り組みであることから、2040年を見据えた「新たな地域医療構想」についての検討会が、厚生労働省により2024年3月から開催され、同年12月にとりまとめが行われた。
2040年には85歳以上の人口が1,000万人を超え、医療と介護の複合的なニーズがピークを迎えると予測されている。このような予測を踏まえ、「新たな地域医療構想」では、病院機能にとどまらず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護の連携など、地域における医療提供体制全体を視野に入れた構想が求められている。

検討すべき要点
このような背景を踏まえ、2040年に向けた「新しい地域医療構想」を検討するにあたり重視すべき要点は、2つある。第一に、高齢者の救急搬送数およびその割合の増加である。2020年から2040年にかけて、75歳以上の救急搬送数は36%、85歳以上に限ると75%増加すると見込まれている。現在も救急搬送の受け入れ先の確保が困難な状況であり、今後さらに厳しくなることが見込まれる。救急搬送された患者の重症度に注目すると、15歳〜65歳と、65歳以上とでは傾向が大きく異なり、高齢者では比較的軽症・中等症での搬送が増加している点が特徴的である。さらに、さらに、高齢者の急性期入院の主な原因や必要とされる医療サービスは他の年代とは大きく異なる。このような高齢者特有の医療ニーズや救急搬送の実態を踏まえたうえで、今後の医療提供体制を検討する必要がある。
検討すべきポイントの2つ目が、在宅医療への需要の増加と、その地域差である。2020年から2040年にかけて、75歳以上の訪問診療需要は43%、85歳以上では62%の増加が見込まれており、在宅医療体制の早急な整備が求められている。近年、診療所においては在宅医療体制の整備が進んでいる一方で、病院における在宅訪問診療体制の整備は十分とは言えない状況にある。
また、地域別に見ると、2040年までに在宅医療需要が50%以上増加すると予測される二次医療圏は66にのぼる一方で、人口規模の小さい地域を中心に、需要の減少が予測される医療圏も23存在する。このように在宅医療の需要には地域差が大きく、地域の特性を踏まえた体制整備が不可欠である。
病床機能と病院機能報告
病床機能は当初、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の4つに分類されていた。2014年度には、地域包括ケアシステムの一翼を担う病棟として、急性期治療後に病状が安定した患者が住み慣れた地域で療養できるよう支援する「地域包括ケア病棟」が診療報酬上の病棟類型に加わった。さらに2024年度からは、高齢者の救急搬送数の増加、特に軽症・中等症患者の増加を背景に、高齢者の早期リハビリテーションや在宅復帰を包括的に支援する「地域包括医療病棟」も新たに類型に加えられている。
一方で、現在の病床機能の分類は、基本的に若い世代の疾患経過を前提として構築されており、85歳以上の高齢者の入退院の流れや多様な医療ニーズに十分対応しきれていないという課題が指摘されている。
このような課題に対し、2040年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として、病床機能区分の「回復期機能」を急性期の機能の1部と回復期の機能をあわせもつ「包括期機能」として位置づけることが提案されている。さらに、「新たな地域医療構想」では、病床機能報告に加え、各医療機関に、「医療機関機能」の報告を求める方向が、政府の検討会で議論されている。具体的に、医療機関機能には、高齢者の救急受け入れや、在宅医療の連携機能、急性期の拠点機能、専門医機能などが含まれることが想定されている。医療機関機能報告を導入することにより、地域ごとの医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携・再編・集約化を推進することを目指している。
■医師の偏在対策
背景
2024年度時点の医師需給推計によれば、2029年には全国の医師数がほぼ需要と均衡すると予測されている。しかし、地域間における医師の偏在が課題として指摘されている。診療所の数は、人口規模の小さい二次医療圏では減少し、大きい医療圏では増加しており、医療圏ごとの格差が拡大している。さらに、診療所の医師の高齢化が進んでいるうえ、人口規模の小さい地域で新規診療所の開業が難しいと予測されることから、そのような地域での将来的な医師不足の深刻化が懸念される。
現在の医師偏在対策とその効果
現在の医師の偏在対策は主に、医師養成過程における取組と、各都道府県のへの取り組み、医師の働き方改革を柱として進められてきた。具体的に、医師養成過程における取組では、大学医学部に、地域枠(特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とした選抜枠)を設けたり、各都道府県の臨床研修の定員を、医師少数地域に配慮した定員設定にしたりすることで、地域偏在の是正を試みている。この取り組みの結果、2024年時点で、地域枠で養成された医師は約9400人に達している。また、都道府県ごとに、医師偏在の状況を把握し、必要な医師数を設定する「医師確保計画」を立て、それに基づき具体的な施策を講じている。しかし、医師の偏在は依然として解消されていない。
医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージ
 厚生労働省は2024年12月25日、医師の地域偏在を是正するため、「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」を策定した。総合的な対策パッケージは、3つの基本的な考え方に基づいている。1つ目は、医師偏在の是正は一つの取組だけでは達成できないという認識に基づき、「医師確保計画に基づく取組を進めつつ、経済的インセンティブ、地域医療機関の支え合いの仕組み、医師養成過程を通じた取組などを組み合わせた総合的な対策を実施する」というものである。2つ目は、「医師の価値観やキャリアパスを踏まえ、医師の勤務・生活環境や柔軟な働き方に配慮しつつ、中堅・シニア世代を含む全ての世代の医師にアプローチする」こと。最後に、3つ目は、「医師偏在指標だけでなく、可住地面積あたりの医師数やアクセス等、地域の実情を考慮し、支援が必要な地域を明確にした上で、従来のへき地対策を超えた取り組みを実施すること」である。
厚生労働省は2024年12月25日、医師の地域偏在を是正するため、「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」を策定した。総合的な対策パッケージは、3つの基本的な考え方に基づいている。1つ目は、医師偏在の是正は一つの取組だけでは達成できないという認識に基づき、「医師確保計画に基づく取組を進めつつ、経済的インセンティブ、地域医療機関の支え合いの仕組み、医師養成過程を通じた取組などを組み合わせた総合的な対策を実施する」というものである。2つ目は、「医師の価値観やキャリアパスを踏まえ、医師の勤務・生活環境や柔軟な働き方に配慮しつつ、中堅・シニア世代を含む全ての世代の医師にアプローチする」こと。最後に、3つ目は、「医師偏在指標だけでなく、可住地面積あたりの医師数やアクセス等、地域の実情を考慮し、支援が必要な地域を明確にした上で、従来のへき地対策を超えた取り組みを実施すること」である。
これらの基本的な考え方に基づき、政府は、医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージにおける具体的な取り組みを5つ示している。(表1)。本講演では、2つの取り組み分野について取り上げられた。1つ目は、医師確保計画の実効性の確保である。具体的には、医師が偏在している地域を重点支援区域として設定し、その地域に対する偏在是正策を優先的かつ集中的に進める取り組みである。さらに、政府は都道府県に対し、支援地域での医師偏在是正プランの策定を求めている。2つ目は、地域の医療機関の支え合いの仕組みである。具体的には、医師少数区域等での勤務経験を求める、管理者要件の対象医療機関を拡大する予定である。現在、厚生労働省では、医師少数区域等に一定期間(6ヵ月以上)勤務し、その期間で、当該地域における医療の提供のために必要な業務を行った医師を評価する制度を設け、その経験を対象の医療機関の管理者の要件としている。医師偏在パッケージでは、今後、この管理者要件を採用する対象医療機関を拡大するとともに、6ヵ月の勤務経験を1年に延長することとしている。さらに、外来医師多数区域における、新規開業希望者への、地域に必要な医療機能の要請も併せて進める方針である。具体的には、都道府県は、外来医師多数区域において、新規開業希望者に対し開業6ヶ月前に提供予定の医療機能等を記載した届出を提出してもらい、地域の外来医療に関する協議への参加を求めることができる。そのうえで、都道府県は、地域で不足している医療の提供を要請できることとされている。
このように、医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージを通じて、地域ごとの人口構造の急激な変化に対応し、将来にわたって必要な医療提供体制を確保するための取り組みが進められている。
(表1)医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージの具体的取り組み
| 取組の分野 | 具体的な取組内容 |
| 1. 医師確保計画の実効性の確保 | ①重点医師偏在対策支援区域 |
| ② 医師偏在是正プラン | |
| 2. 地域の医療機関の支え合いの仕組み | ① 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大等 |
| ② 外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等 | |
| ③ 保険医療機関の管理者要件 | |
| 3. 地域偏在対策にける経済的インセンティブ等 | ① 経済的インセンティブ |
| ② 全国的なマッチング機能の支援 | |
| ③ リカレント教育の支援 | |
| ④ 都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定 | |
| 4. 医師養成過程を通じた取組 | ① 医学部定員・地域枠 |
| ② 臨床研修 | |
| 5. 診療科偏在の是正に向けた取組 |
講演後の会場との質疑応答では、2次医療圏の見直しの可能性、医師偏在対策の具体的な取り組みに対する提案(地域枠の増加や、若手医師の地方での研修制度など)、性別にかかわらず活躍できる医師の働き方改革について、活発な議論が行われました。
(写真:井澤 一憲)
■プロフィール
森光 敬子(厚生労働省 医政局長(死因究明等推進本部事務局長併任))
1992年佐賀医科大学卒業後、厚生省入省。環境庁企画調整局保健業務課、文部省体育局学校健康教育課、埼玉県保健医療部健康づくり支援課、厚生労働省保険局医療課課長補佐、医政局研究開発振興課長を経て、2018年、女性として初めて保険局医療課長に就任。2020年環境省大臣官房審議官兼国立水俣病総合研究センター長、2022年厚生労働省大臣官房審議官 (医療介護連携、データヘルス改革担当)(医政局、老健局併任)、2023年厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 (保険局併任)を経て、2024年、女性として初めて厚生労働省医政局長に就任。

2024年11月26日、日本医療政策機構(HGPI)は「インサイトからインパクトへ:健康政策・システム研究と学びをいかにしてSDGs達成の加速につなげるか?」と題した第56回特別朝食会を開催いたしました。本会合は、ヘルスポリシーとシステムリサーチ・アライアンス(Alliance for Health Policy and Systems Research)が発表した2024-2028年戦略「Aiming for Impact(インパクトを目指して)」の公表直後に実施されたものです。
当日は、ヘルスポリシーとシステムリサーチ・アライアンス理事会議長であり、ニュージーランド元首相および国連開発計画(UNDP)元総裁を務めたヘレン・クラーク氏を基調講演者としてお迎えしました。講演後は、グローバルヘルス分野の有識者によるパネルディスカッションを行い、アンダース・ノードストローム氏(スウェーデン外務省 元グローバルヘルス大使)、山本尚子氏(国際医療福祉大学大学院教授/国際医療協力センター長)、乗竹亮治(日本医療政策機構 代表理事・事務局長)にご登壇いただきました。モデレーターは、世界保健機関(WHO)ヘルスポリシーとシステムリサーチ・アライアンス 事務局長のクマナン・ラサナタン氏が務めました。
本会合は、健康政策・システム研究(HPSR)がいかにして持続可能な開発目標(SDGs)の達成に貢献しうるか、また、エビデンスを実効性ある政策や健康アウトカムの改善につなげる上での障壁をどのように克服するかについて、活発な意見交換を行う貴重な場となりました。
■主な論点(Key Takeaways)
- エビデンスに基づく研究は、世界的に保健医療システムを強化するための基盤であり、現在のグローバルヘルスの課題解決に貢献する戦略的投資です。より強靭で効率的かつ公平なシステム構築に寄与します。
- 「何を(What)」だけでなく、「どうやって(How)」を重視する必要があります。両者を明確に理解し、言語化することが、効果的な政策立案・実行の鍵となります。
- 健康政策・システム研究(HPSR)を通じて健康アウトカムを向上させるためには、学際的かつセクター横断的な連携を推進する強い意志が求められます。
- 研究者と政策決定者の間のギャップを埋めるためには、共通言語と共通目標の設定が不可欠であり、両者間にある時間軸やインセンティブ構造の違いを理解することも重要です。
- エビデンスを生み出す人と政策を形成する人々との間で、相互理解を深めることの重要性が強調されました。
- 多様な専門家、実務家、コミュニティ間での継続的な対話と知識共有を促進することが不可欠です。同時に、これまで十分に取り上げられてこなかった地域や人々の声に耳を傾け、その声を政策形成に反映させる必要があります。
- 国際機関の役割についても議論され、各国のHPSRの能力強化や、グローバルヘルス分野における公平性の推進、政策形成支援など、より積極的な関与が期待されました。
■基調講演
 ヘレン・クラーク氏は基調講演の中で、保健医療システムおよび研究者に対し、「従来型からの脱却」を呼びかけました。すなわち、効果を生まない古い手法から一歩踏み出し、より実効性のある新しいアプローチを採用すべきだと強調しました。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックは、世界各国の保健医療システムの強みと弱みを浮き彫りにした出来事であり、その教訓を生かして、今後の危機にも耐えうる、よりレジリエントで柔軟なシステムを構築する必要があると述べました。
ヘレン・クラーク氏は基調講演の中で、保健医療システムおよび研究者に対し、「従来型からの脱却」を呼びかけました。すなわち、効果を生まない古い手法から一歩踏み出し、より実効性のある新しいアプローチを採用すべきだと強調しました。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックは、世界各国の保健医療システムの強みと弱みを浮き彫りにした出来事であり、その教訓を生かして、今後の危機にも耐えうる、よりレジリエントで柔軟なシステムを構築する必要があると述べました。
さらにクラーク氏は、研究成果をインパクトにつなげるためには、研究者と政策決定者の連携が不可欠であると指摘しました。強い政治的意志や整合性がなければ、優れた研究成果であっても活用されずに終わるリスクがあると述べ、日本における研究者と政策決定者の協働の取り組みは、他国にとっても参考となる好例であると紹介しました。
加えて、研究は贅沢品ではなく、より効果的で公平かつ持続可能な保健医療システムを構築するために不可欠な「戦略的投資」であると強調しました。最後に、クラーク氏は、今後、健康政策とシステム研究が、分野横断的な連携を通じて、世界の課題に対する具体的な解決策を生み出す原動力となることへの期待を述べ、講演を締めくくりました。
■パネルディスカッションの主な論点
保健医療システムが直面する障壁
保健医療システムにおける課題は多岐にわたりますが、その中でも特に重要なのは、異なる背景や分野の人々を結集し、解決策を見出すことの難しさです。多様な立場の人々を一堂に会することは容易ではありませんが、グローバルな課題に取り組むためには不可欠です。
また、これまでの保健医療システムは「何をするか(What)」に重点が置かれ、「どう実行するか(How)」への配慮が不足していたという点も重要な課題です。研究者はエビデンスやリサーチの重要性を理解して行動しますが、政策決定においては「How」の部分が特に求められます。実際には、政治家が必ずしも研究やエビデンスを重視するとは限らず、我々研究者側も「What」と「How」への理解が十分とはいえません。政策決定がエビデンスに基づいて行われるためには、民間・公共の両レベルにおける意思決定プロセスへの理解を深めることが必要です。エビデンスの内容だけでなく、その活用方法を理解し、具体的な解決策として落とし込む力が問われています。
さらに、言語や概念、定義の違いも保健医療システム研究における障壁となっています。研究では専門用語や学術的な表現が多用されますが、これが一般の人々にとっては理解しづらいものとなり、研究成果の活用が妨げられる一因となっています。研究の成果は非研究者に向けて発信されることが多いため、専門用語を用いず、誰もが理解できる言葉で伝える力が研究者に求められます。
また、政策立案における時間軸のギャップも大きな課題です。政策決定者は、将来を見据えた長期的な視野を持ち、限られた時間をいかに有効に活用するかを考えます。一方で、研究者は研究特有のタイムラインで動く傾向があり、このギャップが協働の障害になる場合があります。したがって、研究者は政治的な時間軸の中で、自らの研究のタイミングや意味合いを理解する必要があります。
さらに、保健医療システムに関わる専門家集団同士の連携不足も指摘されました。これにより、効果的なアウトカム指標の開発や、得られた結果の共有が難しくなっています。
特に日本における課題としては、「エビデンス」の概念そのものが不明確かつ十分に洗練されていない点が挙げられました。人は本質的に合理性よりも感情に基づいて行動することが多く、一方で政策決定者は合理性を重視するため、ここにギャップが生じます。そのため、こうしたギャップの要因を明らかにするためのエスノグラフィー(文化人類学的調査)などのアプローチが日本の保健医療システム研究において必要であると指摘されました。
その一例として、乗竹亮治代表理事は「がん対策基本法」を挙げました。同法が制定された際、国は全国47都道府県に地域がん対策推進計画の策定を求めましたが、各自治体の状況や資源は異なり、結果としてその実施状況や成果にバラつきが生じました。したがって、国は地域の実情に即した具体的な計画を提示し、自治体間で学び合いや連携を促進する必要があると述べました。これにより、地域の規模や特性が類似する自治体同士が協力し、成果を共有・検証できる仕組みづくりが重要であると強調しました。
インパクトある保健医療システム研究に必要な要素
 まず、効果的な研究を行うためには、適切なリサーチクエスチョン(研究課題)の設定と、それに基づく適切な手法の選択が不可欠です。また、研究の初期段階から多様な分野の知見を統合することが求められます。研究課題が正しく定義された時点で、現場の実践者(プラクティショナー)を含めた協働が重要となります。実践者が初期段階から研究に関与することで、現場からの視点や知見が反映され、研究の実効性や妥当性が大きく高まります。
まず、効果的な研究を行うためには、適切なリサーチクエスチョン(研究課題)の設定と、それに基づく適切な手法の選択が不可欠です。また、研究の初期段階から多様な分野の知見を統合することが求められます。研究課題が正しく定義された時点で、現場の実践者(プラクティショナー)を含めた協働が重要となります。実践者が初期段階から研究に関与することで、現場からの視点や知見が反映され、研究の実効性や妥当性が大きく高まります。
加えて、人々の価値観や行動変容に関する深い理解も重要です。研究者は人々が行動を変える背景にある価値観や心理を適切に捉えたうえで、行動変容のメカニズムに関する調査・研究を進めるべきです。人々の経験や価値観を研究の中心に据えることで、より共感性の高い、現実に即した研究成果を生み出すことができます。
また、保健医療システムが健康や開発に実質的なインパクトを与えるためには「タイムリーさ」が鍵となります。政策形成におけるインパクト創出には「勢い(モメンタム)」が不可欠であり、そのためにはタイミングを見極める力も求められます。保健医療政策やシステムに携わる研究者は、未来志向を持ちつつ、地域社会など多様なコミュニティとの対話を重ねることが重要です。こうしたコミュニティとの協働は、データの質を高めるだけでなく、地域の人々が研究に参画しているという実感を持つきっかけにもなり、結果として地域にも良い影響をもたらします。
政策の立案や実行は、現場のリアリティに根差したエビデンスに基づくべきであり、そのためには現状を適切に把握することが出発点となります。現状を正しく理解することで、改善に向けた具体的なステップを見出すことができます。
加えて、保健医療政策・システム研究においては「How(どのように)」の部分が極めて重要です。「How」のない「What(何を)」は成果に結びつかず、エビデンスも効果を発揮しません。また、どのようなレベルのエビデンスを提示するかという点も重要であり、これは政策決定における「政治の力学」と密接に関係しています。
たとえば、橋を架ける際、資材や労働力は「エビデンス」に相当しますが、「どこに橋を架けるか」は政治的判断であり、研究者が決定するものではありません。したがって、研究者は政策決定における力学や意思決定プロセスを十分に理解し、その文脈の中で有効に働くエビデンスを提供する必要があります。
このエビデンスは、研究者だけでなく、研究の対象となる「現場の声」や「受益者」の意見も反映することが重要です。こうした「市民の声」を政策に反映させることは、日本医療政策機構(HGPI)の活動の大きな柱のひとつでもあります。
国際機関の役割
国際機関は、研究活動を組織の「DNA」として位置づけるべきです。また、単に「What(何を)」に注目するだけでなく、「How(どのように)」に焦点を当て、その実効性や成果を丁寧に検証し、政策にどのように反映されているかを確認することが求められます。保健医療システム研究においては、過去の分析に留まらず、将来を見据える「フォーサイト(先見性)」が不可欠です。国際機関は研究分野におけるフォーサイトをより一層推進し、予測不能な事態や今後起こりうるシナリオに備えた取り組みをリードしていく必要があります。
また、WHOのような国際機関は、改めて自らの本来の使命に立ち返り、加盟国との連携を一層強化しながら、保健医療システム研究の推進に取り組むことが重要です。
さらに、国際機関は、これまで十分に声が届きにくかった地域からの意見を積極的に吸い上げ、バランスの取れた代表性を確保する役割も担っています。欧米諸国の意見が過度に優勢となり、アジアやアフリカ諸国の声が埋もれてしまう現状を是正し、公平な対話の場を築くことが不可欠です。
加えて、国際連合(UN)などの国際機関は、研究の安全性・自由・倫理性を守る人権擁護の立場を引き続き堅持する必要があります。研究によって時に倫理的課題が明るみに出るケースもありますが、その際には公正な科学の推進に向けた適切な支援体制の整備が不可欠です。
また、国際機関は地域横断的に優良事例(ベストプラクティス)を収集・共有し、学びを深める努力を継続することが求められます。たとえば、HGPIがタイと協力して進めた心血管疾患(CVD)に関するプロジェクトでは、限られた資源の中でも効果的に政策を推進するための知見を得ることができました。
加えて、国際機関は、国・地域・疾患を越えた「グラニュラリティ(きめ細やかさ)」を促進すべきです。特定の疾患に関する政策で得られた教訓は、別の疾患分野でも活用できるケースが多くあります。例えば、日本における認知症政策では「認知症のある方が社会の中で活躍できる」という議論がなされていますが、これは20年前にがん対策の分野でも議論されてきたテーマでもあります。こうした疾患横断的な対話は、異なる疾患領域の当事者同士が学び合う良い機会にもなります。
さらに、国際機関は、人々の心を動かす「物語」に注目し、その力を理解したうえで、自らのアジェンダのみに依拠せずに変化を促す努力を続けるべきです。国際機関の予算サイクルに合わせた柔軟な行動計画とともに、政策を推進する際に重要となる価値観や動機を正しく理解することが不可欠です。価値観への理解なくして、効果的な変革は困難です。
最後に、国際機関は、質の高い保健医療システム研究をさらに推進し、各国が相互に学び合える公平なプラットフォームの構築をリードする必要があります。そのためには、すべての国の声に耳を傾け、尊重する姿勢が不可欠です。国際連合をはじめとした国際機関は、常に謙虚な姿勢で取り組みを進め、こうした考え方を保健医療システム研究の文化として定着させていくことが重要です。
保健医療システム研究による変革の実現
保健医療システム研究は、単に成果やアウトカムを追求するだけでなく、人々がより良く生きることを促すプロセスそのものであるべきです。人々が「なぜ健康に生きることが大切なのか」を理解し、共通認識を築くことから始まる研究は、社会にとって本質的な意義を持ちます。最も重要なアウトカムは、単なる「寿命」ではなく「健康寿命」であり、「人生に年を加える」のではなく、「年に健康を加える」ことが求められます。健康を伴わない延命は真の豊かさとは言えず、今こそ「健康に生きる時間」を最大化することに焦点を当てるべきです。
また、保健医療システムをより効果的にし、研究が真にインパクトをもたらすためには、人が何に動機づけられ、何によって行動変容が促されるのかという“内発的な力”を見過ごすことはできません。例えば、芸術と健康の関係は科学から見落とされがちですが、芸術が精神的な健康に与える影響は極めて大きく、その意義は無視できません。科学者もまた、芸術のような要素が健康に及ぼす影響の重要性を理解し、それらを推進要素として取り入れることで、より持続可能な健康行動の変容を導く必要があります。
さらに、真に意味ある変化を生むためには、「失敗を受け入れる姿勢」や「リスクを取る勇気」が求められます。改革とは、リスクを取り、そこから学ぶ過程でのみ生まれ得るものであり、失敗を恐れずに挑戦することが研究者の責務でもあります。そして、さまざまな分野や背景を持つ人々との継続的な知の共創や対話を促進し、それぞれの声に対し正確かつ誠実に耳を傾ける姿勢が必要不可欠です。
保健医療システム研究が社会にとって意義あるものとなるには、アウトカムと健康の公平性の双方に目を向け、社会との信頼関係を築くことが前提となります。研究が社会的対話の一部として機能するようにするためには、これまでの「関与(involvement)」から「共創(co-creation)」へのパラダイムシフトが不可欠であり、医療サービスの利用者や市民との継続的な協働が求められます。
国ごとに保健医療システムの構造や背景は異なりますが、互いに学び合うことは可能です。そして、グローバルな課題に対しては、各国の保健医療システムが調和を図りながら連携し、グローバルな解決策を共に模索する姿勢が必要です。私たちが直面している世界的な課題は重大である一方で、私たちにはそれらに立ち向かうための知見と手段が研究を通じて備わっています。今こそ、それらを最大限に活用し、より良い未来を築く行動を起こすときです。
■質疑応答セッション
質疑応答セッションでは、参加者との間で活発かつ実りある議論が交わされました。主なテーマとしては、SDGsの達成に向けて各個人がどのように主体的に関与できるか、芸術が科学や健康にもたらす貢献、そして研究における「上手な失敗の仕方」などが挙げられました。また、製薬企業に対する信頼の構築、リサーチ・リテラシーの向上、保健医療システムの適切な評価方法に関する議論も展開され、多角的な視点からの意見交換が行われました。
(写真:井澤 一憲)
■プロフィール
ヘレン・クラーク(ヘルスポリシーとシステムリサーチ・アライアンス 理事会議長/元ニュージーランド首相/元国連開発計画(UNDP)総裁)
ヘレン・クラークは、1999年から2008年までニュージーランドの首相を務め、27年間議員として活動。彼女は経済的および社会的正義、持続可能性と気候変動対策、そして多国間主義を強く支持してきた。2009年から2017年まで国連開発計画(UNDP)の総裁として二期務め、国連開発グループの議長も務めた。以前は、オークランド大学の政治学部で教鞭を執り、学士号および修士号(優等)を取得。彼女は持続可能な開発、気候変動対策、ジェンダー平等、女性のリーダーシップ、平和と正義、そして緊急のグローバルヘルス問題への取り組みを提唱。2020年7月には、世界保健機関(WHO)事務局長によってパンデミック準備と対応の独立パネルの共同議長に任命。採掘産業透明性イニシアティブ、母子健康パートナーシップなど、公共の利益を目的とした組織やイニシアティブの理事会の議長を務める。
アンダース・ノードストローム(ヘルスポリシーとシステムリサーチ・アライアンス 理事/スウェーデン外務省元グローバルヘルス大使)
アンダース・ノードストロームは、元スウェーデンのグローバルヘルス大使であり、カロリンスカ研究所で医学を学んだ医師。現在、彼はカロリンスカ研究所とストックホルム経済学校に関連するアドバイザーとして活動している。彼は、ヘルスシステムリサーチの理事、SUN-Lancet PRIME委員会、国際ワクチン研究所のグローバルアドバイザーグループの専門家、およびヴァーチョウ財団のグローバルヘルス評議会のメンバーを務める。最近では、2020年から2021年までパンデミック準備と対応の独立パネルの事務局長を務めた。また、2006年5月から2007年1月までWHOの事務局長代行を務め、2003年から2006年まで一般管理担当のアシスタント事務局長、2007年に健康システムおよびサービス担当のアシスタント事務局長、2015年から2017年までシエラレオネのWHO国事務所長を歴任した。2002年には、エイズ、結核、マラリア撲滅のためのグローバルファンドを法的実体として設立した。彼は以前、グローバルファンド、GAVI、UNAIDS、PMNCHの理事を務め、多くの国際的な作業グループやプロセスの議長を務めてきた。2007年から2010年までスウェーデン国際開発協力庁の事務局長を務めた。
クマナン・ラサナタン(世界保健機関(WHO)ヘルスポリシーとシステムリサーチ・アライアンス エグゼクティブディレクター)
クマナン・ラサナタンは、スイス・ジュネーブにある世界保健機関(WHO)のヘルスポリシーとシステムリサーチ・アライアンスのエグゼクティブディレクターである。彼は公衆衛生の医師であり、保健医療政策とシステム研究に強いバックグラウンドを持ち、WHOや国連システム内でさまざまなレベルでの広範な経験を有する。ヘルスシステムでの25年近くにわたるキャリアの中で、カンボジアにおけるCOVID-19対応のインシデントマネージャーを務めたり、UNICEFでの持続可能な開発目標(SDGs)に向けた健康アジェンダの策定に寄与したり、WHOの健康の社会的決定要因に関する委員会の活動に貢献したり、2008年のWHO世界保健報告書の一次医療に関する執筆に参加したり、ニュージーランドにおける髄膜炎ワクチンの臨床試験を実施してワクチンの承認と導入を実現した。彼は2016年から2020年までヘルスシステムグローバルの理事を務め、2013年から2014年までロックフェラー財団のソーシャルイノベーションのグローバルフェローとして活動し、2017年から2023年までアメリカ国立医学アカデミーの微生物脅威フォーラムのメンバーも歴任。
山本 尚子(国際医療福祉大学 大学院 教授/国際医療協力センター長)
医師、医学博士、公衆衛生学修士。(旧)厚生省入省後、厚生労働省、防衛省、外務省及び自治体などで保健医療福祉関係の役職を歴任。2015年にUHCに関する国際会議、2016年には「国際保健のためのG7伊勢志摩ビジョン」、「G7保健大臣会合神戸コミュニケ」の開催、取りまとめを厚生労働省国際保健担当大臣官房審議官として担当し、日本のグローバルヘルス・リーダーシップに深くかかわってきた。2017年に世界保健機関(WHO)本部のユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)/保健システム担当事務局長補佐に就任。 2018年からUHC/健康づくり担当事務局長に就任。2021年1月1日より、国連栄養委員会委員長を併任。2022年11月末にWHOを退官し、2022年12月より現職。

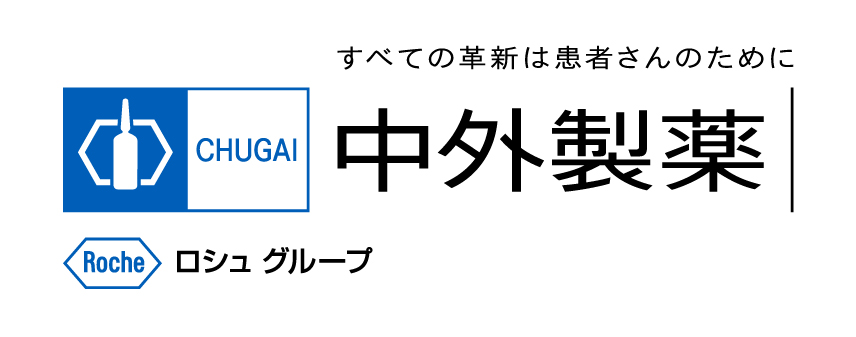
|
奥田 修 |
|
日本医療政策機構(HGPI)の設立20周年を心よりお祝い申し上げます。 中外製薬株式会社は、1925年の創立以来、革新的な医薬品の研究開発を通じて世界の医療と人々の健康に貢献することを使命としてきました。2002年にスイスの製薬企業ロシュ社と戦略的アライアンスを開始した後は、患者中心の高度で持続可能な医療を実現するヘルスケア産業のトップイノベーターを目指し、「患者中心」「フロンティア精神」「誠実」の3つの価値観のもと、革新的新薬の創出に取り組んでいます。 HGPIとは、設立当初からその崇高な理念に賛同し、2012年より賛助会員として活動を支援するとともに、「産官学民で考えるがん個別化医療の未来プロジェクト」や「患者当事者支援プロジェクト」など、重要なプロジェクトにも参画、協力してまいりました。また、医療政策アカデミーへ社員が参加する機会などあり、貴機構から多くの貴重な機会を賜りましたことに心から感謝申し上げます。 HGPIが有する専門性の高い医療政策の提言力は、我が国の医療水準の向上と課題解決に大きく寄与してきました。当社としても、これからも日本の医療政策の発展と社会課題解決に向けた貴機構の活動に大いに期待を寄せております。この度の20周年を節目に、ますますのご発展とご活躍を心よりお祈り申し上げます。 |
|
■企業情報 |


|
長山 和正
|
|
日本医療政策機構(HGPI)の20周年を心よりお祝い申し上げます。 モデルナは2010年の創業以来、人々の健康を大きく向上させるべくメッセンジャーRNA(mRNA)技術を核としたワクチン・医薬品の研究開発に取り組んでまいりました。2021年にはモデルナ・ジャパンを設立し、「mRNA医薬で人々の健康に最大の可能性を」というミッションのもと、新型コロナウイルスワクチンを通して、日本の皆さまの健康に寄与すべく邁進してまいりました。 mRNA技術は、人類が病気と闘う方法に革命を起こす可能性を秘めています。モデルナでは、感染症はもちろんのこと、希少疾患や心血管疾患、自己免疫疾患、そしてがん治療など、多岐にわたる分野で研究開発を進めております。私たちは、この技術により、これまで解決が困難だった医療の課題に対しても、新たな解決策を提供できると信じています。HGPIの専門性と行動力が生み出す成果を糧に、引き続き共にグローバルな課題に立ち向かっていけることを光栄に思います。 HGPIの20周年、誠におめでとうございます。今後もますますのご発展とご活躍を心よりお祈り申し上げます。 |
|
■企業情報 |


|
宮本 昌志 |
|
日本医療政策機構(HGPI)の記念すべき20周年を心よりお祝い申し上げます。 HGPIが活動の場とする健康・医療の分野において、協和キリンは「ライフサイエンスとテクノロジーの進歩を追求し、新しい価値の創造により、世界の人々の健康と豊かさに貢献します」の経営理念を掲げ、日本発のグローバル・スペシャリティファーマとして、独自の抗体技術をはじめ多様な創薬技術を駆使し、病気と向き合う人々の笑顔のために、画期的な新薬を生み出す研究開発に日々挑んでいます。 協和キリンは2030年を見据えたビジョンとして、「イノベーションの情熱と多様な個性が輝くチームの力で、日本発のグローバル・スペシャリティファーマとして病気と向き合う人々に笑顔をもたらすLife-changingな価値の継続的な創出を実現します」を掲げています。満たされていない医療ニーズを見出し、そのニーズに応えるための新たな薬やサービスを創造し提供すること、あらゆる部門や地域でイノベーションを起こすことで、病気と向き合う人々が「生活が劇的に良くなった」と感じ笑顔になる、そういうLife-changingな価値を継続して創出できるような会社を目指していきます。 HGPIが設立以来連綿と紡いできた健康・医療分野での情熱にあふれる活動の歴史、その活動が産み出した国内外における数多の功績に対し深く敬意を表するとともに、人々のより健康で豊かな社会の実現に向け、貴機構の益々のご発展とご活躍を祈念いたします。20周年、誠におめでとうございます。 |
|
■企業情報 |

* 岸田文雄内閣総理大臣によるビデオメッセージが首相官邸ウェブサイトに公開されました。(2024 年9月26日)
日本医療政策機構とAMRアライアンス・ジャパンは、AMR(薬剤耐性)に関する国連総会ハイレベル会合 サイドイベント「AMRに関する世界的アクション:UHCにおける健康長寿と持続可能性の促進」をアメリカ・ニューヨークで開催いたしました。
2024年9月の第79回国連総会に併せて、9月26日にAMR(薬剤耐性)に関するハイレベル会合が開催されます。2016年以来、8年振りに国連における首脳級会合の議題としてAMRが取り上げられることから、AMR対策における、これまでの日本の貢献を議論し、国際社会に発信するとともに、今後の国際連携の在り方を描く場を設けました。AMR当事者、産官学民の有識者が世界各国から集まり、活発な意見交換の場となりました。
また、本会合の開催にあたり、岸田文雄内閣総理大臣からビデオメッセージを、Dame Sally Davies 英国政府AMR特使からは書面でメッセージを頂戴いたしました。
※本会合での議論を踏まえた論点整理は、後日公開予定です。
【開催概要】
- 日程:2024年9月25日(水)14:00–16:00(現地時間)
- 会場:日本クラブ(145 West 57th Street, New York, NY 10019)※現地のみ、オンライン配信なし
- 言語:英語
- 主催:日本医療政策機構、AMRアライアンス・ジャパン
- 共催:厚生労働省
- 協力:AMR マルチステークホルダープラットフォーム、CARB-X、GARDP、Global Coalition on Aging、国際製薬団体連合会、日本国際交流センター、日本製薬工業協会
- 後援:日経・FT感染症会議
【プログラム】(敬称略・アルファベット順)
| 14:00-14:05 | ビデオメッセージ |
|
岸田 文雄(内閣総理大臣) |
|
| 14:05-14:15 | 開会の辞 |
|
塩崎 恭久 (勁草日本イニシアティブ 代表理事/AMRグローバル・リーダーズ・グループ メンバー/日本国際交流センター「グローバルヘルスと人間の安全保障」運営委員会 委員長) |
|
| 14:15-14:20 | 趣旨説明 |
|
河野 結(日本医療政策機構 マネージャー/AMRアライアンス・ジャパン) |
|
| 14:20-15:20 | ラウンドテーブルディスカッション「国際社会におけるより良いAMR政策の実現に向けて – 日本からの貢献、日本への期待」 |
|
登壇者: |
|
|
Peter Beyer(GARDP デピュティエグゼクティブディレクター) |
|
|
Vanessa Carter(AMRサバイバー WHOタスクフォース 委員長、The AMR Narrative エグゼクティブディレクター) |
|
|
Christos Christou(国境なき医師団 インターナショナル会長) |
|
|
井上 肇(厚生労働省 大臣官房 国際保健福祉交渉官) |
|
|
大曲 貴夫(国立国際医療研究センター 国際感染症センター センター長/国立国際医療研究センター病院 AMR臨床リファレンスセンター センター長) |
|
|
Kevin Outterson(ボストン大学 教授/CARB-X エグゼクティブディレクター) |
|
|
澤田 拓子(日本製薬工業協会/塩野義製薬株式会社 取締役副会長) |
|
|
Thanawat Tiensin(AMRマルチステークホルダープラットフォーム/国連食糧農業機関 事務局長補・首席獣医師官/国連食糧農業機関 畜産・動物衛生部 ディレクター) |
|
|
Anna Wechsberg(英国保健省 インターナショナルディレクター) |
|
|
モデレーター: |
|
| 15:20-15:30 | 閉会 |
| 15:30-16:00 | ネットワーキング |
(写真:Christopher Cataldi)
Message from Dame Sally Davies
AMR impacts all of us. Over 1.1million people died from AMR in 2021, and by 2050, more than 39million people will die. They could be any one of us, from anywhere in the world, although the burden falls the greatest in western sub-Saharan Africa, Tropical Latin America, high-income North America, Southeast Asia, and South Asia. That’s why this High-Level Meeting is key to driving global action and I am grateful to HGPI and the AMR Alliance Japan for corralling ambition and action, and for the crucial demonstration of support from Fumio Kishida, Prime Minister of Japan. The High-Level Meeting will put access at the heart of our action:
- Access to antibiotics, which could save 92 million lives between 2025 and 2050.
- Access to sustainable financing – we need to leverage and make accessible the financing that is already out there in multilateral streams and development banks to fund National Action Plans on AMR.
- Access to education, scaling up some of the fantastic initiatives across the world, such as AMR art and drama clubs for schools in Tanzania.
The first key step will be Member States agreeing to establish a new independent science panel on AMR, which we desperately need to assess the evidence that is out there and inform future targets and interventions. I hope the panel will be based at the UN Environment Programme HQ in Nairobi – so it can look at human, animal and environmental aspects of AMR, and be rooted where the burden of AMR is greatest. I look forward to working with you all to deliver on our commitments and making progress to stop 39 million people dying by 2050. Everyone can play a personal and professional role in how they use antibiotics, consume meat, and raise awareness. We can do it, together.
Dame Sally Davies
Special Envoy on Antimicrobial Resistance for the United Kingdom

この度、武見敬三氏(参議院議員/厚生労働大臣)をお招きし、第54回特別朝食会を開催いたしました。
2023年9月から厚生労働大臣を務められている武見氏に、今後の厚生行政についてご講演いただきました。
<講演のポイント>
- 少子高齢化・人口減少時代において、厚生労働行政は歴史的な転換期にある。
- 社会・経済の活力が、国内・海外に広く行き渡るシステムを構築し、未来型デジタル健康活躍社会を実現することが求められている。
- そのためには、医療DXやイノベーションの推進、健康危機管理研究機構(JIHS: Japan Institute for Health Security)や「UHCナレッジハブ」を通じた国際連携が重要である。
■日本の保健医療分野のこれから
日本の生産労働人口は2030年から急速に減少し始め、2040年には高齢者人口がピークを迎える。その後、高齢者人口は減少に転じ、日本の人口が急減する。国際社会において先頭グループを維持できるような社会・経済を如何にして再構築するかが、最大のテーマである。
医療制度改革の一丁目一番地が医療・介護DXの推進であることは明白である。その上で、全世代型の社会保障制度を、持続可能かつイノベーションを吸収できる形で再構築することが求められる。医学・医療の進歩はコストが極めて高く、現在の保健診療における医療財源の枠組みの中で全てをカバーすることが難しい。新たな医療財源を確保し、科学の進歩を医療保険にどう取り込むかという考え方が必要である。保健・医療・介護を改めて産業政策の適用対象に位置づけ、厚生労働省としてポテンシャルを引き出す政策を展開しなければならない。
また、一連の政策転換は、いずれも国際的な文脈で考える必要がある。人材・資本・技術を国際的に連携して産業政策を展開しなければ、日本企業だけで解決しようという極めて偏狭なナショナリズムになりかねない。保健・医療・介護の産業政策と国際連携によりイノベーションが確実に進展し、日本の社会・経済を確実に復活させ、未来型のデジタル健康活躍社会を作ろうという構図である。
■未来型のデジタル健康活躍社会の実現に向けて
2050年に世界の65歳以上の人口の7割弱はアジアに居住することになる。アジアの国々では、高齢化による疾病構造の変化に対応できない国々が多く出現し、不適切な健康格差の拡大が起きる。日本はアジアにおける最先端の高齢者社会であり、知見が官民学に蓄積されている。これらの知見を加工・活用し、政府は政府開発援助(ODA: Official Development Assistance)のようなツール、民間は市場のメカニズムを通じて相互連携を取り、戦略的にアジア諸国の健康格差を適切に抑止できるよう貢献しなければならない。
また、国際戦略と国内戦略が極めて緊密に連携する必要がある。例えば、日本で不足している介護人材をアジア各国から調達し、日本での労働経験を積んだ人材をその後、母国で幹部社員として登用することで、労働力の循環が可能な産業展開を進めることができる。
そして、国際社会の中で、日本が正しく、大きく貢献しようとしている旨を示さなければならない。日本は直近20年間程度、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC: Universal Health Coverage)において国際社会を主導している。2008年のG8洞爺湖サミットで、保健システムの強化を初めて主要政策課題として取り上げた。以後、人材・情報・財政を主要な3要素として位置づけ、その上で、UHCが保健システムアプローチの目的となるべきとの考えの下、国際社会に積極的に働きかけている。安倍政権時代には、世界保健機関(WHO: World Health Organization)事務局長、世界銀行総裁、国連児童基金(UNICEF: United Nations Children’s Fund)事務局長といったリーダー達が、日本主導の下で国連総会の前に一堂に会し、UHCの重要性を確認するという国際会議を2年続けて開催した。結果として、持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)でもUHCが取り上げられている。
現在、「すべての人が、適切な健康増進、予防、治療、機能回復に関するサービスを、支払い可能な費用で受けられる」というUHCの定義を達成するためには、ファイナンスに優先順位を置く関心が高まっている。2019年に開催されたG20大阪サミットにおいて歴史的な財務大臣・保健大臣合同会議が開催され共同声明がまとめられている。2023年のG7広島サミットの首脳宣言などをもとに、世界銀行とWHOが連携し、低中所得国の保健財政の専門家を集め、「UHCファイナンスのための知識(Knowledge for UHC Finance)」を学ぶための2週間の研修を年4回実施できないか検討している。加えて、年1回、招待制のUHCハイレベルフォーラムを日本が主催し、主要なステークホルダーの代表者を東京に集め、UHC推進の方向性を議論・確認する。このようにしてUHCの推進力を日本が作り上げたいと考えている。こうした役割を通じて、インド太平洋における健康戦略などが、正統性(Legitimacy)をしっかり持った形で展開されることにより、日本が果たす国際保健における役割をより明確にしていきたい。
■国内戦略
医療・介護DXの更なる推進
現在の電子カルテ情報システムは各医療機関のテーラーメイドであるため、横連携できず、コロナ禍における状況判断では大きなハンディキャップとなってしまった。これを改善するため、医療情報(いわゆる「3文書6情報」)の一次利活用に関わる全国的なプラットフォームを設ける。プラットフォームに接続するアプリケーションを政府が2024年度中に開発し、2025年度から各医療機関に配布、2026年度からアプリケーションを通じて診療報酬(レセプト)の申請もできるという工程表を策定した。
マイナ保険証も必要である。医療機関でマイナンバーカードを顔認証の機械にカードを入れ、「同意する」をクリックすれば、直ちにそこでマイナンバーカードはマイナ保険証になる。保険証にしておくことで、救急搬送時には救急救命士が救急車の中に積んである機械を通じてカードを読み取り、病院到着前に既往症や処方情報を把握でき、病院側はより迅速な対応が可能となる。
イノベーションを健康づくり・治療に活かす環境整備
最早この電子カルテを超えるウェアラブルデバイスが、今後急速に普及すると考えられる。既に多くの項目を検診でき、生成AIを通じて異常数値を検知すると、直ちに本人とかかりつけ医・医療機関に知らされ、初期診断をより迅速に行うことができる。高齢者の場合、認知症の深夜徘徊でもウェアラブルデバイスで見守ることができ、確実に少ない人数で介護サービスの提供もできる。まずは富裕層にウェアラブルデバイスを自己負担で購入いただき、登録済みの医師や医療機関に対しては、保険診療での一定の加算により、24時間健康管理でサポートするしくみを作ることも可能である。
また、医学・医療の進歩をより積極的に取り入れるためには、新たなしくみの導入が必要である。選定療養や様々な個人負担にある療養制度を活用しながら、進歩の果実を先進的に活用し、保健医療と結びつけたシステムを作る。そして、ウェアラブルデバイスなどが大量に生産されることになれば確実にコストを抑えられるようになり、保険診療の適応対象にも組み込むことができるかもしれない。同じ時期だけで平等か否かの判断をするのではなく、時間軸を設けて、確実に進歩の果実が1人でも多くの方々にきちんと公平に行き渡るという考え方で新しい制度の設計をしていくことが必要である。
イノベーションの国際展開
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な感染拡大(パンデミック)では、国内の医薬品メーカーがmRNAタイプのワクチンの開発で遅れをとってしまった。ワクチンのみならず、経口薬やその他の医薬品に関しても、日本の創薬基盤や完成された医薬品の世界におけるマーケットシェアは衰退し始めている。アメリカでは、アカデミアの研究開発から、大量の資金が必要なヒト初回投与(FIH: First in Human)試験、治験、政府の許認可、大量生産設備の確保までが全て繋がっている。米国の企業がmRNAワクチンを開発した際も、ドイツの企業と連携し、国境を越えて新しい医薬品が開発された。それがもはや当然の時代である。
日本は、まずは潜在力の高いアカデミアを対象として、特定の創薬と結び付いた研究開発能力をアカデミアの中でターゲットを決めて発展させるべきであり、このような創薬基盤強化を主導する「創薬基盤強化機構(仮称)」のような組織が必要である。当該組織が政府・民間合わせて1兆円規模で資金を調達し、通常であれば資金調達が困難な創薬初期段階から投資し、創薬のための科学者、いわゆるアクセラレーター(Accelerator)がアカデミアと共に研究開発をしていくことで、より創薬開発能力が強化されるしくみを作りたい。アクセラレーターは海外から招聘し、技術開発を支援していただく。投資に協力する方々には優先交渉権を保証し、創薬と関係性の深い物質(シーズ)の開発があれば高値で購入いただき、知的所有権にかかわる法律上の整備もきちんとした上で、持続可能な形で財源を確保しつつ投資していくべき。アカデミアは神聖なもので、利害関係者と緊密になって学者が儲けることはけしからんという文化があった。そのような文化は捨て、優れた学者は製薬企業とも連携をしながら開発していただく。知的所有権についても確保する体制を整え、資金を稼いでいただけるしくみを、今デザインしている。
医療提供体制の改革(医師偏在対策など)
海外からの患者(インバウンド患者)への対応も重要課題である。2023年には2000人以上の方々が医療ビザを取って日本で治療をされた。ほとんどの方が入院治療であり、医療サービスがある意味で浸食されている。今後の病床管理のしかたとして、国外の患者や自由診療の患者に関しては、別枠で規制し、国内の医療体制と共存するしくみが必要。インバウンド専門の病院を作り、海外(アウトバウンド)で展開している企業も経営に参画し連携することで、産業政策として医療サービスを展開し、諸外国との健康格差の是正に貢献すると同時に、臨床技術の移転も行えるしくみを作っていきたい。それぞれの国の医療制度、地域ごとの医療従事者と緊密に連携することが成功の秘訣であり、このような連携の中心は医師である。日本の医学部には260人程度の留学生がいるが、各国の医師志望者を上手に選考し、奨学金を与え、日本で医師の資格を取っていただく方々を増やしたい。最終的には、日本の国家試験も英語受験が可能とすることも想定される。「日本版CDC(Centers for Disease Control and Prevention)」こと「健康危機管理研究機構(JIHS: Japan Institute for Health Security)の基幹言語は英語である。危機管理には国外との連携が不可欠であり、英語でなければ連携が出来ない。
医師偏在対策について、2024年の「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」では、管理者要件の大幅拡大が明確に書き込まれた。病院院長の要件として、プライマリーヘルスケアに関わる研修を受けた上で、過疎地で最低1年は医師として従事いただく。大学や市民病院が中心となって都道府県ごとに医師をプールすることで、医師不足地域での医師確保がより確実にできるような制度設計を目指す。
■国外戦略
世界の感染症対策を牽引する、感染症危機管理体制の構築
2025年の4月1日にJIHSが創設される。骨格になる動向調査(サーベイランス)システムの構築には、各都道府県の地方衛生研究所・保健所との連携が不可欠であるものの、危機管理におけるトップダウンの一貫した指揮命令系統まではできていない。平時から都道府県と協議し、有事において直ちに一貫した指揮命令系統のもとで情報共有できるシステムが必要である。JIHSの理事会メンバーには各知事会・市町村の代表にも入っていただき、必要な人材が国内にいない場合は、海外からの招聘も検討している。秋ごろには(JIHSの)理事長の人事も決まり、具体的に組織編成が行われる。
世界の安定と平和の礎を構築するために途上国の健康医療政策を支援する「UHCナレッジハブ」の日本設置
2023年広島サミットの成果文書に「この目的のため、我々は、UHC行動アジェンダに関するG7グローバル・プランを承認し、関連する国際機関を支援し、財政、知見の管理、人材を含むUHCに関する世界的なハブ機能の重要性に留意する。(To this end, we endorse the “G7 Global Plan for UHC Action Agenda” and note the importance of a global hub function, in support of relevant international organizations, including for financing, knowledge management, and human resources on UHC.)」という用語が入った。この、G7各国との合意事項を進めるために、世界銀行とWHOが連携し、重層的に国際的なガバナンスの構造を作り、低中所得国における保健医療システムの財政基盤の拡大を目指す。そのための人材育成と一定のシンクタンク機能を作り、定期的に指導者が議論できる場所を提供することで、UHCを達成するための推進力となる。
途上国の健康医療政策支援において、日本には大きな比較優位性がある。政府はこれらの知見を戦略的に活用し、新しい産業政策としての保健・医療・介護を行う方針である。保健・医療・介護を通じて、日本の社会・経済の活力を再度作り上げ、国際社会における健康格差是正に大きく貢献し、国として発展させていきたい。
 |
 |
講演後の会場との質疑応答では、創薬イノベーション、感染症の動向調査(サーベイランス)、医師偏在の是正、財源の確保や人材育成について、活発な意見交換が行われました。
(写真:井澤 一憲)
■プロフィール
武見 敬三(参議院議員/厚生労働大臣)
1951年11月5日東京都港区生まれ。1974年慶應義塾大学法学部政治学科卒業、1976年同大学法学研究科修士課程修了。1980年東海大学政治経済学部政治学科助手、1987年助教授、1995年教授就任。同年参議院議員に初当選。
1984年~1987年、テレビ朝日CNNデイウォッチ、モーニングショーのキャスターを務める。公務では外務政務次官、参議院外交防衛委員長、厚生労働副大臣、政務では自民党総務会長代理、参議員自民党政策審議会長を歴任。国連事務総長の下で国連制度改革委員会委員、同じく母子保健改善の為の委員会委員、世界保健機構(WHO)研究開発資金専門家委員会委員を務める。2007年~2009年までハーバード大学公衆衛生大学院研究員。2019年~2022年までWHO(世界保健機関)UHC担当親善大使。2020年にはUNDP(国連開発計画)人間の安全保障に関する特別報告書ハイレベル諮問パネルの共同議長に就任。日英21世紀委員会の日本側座長も務める。2023年には、厚生労働大臣に就任し、現在に至る。

このたび、特定非営利活動法人 日本医療政策機構は、2024年6月21日に開催された理事会において、7月1日付で乗竹亮治(当機構 理事・事務局長)を、代表理事に任命することと決定いたしました。乗竹亮治は、引き続き当機構 事務局長としても、その任にあたります。
また、黒川清は、理事・終身名誉チェアマンとして引き続き当機構の活動に携わって参ります。
設立20周年の節目を迎えた本年は、新体制のもと、さらに活動を強化して参ります。引き続き当機構をご支援頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。
■役員一覧(2024年7月1日時点)
- 終身名誉チェアマン 黒川 清
- 代表理事 乗竹 亮治(事務局長兼任)
- 副代表理事 吉田 裕明
- 理事 小野崎 耕平
- 理事 津川 友介
- 理事 永井 良三
- 理事 堀田 聰子
- 理事 武藤 真祐
- 監事 前川 健嗣
- 監事 松澤 香
※常勤の事務局長兼任である乗竹以外の役員は、非常勤・無報酬

この度、赤堀毅氏(外務省 地球規模課題審議官)をお招きし、第53回特別朝食会を開催いたしました。
2022年1月から地球規模課題審議官(大使)を担われている赤堀氏に、「日本政府の交渉責任者が見据える世界の健康を守るルール作り:「パンデミック条約」の展望」についてご講演いただきました。
<講演のポイント>
- 日本は人間の安全保障を外交理念の中核として推進し、その基盤である国際保健分野での取り組みを通じて、グローバルヘルスの課題への対応に貢献してきた。
- 2022年5月には日本の国際保健に関する基本方針として、グローバルヘルス戦略を策定し、その中でグローバルヘルス・アーキテクチャー(GHA)構築への貢献及びユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を政策目標とした。また、2023年のG7広島サミット及び長崎保健大臣会合では、1. グローバルヘルス・アーキテクチャー(GHA)、2. ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)、そして3. 研究開発(R&D)を中心に、日本が議長国としてG7各国の議論を主導した。
- そのような取組の中、新型コロナウイルスの教訓を踏まえWHO加盟国間で世界の健康危機への対応能力の構築・強化に関する議論が行われた結果、2021年にいわゆる「パンデミック条約」作成のための政府間交渉会議(INB)の設置が決定され、現在まで交渉が継続している。
- 将来のパンデミックへの予防、備え、対応強化のため、「パンデミック条約」の作成等を通じた国際的規範の強化は、グローバルヘルス・アーキテクチャー(GHA)構築の観点からも重要であり、日本としても建設的に議論に貢献していく考えである。
日本の国際保健分野での取組み
日本は従来から国際保健外交を重視していたが、特に2000年のG8九州沖縄サミットでは感染症対策を大きく取り上げ、これがグローバルファンドの設立につながった。その後も日本がG7(G8)及びG20議長国の際は、国際保健外交をサミットの柱として取り上げてきた。日本が外交理念の1つとして人間の安全保障を推進するなかで、その中核かつ基礎が保健であり、これがなければ経済発展も立ちゆかなくなるといった考えから、国際保健外交の強化に一貫して取り組んでいる。最近ではグローバルヘルス技術振興基金(GHIT Fund: Global Health Innovative Technology Fund)など国際的に多くの機関や官民連携基金などが立ち上がり、国際保健が主流化されている。
そのような取組の中で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な感染拡大(パンデミック)をきっかけとして国際社会の中で、いわゆる「パンデミック条約」と国際保健規則(IHR: International Health Regulations)の改正の議論が進められている。「パンデミック条約」の条約案は現在交渉中であり、その正式名称も確定していないため、この場では仮称として一般的に使用されている「パンデミック条約」を用いながら、日本政府の取組について概要をお伝えする。この「パンデミック条約」とIHRの改正は、外務省と厚生労働省の二人三脚で、他の関係省庁とともに日本政府代表団が一丸となって臨んでいる交渉である。
日本の基本方針と貢献
日本は2022年5月に国際保健に関する基本方針として、グローバルヘルス戦略を策定した。グローバルヘルスは人々の健康に直接関わるのみならず、経済・社会・安全保障上の大きなリスクを包含する国際社会の重要課題であり、人間の安全保障の観点からも重視すべきであり、人類と地球との共存という視座からも考える必要のある地球規模課題である。国際保健に世界的に貢献していくことによって、良好な国際環境が醸成され、国益にもつながると考えている。特に感染症は、気候変動とともに国境を越えた課題であり、地球規模課題の典型例である。
グローバルヘルス戦略の政策目標の一つは、健康安全保障に資するグローバルヘルス・アーキテクチャー(GHA: Global Health Architecture)の構築への貢献であり、パンデミックの予防、備え及び対応(PPR: Prevention, Preparedness, Response)の強化である。グローバルヘルス戦略の中では、国際規範の強化に貢献することが明記されており、「パンデミック条約」作成への取組はまさにその一部を成している。
グローバルヘル戦略のもう一つの政策目標として、より強靭より衡平より持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC: Universal Health Coverage)の達成に向けた保健システムの強化を実現することがあり、政策面・理念面・実践面で、国際協力機構(JICA: Japan International Cooperation Agency)や国際機関を通じて実践していくことを目指している。
UHC達成に向けた様々な取組やCOVID-19対策を含めた日本の支援が役立ち、諸外国からは多くの謝意をいただいている。日本の国際保健外交にとって1つの山場となったのが、2023年のG7広島サミットおよび長崎保健大臣会合であり、集中して取り組んだ。その成果として、1. グローバルヘルス・アーキテクチャー(GHA)、2. ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)、そして3. 研究開発(R&D)をG7広島首脳コミュニケにおける保健分野の3つの柱として整理し、日本が議長国として取組をまとめた。
さらに、2023年9月に開催された国連総会のハイレベルウィークには140カ国の首脳がニューヨークに集結し、国際的なコンセンサスの醸成がなされた。特に、9月20日には「パンデミックの予防・備え・対応(PPR: Prevention, Preparedness and Response)」、21日には「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC: Universal Health Coverage)」、そして22日には「結核(Tuberculosis)」の3つの保健分野に関わるハイレベル会合(HLM: High Level Meeting)が行われた。また、これまでの日本の国際保健分野での取組やG7サミットにおけるリーダーシップなどが評価され、岸田総理はビル&メリンダ・ゲイツ財団が主催する「2023年グローバル・ゴールキーパー賞」を受賞した。
国際保健規則(IHR)の改正と「パンデミック条約」の背景
世界保健機関(WHO: World Health Organization)には、国際交通及び取引に対する不要な阻害を回避し、疾病の国際的拡大を防止、防護、管理することを目的とした国際保健規則(IHR: International Health Regulations)がある。このIHR では、空港、港湾及び陸上越境地点における日常の衛生管理や緊急事態発生時の対応等に関して各国が整備すべき基本的能力が規定されている。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の経験を経て、WHO加盟国の間で2005年に改正されたIHR (2005)をより良くするために、再び改正する動きが生じ、国際的に合意可能な改善点や課題について議論が行われている。
それとは異なる動きとして、このIHR改正だけでは不十分であるといった声が上がり、2020年11月のG20リヤド・サミットで、ミシェル欧州理事会議長が、パンデミックに関する国際的な条約作成の必要性に初めて言及し、2021年1月のWHOの執行理事会ではCOVID-19の状況を念頭に、IHR(2005)を補完する形で将来のパンデミックを予防し、国際的な協力の下でより迅速に対応できるよう法的拘束力を伴う条約の作成が提案された。2021年5月に開催されたWHO総会ではWHO強化作業部会を設置し、パンデミックのPPRに関する条約、協定又はその他の文書を検討し、同年の11月末にWHO特別総会を開催して議論を行うことを決定した。そのWHO特別総会では主に以下の点が決定された
- 2022年3月1日までに政府間交渉会議(INB: Intergovernmental Negotiating Body)の初回会合を開催する
- INBは新規国際文書の要素を検討し、新規国際文書の形式(条約、協定、規則、その他)を決定する
- INBは、新規国際文書とIHRの間に重複や矛盾がないよう、WHO強化作業部会と連携する
- INBは、第76回総会(2023年5月)に進捗状況を報告し、第77回WHO総会(2024年5月)に成果物を提出する
- 加盟国は、部分改正を含めたIHRの強化の議論を継続する
2022年に開催された第1回政府間交渉会議では、交渉の立ち上げや方法、形式等についての議論が行われ、内容に関する実質的な議論は第3回目頃から開始された。現在、第7回再開会合まで行われており、2024年2月に第8回、3月に第9回政府間交渉会議が予定され、成果物を出す期限が2024年5月となっている(2024年1月現在)。
(編集者追記:2024年6月1日には第77回WHO総会において、IHR(2005)の改正がコンセンサスで採択され、「パンデミック条約」の交渉延長が決定されました。)
今後の見通し
交渉の成果物の提出期限である2024年5月まで約4か月となった現在、良いものを作りたい、良いものを作るにはもう少し時間が必要だと考え始めている国も出始めている。多様な声があるが、G7での連携や新興国との議論を経て、いつまでにどういうものをまとめるのか、何があれば成功なのか、何が必須なのかという議論を今後進める必要があり、日本としても建設的に議論に貢献していきたいと考えている。なお、現在交渉に使用されている、第1章(序論)第3条の一般原則及びアプローチの内容に「主権」という言葉が入っている。条約の議論を進める上で各国の主権は重要であり、これには各国政府から異論は出ていない。
先行きが見えづらい現状ではあるが、現在どういう状況で日本の外交交渉団が、日本の国益、または次のパンデミックの備えになるかという観点から真剣に交渉に参加しているということをご紹介した。
講演後の会場との質疑応答では、条約としてのあり方や、グローバルヘルス戦略などについて、活発な意見交換が行われました。
(写真:井澤 一憲)
■プロフィール
赤堀 毅(外務省 地球規模課題審議官)
1966年8月25日生まれ。東京大学法学部第二類卒業後、1989年に外務省入省。1991年フランス国立行政学院卒業(国際行政修士)。フランス国立東洋言語文化学院国際関係修士コースを中断し、在フランス大使館勤務。1994年に帰国後、南東アジア第一課課長補佐、国連政策課課長補佐、大臣官房総務課総括課長補佐、条約局法規課首席事務官、北米局北米第一課首席事務官。2004年から在アメリカ合衆国日本国大使館参事官(経済部→政務部)。2007年に帰国後、アジア大洋州局北東アジア課日韓経済室長兼朝鮮半島政策調整官(日韓EPA交渉、六者会合経済エネルギー作業部会代表代理、KEDO代表代理等担当)、大臣官房広報文化交流部文化交流課長。2011年から外務大臣秘書官。2012年12月から国際法局条約課長。九州大学及び国際大学で講師(国際法実務)。2015年9月から国際連合日本政府代表部政務公使(2016年から2年間の日本の安保理任期中、ポリティカル・コーディネーターを務める。)。2018年7月から大臣官房参事官兼G20サミット事務局長(大使)。2019年7月から総合外交政策局参事官兼サイバー政策担当大使。2020年8月から総合外交政策局審議官兼国連・サイバー政策担当大使。2019年から2021年まで開催されたサイバーセキュリティに関する第六次国連政府専門家グループ(GGE)の構成員25名の1人。2021年8月から国際協力局審議官(地球規模課題担当)兼気候変動交渉担当大使。2022年1月から地球規模課題審議官(大使)。同年6月からGaviワクチンアライアンス理事。
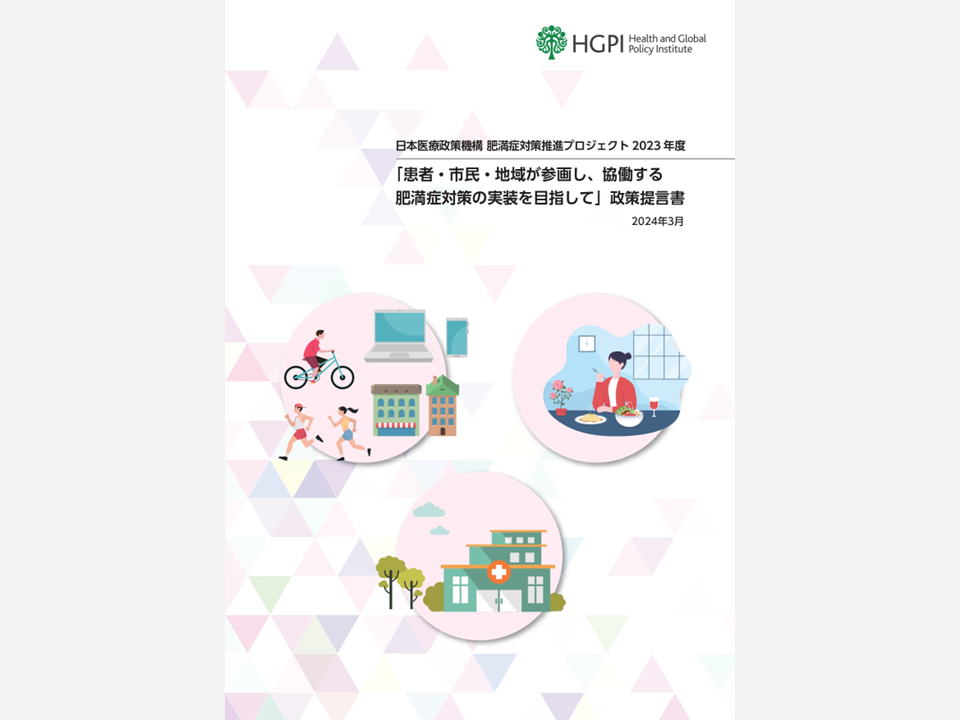
当機構では、2022年より肥満症や肥満に関する社会全体の関心を引き上げ、効果的な対策を推進すべく「肥満症対策推進プロジェクト」を始動させています。
2023年度は、2022年度の提言内容の深堀および実装を目指し、肥満症当事者・医療関係者へのヒアリングおよび産官学民の有識者で構成されるアドバイザリーボード会合を開催しました。医療現場ならびに社会における肥満症当事者を取り巻く実態、課題の把握を踏まえて、当事者の視点に基づく社会、医療において求められる肥満症対策について、以下に提言します。
※本提言書は、3月4日に公表した提言概要【速報版】から更新された、提言本体【確定版】になります。
肥満症対策に求められる6つの提言(概要)
- 提言1:行政機関と産業界が連携し、健康的な生活習慣に関する教育と健康リスクの少ない社会づくりを両輪として、肥満症を含めた生活習慣病の一次予防を強化すべき
- 提言2:特定健康診査・特定保健指導におけるデータヘルスの推進と実効性の強化を通じた、疾病予防効果の高い二次予防政策を実現するべき
- 提言3:肥満および肥満症の患者へ適切な介入を行うべく、地域において産官学民が連携の上、肥満症当事者の課題やニーズに寄り添った医療提供体制および支援体制を構築すべき
- 提言4:高度肥満症の患者に集学的治療が行われるよう医療提供体制の整備と全国均てん化を推進すべき
- 提言5:肥満症政策推進および医療提供体制の充実・均てん化のために、肥満症を含む慢性疾患対策への効果に関するエビデンスを創出すべき
- 提言6:偏ったボディイメージを是とする風潮や、肥満への自己責任論から脱却するとともに、医学的な病態としての肥満や肥満症に関する理解を醸成し、適時適切な医療の妨げとなるスティグマを解消すべき
詳細については下部PDFをご覧ください。
■ヒアリングにご協力いただいた自治体、専門家及び当事者(敬称略・県と市・専門家・当事者ごとに五十音順)
佐賀県 健康福祉部 健康福祉政策課
福島県 教育庁 健康教育課
宮城県 保健福祉部 健康推進課
北海道釧路市 こども保健部 健康推進課
肥満症当事者4名
■「肥満症対策推進プロジェクト」アドバイザリーボードメンバー(敬称略・五十音順・ご所属・肩書はご参画当時)
今岡 丈士(日本イーライリリー株式会社 研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部 糖尿病領域兼臨床薬理メディカルアソシエイトバイスプレジデント・メディカル)
岡村 智教(慶應義塾大学 医学部衛生学公衆衛生学教室教授)
小熊 祐子(慶應義塾大学スポーツ医学研究センター・大学院 健康マネジメント研究科 准教授)
加隈 哲也(大分大学 医学部看護学科基盤看護学講座 健康科学領域 教授)
黒瀨 巌(日本医師会 常任理事)
齋木 厚人(東邦大学医学部 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌学分野 教授)
新垣 友隆(日本イーライリリー株式会社 研究開発・メディカルアフェアーズ統括本部 糖尿病領域 シニアアドバイザー)
杉井 寛(ノボノルディスクファーマ株式会社 取締役副社長 開発本部長)
辻 沙耶佳(東邦大学医療センター佐倉病院 肥満症治療コーディネーター)
龍野 一郎(日本肥満症治療学会 理事長/千葉県立保健医療大学 学長)
横手 幸太郎(日本肥満学会 理事長/千葉大学医学部附属病院 病院長)
■協賛企業・団体(五十音順)
国立大学法人 政策研究大学院大学 グローバルヘルス イノベーション政策プログラム
日本イーライリリー株式会社
ノボノルディスクファーマ株式会社





















