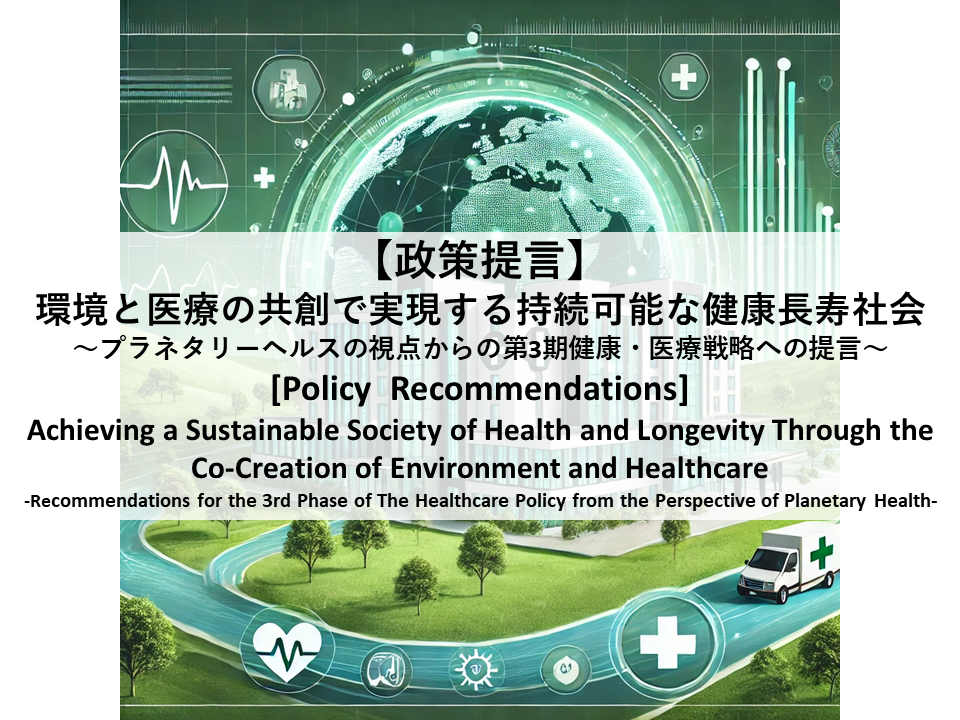
日本医療政策機構プラネタリーヘルスプロジェクトは、「環境と医療の融合で実現する持続可能な健康長寿社会~プラネタリーヘルスの視点を取り入れた第3期健康・医療戦略への提言~」を公表しました。
日本政府が推進する「健康・医療戦略」は、国民の健康寿命の延伸を目指し、医療研究開発や新産業の創出を通じて社会と経済の持続可能な発展を省庁横断的に図る重要な政策です。第3期においては、気候変動や環境汚染、生物多様性の喪失といった地球規模の課題が、人々の健康に直接的かつ深刻な影響を与えることが明らかになっています。これらの課題に取り組むためには、従来の保健医療の枠を超え、環境と健康を一体的に捉える「プラネタリーヘルス」の視点を政策に統合する必要があります。
さらに、2024年11月に開催されたグローバルヘルス戦略推進協議会においても、「気候変動と健康」の重要性が省庁横断的な取り組みとして強調されており、具体的な取り組みとしては、経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも明記され、厚生労働省が推進している「気候変動と健康に関する変革的行動のためのアライアンス(ATACH)」、経済産業省による環境インフラや脱炭素・環境負荷低減技術の海外展開促進に向けた支援、そして環境省による気候変動による健康リスク評価システム(Adaptwell)などが示されています。
この政策提言では、健康・医療戦略が2040年頃までを視野に入れる中で、気候変動が与える健康影響への対応、環境負荷の軽減、そして持続可能な健康長寿社会の実現を目指した具体的な提案を提示します。
■ポイント:
1.気候変動が健康に与える影響への対応
- 気候脆弱性評価とリスク地域の特定
- 異常気象や大気汚染による健康リスクを軽減する早期警戒システムの導入
2.持続可能な保健医療システムの構築
- 医療DXや遠隔診療の推進による温室効果ガス削減
- 医療廃棄物削減や再製造技術の普及
3.医療分野における脱炭素化と環境配慮型製品の推進
- 医療施設のエネルギー効率向上や再生可能エネルギーの導入
- 環境負荷を考慮した治療法や医薬品の研究開発
4.国際的なリーダーシップの発揮
- ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を基盤にした「グリーナーUHC」の実現
- 環境・健康の統合的課題への国際的なルール形成への貢献
プラネタリーヘルスの視点を取り入れることは、持続可能な健康長寿社会の実現に向けた重要な鍵です。第3期健康・医療戦略では、地球環境と人間の健康が密接に関連しているという認識のもと、環境保全と健康増進を同時に達成する施策を推進することが求められます。
当機構は、気候変動と健康の課題解決に向けた具体的な政策提言を通じ、日本が環境・医療分野での国際的リーダーシップを発揮することを期待します。
詳細は、ページ下部のPDF資料をご覧ください。

日本医療政策機構(HGPI)では2022年度より腎疾患対策推進プロジェクトを始動し、慢性腎臓病(CKD)の予防や早期介入の必要性、多職種や多機関連携の重要性、自治体の好事例の横展開の必要性、患者・当事者視点に基づいた腎疾患対策の推進の必要性などを提言してきました。
CKDは労働世代においても無縁ではない疾患です。労働世代の中にも CKDのある人、ハイリスクな人、人工透析を受ける人は決して少なくないことから、現状の腎疾患対策の課題を正確に理解した上で、労働世代に求められる現実的なCKD対策やその範囲を検討していく必要があると認識しています。
この度当機構では、労働世代におけるCKD対策の強化に向けて、産官学民の有識者の皆様へのヒアリングとこれまでの議論を今回調査し、提言として取りまとめました。
詳細は末尾のPDFファイルをご覧ください。

<POINTS>
- 2015年に採択されたパリ協定以降、日本を含めた世界各国では「2050年カーボンニュートラル」に向け大胆な取組みが行われている
- その潮流の中で、世界中のビジネスや金融市場は気候変動への対応とそれに合わせたビジネスモデルや戦略の変革を求められている
- 製薬業界では、日本製薬団体連合会を代表とし、各企業におけるカーボンニュートラルの達成に向けた目標設定と取組みが行われている
はじめに
2015年に開催された第21回 国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定を契機に、世界の120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げ、大胆な取組みを行っています。その潮流の中で、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures)の設置をはじめ、世界中のビジネスや金融市場は大きく変容を遂げようとしています。企業における気候変動への対応は、「企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)」によるものから企業が投資や融資を受けるにあたって重要な情報となり、事業活動をおこなう上での“リスク”あるいは“チャンス”と変化してきています。
日本も例外ではなく、2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガス(GHG: Greenhouse Gas)の排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。その後「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(経済産業省)が策定され、取組みを後押しするための規制改革や金融制度を設置するなど、企業はこれまでのビジネスモデルや戦略の変革を求められています。
特に、気候変動が人間の健康に直接的・間接的に悪影響を与える中で、健康を保持・増進させる機能を持つヘルスケアセクターにおいては、その役割および義務として、企業の取組み全体の脱炭素化・環境負荷への配慮が重要です。
今回のコラムでは、ヘルスケアシステムの中でも約50%のGHG排出量を占める製品とサプライチェーンに焦点を当て、日本の製薬業界におけるカーボンニュートラルの取組みについて、好事例も含めてご紹介します。
日本の製薬業界のカーボンニュートラル実現への取組み
15団体319企業を傘下におき、医薬品工業の健全なる発達を目的とした業界団体の連合会である日本製薬団体連合会(日薬連)では、環境委員会を設置し、加盟団体と共に製薬産業界全体の環境対策のため情報共有および方針の検討を行っています。同委員会は取組みの一つとして、カーボンニュートラル行動計画ワーキンググループを設置しています。このワーキンググループでは日本経済団体連合会(経団連)が策定する「低炭素社会実行計画」に2010年より参画し、カーボンニュートラルを達成するための目標設定と取組みを行っています。
2050年カーボンニュートラルに向けた医薬品業界のビジョン(基本方針等)
|
将来像・目指す姿 |
|
2050年までの温室効果ガスの排出量を全体としてゼロとする |
|
1. 国内の事業活動における2030年の目標等 |
目標・行動計画 |
2013年度を基準に、2030年度のCO2排出量を46%削減する |
|
対象とする事業領域 |
工場、研究所、オフィス、営業車両から排出されるエネルギー起源のCO2 |
|
|
取組み方針 |
|
|
|
2. 主体間連携の強化 |
概要・削減貢献量 |
|
|
3. 国際貢献の推進 |
概要・削減貢献量 |
|
|
4. 2050年カーボンニュートラルに向けた革新的技術の開発 |
概要・削減貢献量 |
|
※引用:日本経済団体連合会, 経団連カーボンニュートラル行動計画2023年度フォローアップ結果 個別業種編. 2024. https://www.keidanren.or.jp/policy/2023/072_kobetsu13.pdf. (参照日2024年10月16日).
製薬業界における取組み事例
1. 国内の事業活動における2030年の目標等
各企業では、CO2排出量の推移と、目標達成の蓋然性や進捗率などを分析し報告しています。各企業におけるCO2排出削減の取組みの一つとして、オフィスや自社工場等における省エネルギー設備・基準の採用、再生可能エネルギー(再エネ)の導入、製品製造の効率化などにより、エネルギー起源のCO2削減および炭素効率化等に取り組んでいます。また一部では、直接的な排出削減以外の取組みとして、J-クレジット制度、非化石証書、グリーン電力証書といった環境価値証書の活用によるカーボンオフセットの取組みも進められています。例えば、J-クレジット制度は、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度です。企業は、このクレジットを購入することで、自社では削減困難なGHG排出量を相殺することができます。更に、「環境に配慮した取組み」を行っていることを社会に明示することが可能です。
アストラゼネカ株式会社
2022年4月より滋賀県米原工場における太陽光発電設備の導入及び稼働を開始した。本工場における使用電力量の約20%を自家発電により供給し、エネルギー起源CO2排出量の低減に取り組んでいる。また、残り約80%に相当する電力を、固定価格買取制度(FIT: Feed-in Tariff)ではない再エネ電気を調達した、実質再生可能エネルギー電気の利用に切り替えたことで、年間約2,800tのCO2の削減を見込んでいる。J-クレジット制度を活用することで、日本における事業所の再生可能エネルギー100%を達成した。
富士製薬工業株式会社
2021年に製品生産効率の向上を目的として製剤棟を増設したことにより、約10%の炭素生産性の向上が見込まれる。2023年より再エネ電力の直接購入、J-クレジットの活用、または非化石証書の購入によるカーボンオフセットを検討中である。本申請では、J-クレジットの購入で10t-CO2の削減を予定している。これらにより、事業所単位の炭素生産性を10%向上させることを見込んでいる。
2. 主体間連携の強化
社会全体のGHG排出量を削減するためには、自らの事業における排出削減だけではなく、消費者、顧客企業、地域住民、政府・自治体、教育機関等の様々な主体と連携した排出削減の取組みが必要です。製薬業界では、低炭素製品の技術開発や共同配送等の効率的な医薬品輸送に努めることで、製品のライフサイクルを通じた社会全体のGHG排出削減に貢献しています。さらに、営業車両への低燃費車導入や都市部における公共交通機関の利用を促進することによって、自社のCO2排出削減にコミットするだけでなく、取組みやその他の教育等を通じて、社員の気候変動問題に関する意識や知識の向上にも取り組んでいます。
3. 国際貢献の推進
グローバル課題である気候変動に対処するためには、わが国の優れた技術や製品・サービス等の提供により、グローバルに広がるバリューチェーンを意識した排出削減に取組むことが必要です。武田薬品工業株式会社、第一三共株式会社、アステラス製薬株式会社など一部の製薬企業では、パリ協定が求める水準と整合し、パリ協定に整合的な削減目標を設定するイニシアティブである科学に基づく目標設定(SBT: Science Based Targets)を採用しています。国際基準であるSBTの認証により、企業は世界と一体になったGHG排出削減へのコミットメントが求められます。
4. 2050年カーボンニュートラルに向けた革新的技術の開発
各業界はCO2削減を加速させていくために、従来の取組みだけでなく、全く新たなイノベーションの創出にも着手しています。製薬業界においても、例えば、アメリカ化学会(ACS: American Chemical Society)によるACSグリーンケミストリー研究所(GCI: Green Chemistry Institute)は、2005年に製薬業界における環境と人体にやさしい化学を目指す「グリーンケミストリー」と「エンジニアリング」の統合を促進することを目的に、ACS GCI 製薬ラウンドテーブル(ACS GCI Pharmaceutical Roundtable)を結成しました。このラウンドテーブルには、アストラゼネカ、バイエル、イーライリリー、グラクソ・スミスクライン、メルク、ノバルティス、ファイザー、ノボノルディスクなどの企業が参加しており、廃棄物の少ない化学合成プロセスの設計や、安全性の高い化学物質の開発などに取り組んでいます。その他、製薬業界では、薬品の製造プロセスを従来のバッチ生産(個別生産)から連続生産(一つの製造プロセスで多種生産)に切り替えることで生産性を向上させることや長期徐放製剤の開発を進めていくことで人体への負担を軽減するだけでなく輸送・移動段階でのCO2削減にも貢献しています。
まとめ
以上、製薬業界におけるカーボンニュートラル実現への取組みについて事例を交えてお伝えしました。各企業の取組み内容や状況は、企業規模や業種によっても異なります。ビジネスや金融市場の変革が企業のカーボンニュートラル実現への取組み推進の鍵を握ることは間違いありませんが、特にヘルスケアセクターにおいては、保健医療システムの一員であるという自覚と責任感こそ、その役割や義務を果たしていくためには欠かせません。より多くの企業がその自覚と責任感をもって精力的な取組みを展開していくことを期待します。
【参考文献】
1. 経済産業省. 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略. https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/index.html. (閲覧日2024年10月15日)
2. 経済産業省. 企業の環境活動を金融を通じてうながす新たな取組み「TCFD」とは?. https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/tcfd.html. (閲覧日2024年10月15日)
3. 日本経済団体連合会, 2030年に向けた経団連低炭素社会実行計画(フェーズⅡ), https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/031.html. (閲覧日2024年10月15日)
4. 日本経済団体連合会, 経団連カーボンニュートラル行動計画2023年度フォローアップ結果 個別業種編. 2024. https://www.keidanren.or.jp/policy/2023/072_kobetsu13.pdf.(参照日2024年10月16日)
【執筆者のご紹介】
松本 こずえ(日本医療政策機構 プログラムスペシャリスト)
島袋 彰(日本医療政策機構 アドジャンクトフェロー)
ケイヒル・エリ(日本医療政策機構 プログラムスペシャリスト)
菅原 丈二(日本医療政策機構 副事務局長)
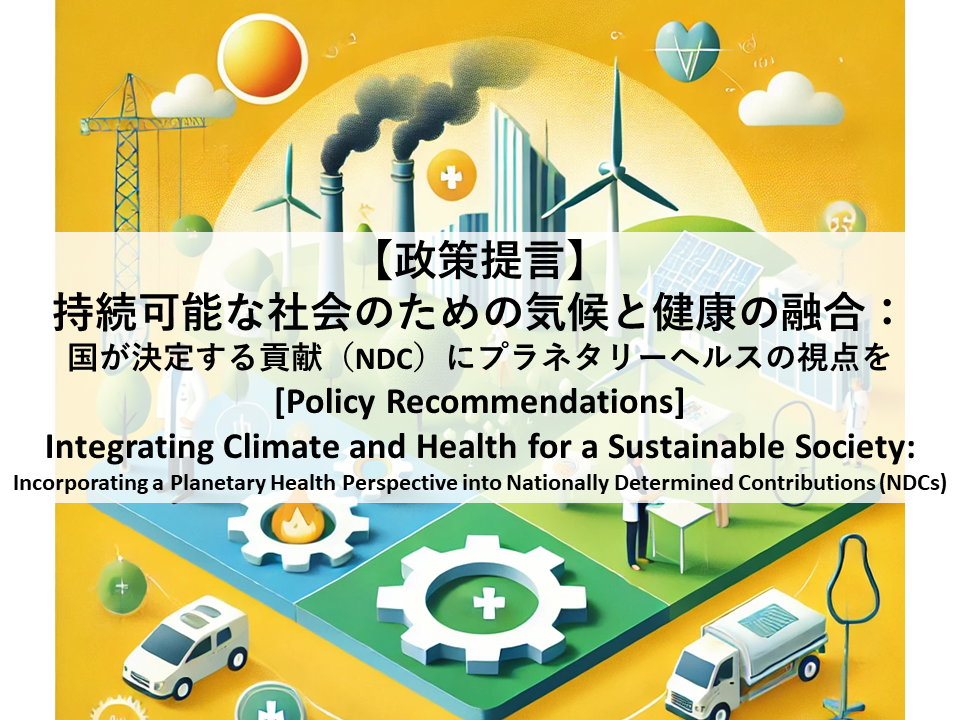
日本医療政策機構プラネタリーヘルスプロジェクトは、「持続可能な社会のための気候と健康の融合:国が決定する貢献(NDC)にプラネタリーヘルスの視点を」を公表しました。
国が決定する貢献(NDC: Nationally Determined Contributions)は、パリ協定に基づいて温室効果ガス(GHG: Green House Gases)の削減目標を設定するものであり、日本のエネルギー戦略や成長戦略にも大きな影響を与えます。パリ協定では、2025年に2035年以降の数値目標に関するNDCを各国が提出することを求めており、現在、日本でも、この見直しに向けた動きが始まっています。
近年ではNDCに健康の視点を盛り込む国が増えており、2022年には91%(193カ国中175カ国)に健康への配慮が盛り込まれるようになりました。加えて、アジア地域やG7諸国の一部のNDC(21カ国 全体の11%)においては、健康を守るという側面から保健医療セクターに特化したGHG排出削減と適応策についても項目として盛り込まれています。そして、国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)に向けて、世界保健機関(WHO: World Health Organization)は「COP29特別報告書:気候変動と健康(COP29 Special Report on Climate Change and Health)」および「各国自主貢献(NDCs)に健康を統合するための品質基準(Quality criteria for integrating health into Nationally Determined Contributions (NDCs))」を発表し、各国が健康を気候変動政策の中心に据える必要性を強調しています。この指針は、NDCに健康目標を統合することで、気候変動が健康に与える悪影響を緩和し、持続可能な未来の実現を目指しています。しかし、日本のNDCには、依然として健康に関する言及が含まれていません。
気候変動が与える人々の健康への影響の重大性からも、ドイツ、イギリス、アメリカなどの長期低排出発展戦略(LT-LEDS)では、国民の健康とウェルビーイングを最大化する観点で、長期的な気候目標が優先されており、日本においても、より国民の健康に重点をおいた国の戦略を立てていく必要があります。
そこで、日本医療政策機構は、2025年のNDC提出に向けて、健康の視点が反映されるよう、以下の5つの提言を行います。
要望1:気候変動対策が必要な背景として、気候変動が健康に及ぼす広範な影響について記載すること
要望2:気候変動が健康に与える影響を考慮した、緩和策について記載を行うこと
要望3:緩和と適応を両輪で進めるコベネフィットの促進について記載を行うこと
要望4:保健医療分野の緩和策推進について記載を行うこと
要望5:適応策の一つとして、気候変動に強靭な保健医療制度の構築について記載を行うこと
詳細は、ページ下部のPDF資料をご覧ください。

2015年に提唱された「プラネタリーヘルス」の概念は、人間の健康と地球の健康は表裏一体であることを示しており、人間と地球双方の健康が持続可能である最適な状態を探求していくことが求められています。地球規模で生じている気候変動、環境汚染および生物多様性の喪失は、すでに人々の生活や健康、そして社会に影響を及ぼすようになっており、世界規模の緊急事態にそれぞれの地域において対処するための調査研究およびそれに基づいた行動が必要です。
子どもの健康と環境に関する全国調査(通称:エコチル調査)は、2010年度から環境省が実施している10万組の家族が参加している大規模な疫学調査です。特に環境中の化学物質に焦点を当て、その影響についての調査を行っています。国立環境研究所のエコチル調査コアセンターが事務局を務めており、全国15地域の大学・医療機関に設置されたユニットセンター、医学的側面の支援を行う国立成育医療研究センターに設置されたメディカルサポートセンターと共に調査を進めています。2022年度には、追跡調査を行う期間を40歳程度になるまで調査を継続して進めていく方針が打ち出されるなど、より長期的に環境中の化学物質と人の健康の関連を調査する方針となっています。すでに480編以上の英文原著論文がエコチル調査から発表されており、世界的にも評価が高い大規模な出生コホート研究となっています。
このように、エコチル調査は地球環境と人の健康について理解する上で、重要な役割を担っておりますが、今後私たちが「プラネタリーヘルス」の視点に立ち、人間の健康と地球の健康について理解し、対策を講じていくためには、さらに広い視点での調査研究とそれに基づく対策が必要となります。
今回のHGPIセミナーでは、国立環境研究所 エコチル調査コアセンター センター長の山崎新氏をお招きし、エコチル調査のこれまでの取組と、今後の期待についてお話しいただきます。世界でも有数の大規模疫学調査のご経験から、プラネタリーヘルスの視点において、今後どのような取組が必要かについてご示唆をいただければと思います。
【開催概要】
- 登壇者:
山崎 新 氏(国立環境研究所 エコチル調査コアセンター センター長)
- 日時:2024年12月23日(月) 18:30-19:45
- 形式:オンライン(Zoomウェビナー)
- 言語:日本語
- 参加費:無料
- 定員:500名
■登壇者プロフィール
山崎 新 氏(国立環境研究所 エコチル調査コアセンター センター長)
2006年京都大学大学院医学研究科博士後期課程を修了。2007年より京都大学大学院医学研究科准教授に就任。2015年国立環境研究所環境疫学研究室長、2017年同研究所環境リスク健康研究センター副センター長、2019年同研究所エコチル調査コアセンター長を歴任し、現在に至る。
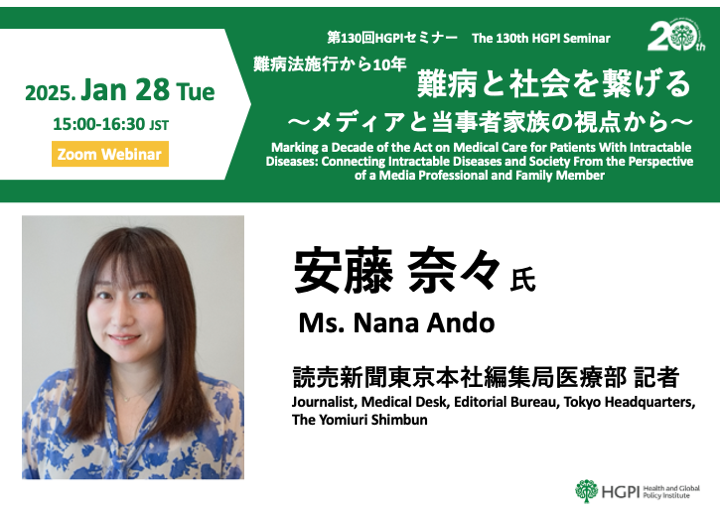
日本医療政策機構(HGPI)では、2024年度より難病・希少疾患プロジェクトを始動いたしました。2024年5月23日「難病の日」には、シンポジウム「患者・市民の視点から考えるこれからの難病対策」を開催し、これからの難病対策のあり方についてマルチステークホルダーによる議論を行い、報告書を公表いたしました。
難病は数多ある医療政策の課題の中でも、特に重要な課題の1つです。希少疾患と合わせて議論されることが多いですが、特に難病の場合はその発生機序が明らかでない事が多く、明確な治療法が確立されてない、また長期の療養が必要になるなど、患者の心身の負担が大きくなるとされています。日本では、指定難病とされる疾患は今日現在341に上り、患者数は100万人を超えるとされています。
2014 年には「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が制定され、医療の推進をはじめ、社会環境の整備も含めた方向性を打ち出しています。一方で、依然として難病対策の課題も様々な指摘がなされています。当機構が2024年5月23日に開催した「難病の日」のシンポジウムにおいても、これからの難病対策として指定難病のあり方、社会への情報発信、早期診断を促進するための体制整備を含めて「診断ラグ」の解消を目指すことの重要性と、政策形成過程における患者・市民の参画に基づくアプローチの重要性が示唆されました。さらには、治療のみならず患者とその家族を含めた生活面にも注目した議論を展開することも期待されています。
本セミナーでは、読売新聞東京本社編集局医療部 記者の安藤奈々氏をお迎えし、難病を取り巻く現状やこれまでの取材を通して考えるメディアの役割、さらには今後の難病政策に求められることなど、医療記者と当事者家族の視点から幅広くお話いただきます。
【開催概要】
- 登壇者:
安藤 奈々氏(読売新聞東京本社編集局医療部 記者) - 日時:2025年1月28日(火)15:00-16:30
- 形式:オンライン(ZOOMウェビナー)
- 言語:日本語
- 参加費:無料
- 定員:500名
■登壇者プロフィール
安藤 奈々氏(読売新聞東京本社編集局医療部 記者)
中央大学法学部卒。2010年、読売新聞東京本社に入社。長野支局、経済部などを経て、2017年から医療部で医療取材に携わる。現在は主に小児医療、生殖医療を担当。
妹が指定難病の「レット症候群」で、難病の患者さんや家族にとって確かな情報を広く発信したいと医療記者を志した。難病における新たな診断・治療法の研究や、当事者を取り巻く生活環境の課題などをテーマに取材を続けている。




