
2018年05月08日
当機構が行った「2017年 日本の医療に関する世論調査」結果が、DIAMOND onlineの記事「受動喫煙規制は「前時代的な利害調整」との戦いだ」に引用されました。
記事はこちらに掲載されています。

2018年04月21日
プレ会合:
医療システムの持続可能性とイノベーションの両立 シリーズ
~試行的導入から見えてきた費用対効果評価導入への課題~
イノベーションと持続可能な保健医療を実現するための、効率的・効果的な医療制度の構築は、日本のみならず世界共通の課題です。医療を適切に評価するための取り組みが各国でなされており、例えば、医療技術評価(HTA: Health Technology Assessment)によって、医療資源の適切な配分が可能になると期待する声もあります。わが国でも、中央社会保険医療協議会(中医協) 費用対効果評価専門部会で、2012年度から議論が重ねられるなど、HTA導入に向けて議論が重ねられてきました。2017年度には、費用対効果評価の試行的導入が実施され、2018年度も、今後の本格的導入に向けて、引き続き検討が重ねられる予定となっています。
日時:2018年5月31日(木)18:30-20:30(開場:18:00)
会場:Global Business Hub Tokyoフィールド・スペース(当機構 オフィス)
(東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ3階)
主催:特定非営利活動法人 日本医療政策機構(HGPI: Health and Global Policy Institute)
専門家:国内外を代表する有識者約20名によるラウンドテーブル・ディスカッション
参加予定者:政策立案者、関連省庁関係者、学識関係者、企業関係者など (招待制/40名程度)
※本会合は日本語で実施され、同時通訳はございません。
プログラム:*
18:30-18:40 開会(趣旨説明)
18:40-19:30 ラウンドテーブル登壇者による冒頭発言
19:30-20:30 2018年連続フォーラムで議論すべきテーマやアジェンダについての議論
(例)
- 保健医療システム全体を見据えた評価結果の総合的な評価・反映
- 費用対効果評価を実施する人材の不足(産官学民、すべてのステークホルダーにおいて)
- 企業・再分析班などのステークホルダー間でのコミュニケーション
- 医療に求められる価値や他の政策との整合性
- 医薬品や医療機器などの分析方法と合理性 など
20:30 閉会
*プログラム内容は都合により変更する場合がございます


2018年04月17日

2018年04月16日
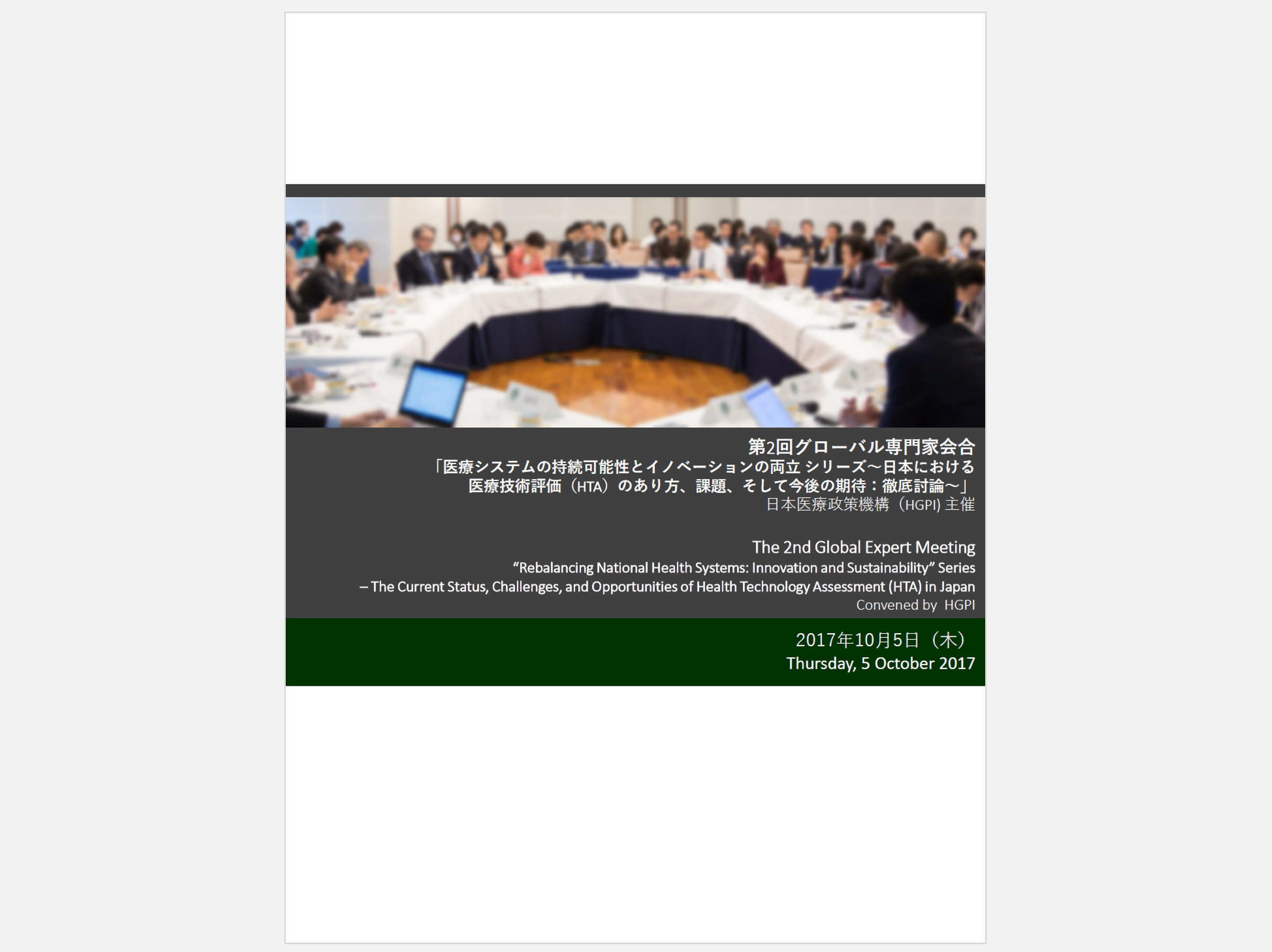
2018年04月12日
*****最終報告書を作成し、発表しました。 (2018年4月10日)
詳しくは、当ページのPDFファイルをご覧ください。
2017年10月5日(木)、日本医療政策機構は、第2回グローバル専門家会合「医療システムの持続可能性とイノベーションの両立 シリーズ~日本における医療技術評価(HTA)のあり方、課題、そして今後の期待:徹底討論~」を開催しました。
2017年4月に日本医療政策機構(HGPI)は、グローバル専門家会合「医療システムにおけるイノベーションと持続可能性の両立に向けて」を米国戦略国際問題研究所(CSIS: Center for Strategic and International Studies)と共催で開催しました。4月会合では、イノベーションを推進しながら、公平なアクセスを確保し、質の高い医療の提供を担保する一方で、コストを抑えるという難題は、日本独自の課題ではなく、世界共通の課題であることが確認されました。また、医療技術や機器・薬剤の価値を適切に評価するために、財政的な負担と公衆衛生上の利点の双方を指標とし、マルチステークホルダーによる意思決定プロセスにおける国民の参画の重要性が指摘されました。
4月会合を受け、今回、第2回グローバル専門家会合となる「医療システムの持続可能性とイノベーションの両立 シリーズ~日本における医療技術評価(HTA)のあり方、課題、そして今後の期待:徹底討論~」を開催いたしました。国内外の産官学民を代表する20名の有識者が一同に会し、チャタムハウスルールによるラウンドテーブルという形式で議論がなされました。


慢性疾患の増加による疾病構造の変化や高齢化、医療機器・医薬品の発展による医療費の急速な高額化により、医療保険制度の持続可能性とイノベーションの両立は世界各国の喫緊の課題となっています。我が国でも、限られた医療保険財源で高い保健医療水準を担保し、国民皆保険制度を維持することは重要な課題となっています。解決策の一つとし、厚生労働省は、2018年度からの医療技術評価(HTA: Health Technology Assessment)の制度化を進めています。中央社会保険医協議会(中医協)などにおいて、その骨組みをとりまとめている段階であるなか、フラットかつマルチステークホルダーによる議論が行われました。
今後検討すべき総合的な論点(専門家会合まとめ)
総合的な視点 1:
医療技術評価(HTA: Health Technology Assessment)は医療費抑制のツールではなく、国民や患者のために医療技術を正当に評価する手法であることを、ステークホルダーが再認識する必要性
- 中央社会保険医療協議会(中医協)の議論をはじめ、医療費抑制のための費用対効果という議論になってしまう場合があるが、HTAは本質的に国民や患者の利益に寄与することができるという視点を再認識すべきである。
総合的な視点 2:
導入段階として、医療機器と医薬品についてのHTA議論が本格化しているが、医療技術全般についてのHTA導入についても検討する必要性
- 患者にとっての価値に基づく医療(value-based healthcare)を実現するためには、医療技術や医療サービス全般の質の向上についても議論を重ねていくべきである。
- HTAの結果が、最終的に患者利益につながっていない場合もあり、総合的で臨床現場の視点を含めた評価も検討されるべきである。(例:注射薬が経口薬に代わるなどのイノベーションがある一方で、その経口薬の処方を受けるために、病院内の別の診療科で受診する必要があるなど)
総合的な視点 3:
HTA導入によりイノベーションを正当に評価するためには、保健医療システム全体を見据えて、効率性や生産性を向上させることも同時に検討する必要性
- HTAによって優れていると評価され得る医薬品や医療機器を研究開発する環境を維持向上すべく、残薬問題の解消、多剤併用の解消、ジェネリックやバイオ後続品の普及推進などによる保健医療システム全体の効果的で効率的な運用も検討されるべきである。
■概要:
基調講演1:「Rebalancing Innovation & Sustainability – Japan’s case-」
- 鈴木康裕(厚生労働省 医務技監)

基調講演2:「医療技術評価(HTA)の学問的な変遷と今後の展開」
- 齋藤信也(岡山大学大学院 保健学研究科 教授/国際医薬経済・アウトカム研究学会(ISPOR)日本部会 会長))

ラウンドテーブル 「日本における医療技術評価(HTA)のあり方、課題、そして今後の期待」
■登壇者(五十音順・敬称略):
- 赤沢 学(明治薬科大学 公衆衛生・疫学研究室 教授)
- 五十嵐 中(東京大学大学院 薬学系研究科 医薬政策学 特任准教授)
- 市川 衛(医療ジャーナリスト / 日本放送協会(NHK) 科学・環境番組部 第1制作センター 制作局 ディレクター)
- Eun-Young Bae(慶尚大学校 薬学部 教授)
- 大西 佳恵(クリエイティブ・スーティカル 株式会社 日本代表)
- Chris Hourigan(ヤンセンファーマ株式会社 代表取締役社長)
- Kevin Haninger(米国研究製薬工業協会(PhRMA) インターナショナル・アドボカシー デピュティ・バイス・プレジデント)
- Koen Torfs(Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson グローバル・リエンバースメント&リアル・ワールド・エビデンス バイスプレジデント)
- 後藤 悌(国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科)
- 小谷 秀仁(パナソニック ヘルスケアホールディングス株式会社 代表取締役社長 /パナソニック ヘルスケア株式会社 代表取締役社長 最高経営責任者 最高技術責任者)
- 齋藤 信也(岡山大学大学院 保健学研究科 教授/国際医薬経済・アウトカム研究学会(ISPOR)日本部会 会長)
- 桜井 なおみ(キャンサー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長/がん対策推進協議会 患者委員)
- 白岩 健(国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 主任研究官)
- 田村 誠(米国医療機器・IVD工業会(AMDD)医療技術政策研究所 所長/一般社団法人 医療システムプランニング 代表理事)
- 中村 洋(慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 教授)
- 二木 立(日本福祉大学 相談役・大学院 特任教授)
- Philippe Fauchet(欧州製薬団体連合会(EFPIA Japan)副会長/ グラクソ・スミスクライン株式会社 代表取締役会長)
- 眞島 喜幸(特定非営利活動法人 パンキャンジャパン 理事長)
- 松本 純一(公益社団法人 日本医師会 常任理事)
- 眞鍋 馨(文部科学省 高等教育局 医学教育課 企画官)
■モデレーター:
- 乗竹 亮治(日本医療政策機構 事務局長)
- 菅原 丈二(日本医療政策機構 アソシエイト)

ラウンドテーブル 「日本における医療技術評価(HTA)のあり方、課題、そして今後の期待」では、2017年10月5日(木)までにおける、中医協での議論をもとに費用対効果評価を行っていく工程毎の課題、そして本格導入に向けて更に議論が必要である課題について議論がなされた。
尚、グローバル専門家会合で議論された内容について、主催者側が論点を抽出し、とりまとめたものであり、必ずしも登壇した方々の意見を代表するものではなく、本報告書発行時における最新の議論が反映されていない場合がある。
- 論点 1:質の高いデータを収集するシステムの必要性
- 論点 2:支払い意思額(WTP)を定めずに分析・評価する方法の可能性
- 論点 3:企業と再分析班の間で科学的でフェアなコミュニケーションの必要性
- 論点 4:再分析班でアナリストとして活躍できる人材のさらなる育成の必要性
- 論点 5:再分析結果の国民への公表の必要性とその方法
- 論点 6:アプレイザル方法の公平性・透明性を確保する必要性
- 論点 7:医療機器と医療品では分析・評価方法などにおいて、異なるアプローチをとる必要性
- 論点 8:評価結果を直接的に価格反映すべきかを含め、価格調整の明確な方針決定の必要性
- 論点 9:国民への説明責任・説明方法(議論の内容、評価方法、価格の提示など)を明確にする必要性
- 論点 10:費用対効果は良いが財政への影響が大きすぎる製品が増えた際、その影響をコントロールするための制度の議論の必要性
(写真:井澤 一憲)

2018年04月12日

2018年04月09日
日本医療政策機構(HGPI)特別朝食会のご案内
「2040年を展望した社会保障の課題と医療・介護の当面の焦点」
(ゲスト:厚生労働省 保険局長 鈴木 俊彦 氏)
「2040年を展望した社会保障の課題と医療・介護の当面の焦点」
(ゲスト:厚生労働省 保険局長 鈴木 俊彦 氏)
拝 啓 時下益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。
平素より、日本医療政策機構にご支援を頂きまして誠にありがとうございます。この度、当機構では、厚生労働省保険局長の鈴木俊彦氏をお招きし、下記の通り特別朝食会を開催することとなりました。
ご高承の通り、今年度は、診療報酬と介護報酬の同時改定が行われ、医療計画・介護保険計画の実施、国民健康保険の財政運営の都道府県単位化など節目の年となります。さらに第3期の医療費適正化計画も開始され、保険局では住民の予防・健康増進に向けた都道府県の取り組みを支援し、喫緊の課題である増大する国民医療費の適正化を進めています。また保健医療分野の各種データベースを連結・整備し、効果的に活用できる仕組みを通じて、健康づくりや医療・介護連携の体制構築を目指しています
鈴木氏はこれまで、社会・援護局長や年金局長などを歴任し、社会保障制度改革のターニングポイントに向き合ってこられました。保健医療分野での重要な局面にあるこの時期に、保険局の取り組みや今度目指す方向性をお示しいただき、今後に向けた日本のあるべき医療提供体制について、知見を語り、皆様と議論を重ねます。是非、ご臨席を賜りますようお願い申し上げます。
敬 具
記
- 日時: 2018年5月21日(月)08:00-09:15 (07:40開場)
- 場所: ホテルニューオータニ ガーデンコート 宴会場階 シリウスの間
- スピーカー: 鈴木 俊彦氏(厚生労働省 保険局長)
以上
申込締切日:2018-05-11
開催日:2018-05-21

2018年04月04日
NCD Global Forum for Civil Society
Diabetes Session
(市民社会のためのNCDグローバルフォーラム 糖尿病セッション)
フォーラムの部
Diabetes Session
(市民社会のためのNCDグローバルフォーラム 糖尿病セッション)
フォーラムの部
日時:2018年5月29日(火)13:00-17:00
(開場:12:40)(レセプション:17:00)
(開場:12:40)(レセプション:17:00)
会場:国際文化会館 岩崎小弥太ホール(東京都港区六本木5‐11‐16)
主催:特定非営利活動法人 日本医療政策機構(HGPI)
参加予定者:患者リーダー、医療政策専門家、議員、省庁関係者、産業界など(80名程度)
プログラム:(登壇依頼中・順不同・敬称略)
※内容や登壇者等、詳細は現時点でのものであり変更の可能性があります
12:40 開場
13:00-13:05 開会の辞(ビデオメッセージ)
黒川 清(日本医療政策機構 代表理事)
13:05-13:15 患者リーダーによるワークショップ・意見交換会 レポート
香川 由美(特定非営利活動法人患者スピーカーバンク 理事長)
香川 由美(特定非営利活動法人患者スピーカーバンク 理事長)
13:15-13:25 基調講演1「日本の非感染症疾患に対するイニシアチブと糖尿病における地域ケア」
検討中(厚生労働省 健康局健康課)
検討中(厚生労働省 健康局健康課)
13:25-13:45 基調講演2「日本における糖尿病ケアと政策的課題」
植木 浩二郎(国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター長)
植木 浩二郎(国立国際医療研究センター研究所 糖尿病研究センター長)
13:45-14:05 スペシャルセッション「糖尿病をはじめとする非感染症疾患に対する国際協力」
ケビン・ウォーカー(米国 Partnership to Fight Chronic Disease(PFCD)
(慢性疾患対策パートナーシップ)エグゼクティブディレクター)
ケビン・ウォーカー(米国 Partnership to Fight Chronic Disease(PFCD)
(慢性疾患対策パートナーシップ)エグゼクティブディレクター)
14:15-16:45 パネルディスカッション
「コミュニティにおける患者中心の糖尿病ケア・マネジメントの国際的潮流と展望」
パネリスト:
植木 浩二郎
オーレ ムルスコウ ベック(ノボノルディスクファーマ株式会社 代表取締役社長)
香川 由美
クリスティーナ・パーソンズ・ペレス(NCDアライアンス 能力開発ディレクター)
ケニス・E・トープ(PFCD 代表理事)
その他検討中
「コミュニティにおける患者中心の糖尿病ケア・マネジメントの国際的潮流と展望」
パネリスト:
植木 浩二郎
オーレ ムルスコウ ベック(ノボノルディスクファーマ株式会社 代表取締役社長)
香川 由美
クリスティーナ・パーソンズ・ペレス(NCDアライアンス 能力開発ディレクター)
ケニス・E・トープ(PFCD 代表理事)
その他検討中
16:50-17:00 閉会の辞
武田 飛呂城(特定非営利活動法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会(J-CDSMA) 事務局長)
武田 飛呂城(特定非営利活動法人 日本慢性疾患セルフマネジメント協会(J-CDSMA) 事務局長)
17:00- レセプション
2018年03月28日

2018年03月23日
当機構が行った「働く女性の健康増進に関する調査2018」の調査結果がBusiness Insiderの記事に引用されました。
詳細はこちらに掲載されています。

2018年03月22日




